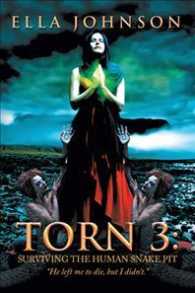内容説明
仙台ではさまざまな団体が子どもの遊び場づくりに取り組んできた歴史があり、「冒険あそび場―せんだい・みやぎネットワーク」は代表的な存在。子どものための独創的な遊び空間をつくりあげる活動の中、2011年の東日本大震災、そして2020年からの新型コロナウイルスという大きな試練を創意と実践によって乗り越えようとしている。本書は、その貴重な活動記録やプレーリーダーが出会った子どもたちに注目し、本来の子どもの遊びと遊び空間の意義について考える。震災後の緊張状態の中、またコロナ禍の中で遊ぶ仙台の子どもたちの姿が、私たちに語りかけてくることは何か―。
目次
プロローグ 仙台と震災の記憶
1 東日本大震災と子ども
2 震災が生んだ巡回型遊び場
3 プレーリーダーが見た子どもの遊び
4 コロナ禍の冒険広場と子どもの遊び
エピローグ “すき間”という宝物
著者等紹介
加藤理[カトウオサム]
宮城県仙台市生まれ。文教大学教育学部教授。子どもの文化を視点にしながら、教育の諸問題や子どもが直面する課題について研究。仙台の子どもの文化史についても研究。著書に『“めんこ”の文化史』(1996年、久山社、日本児童文学学会奨励賞受賞)、『駄菓子屋・読み物と子どもの近代』(2000年、青弓社)、『「児童文化」の誕生と展開―大正自由教育時代の子どもの生活と文化―』(2015年、港の人、日本児童文学学会賞受賞)、他
根本暁生[ネモトアキオ]
東京都生まれ。認定NPO法人冒険あそび場―せんだい・みやぎネットワーク理事・プレーリーダー。学生時代、阪神淡路大震災の救援活動で冒険遊び場と出会い、大学院修了後は東京都世田谷区の活動団体でプレーリーダー、後に運営スタッフを務める。2008年、海岸公園冒険広場の運営にあたるため仙台に。東日本大震災以降は、巡回型遊び場活動の展開にも力を注ぐ
三浦忠士[ミウラタダシ]
宮城県仙台市生まれ。認定NPO法人冒険あそび場―せんだい・みやぎネットワークプレーリーダー。学生時代、子どもの造形的な遊びに関心をもち、博士論文のテーマとする。2010年より現団体に所属し、海岸公園冒険広場で勤務。東日本大震災以降は巡回型遊び場活動にも力を注ぐほか、仙台市子育てふれあいプラザ若林「のびすく若林」で乳幼児親子のための外遊びの環境づくりにも取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。