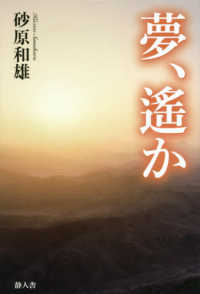内容説明
限りなく世の安寧を願う儒者の探究は、西洋音楽に先んじてどの音でも主音になりうる音律理論に到達した。天・地・人すべてを結ぶユニークな理念を紹介。
目次
1 楽とは何か(経学としての楽;礼楽思想の展開)
2 音律学と律暦思想(三分損益法;劉〓(きん)の律暦思想
朱子学の音律論―朱熹・蔡元定『律呂新書』)
3 中華の楽、夷狄の楽―「雅楽」「胡楽」「俗楽」(隋・唐楽制と外来音楽;北宋・陳暘『楽書』における楽懸編成)
4 朱載〓(いく)の平均律(平均律の発明;律暦合一思想)
5 江永と河図・洛書
著者等紹介
田中有紀[タナカユウキ]
1982年、千葉県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。現在、立正大学経済学部専任講師。中国思想史・中国音楽史専攻。2008年より2010年まで、松下国際スカラシップにより、北京大学哲学系に留学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
14
中国における音楽を論じるが、中国では「楽」は儒教の儒教の重要な学問、つまり、芸術よりは思想・哲学として論じられてきた。興味深かったのが3章、隋唐から北宋にかけて、夷犾の音楽を取り入れていく過程での議論。夷犾の楽を演奏する正当性を『周礼』に求め、中国が夷犾の音楽を掌握することが、天下を統一するのにかかせない、と解釈したとする。本論は清朝までの儒教思想の中の楽だが、「近代中国における国楽と儒教の関係について論じた「おわりに」も興味深かった。2020/09/01
ルンブマ
4
中国における音楽理論を築いたのは、作曲家や音楽家ではなく、儒者たちであったとされる。彼らは当時の統治者のために、または自らの思想と合致させるために、いかなる「楽」(音にまつわる文化の総称)が理想的であるかを論じ、楽制(人格の完成、政治の安定のための思想)に反映させようとした。本書では、春秋戦国時代から清代までの漢籍を通して儒者の思想をたどり、「楽」がどのような思想的意義を持ち、中国において展開していったかを考察している。2021/02/08