目次
序 易とはなにか―知られているようで、知られていない易(易には二つの顔がある;易ということば)
1 『易経』を読むために知っておくこと(『易経』のなりたち―易の仕組みは、どのようなものか;易の専門用語とは―『易経』を読むために ほか)
2 六十四卦の意味すること―「周易序卦伝」を読む(乾為天;坤為地 ほか)
3 易の用い方(四つの易の用い方;君子の易の用い方―平時の時・行動の時 ほか)
補 易はどのように学ばれてきたか―易学小史粗描(易の伝来;朝廷の易学 ほか)
著者等紹介
黒岩重人[クロイワシゲト]
1946年長野県生。法政大学文学部卒業。故景嘉師に師事して、易経及び陰陽五行思想を学ぶ。易・陰陽五行に関する諸講座の講師。西東京市にて、「易・陰陽五行の会」講師。「東京新宿易の会」主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ピンガペンギン
30
易には、占いとしての易と哲学としての易があり、この本は哲学としての易の立場で書かれている。四書五経の筆頭であり、明治の初頭までは知識層(本に渋沢栄一の農民の父親が易の知識で子に諭したエピソードあり)必読だった。老子の哲学(魏の王弼)や、天台宗(明代)などの立場からも解釈し読まれてきた。陰陽というのは、ふたつの別のものではなく、説明のために分けて考えるのみだと。実際は一つのものの裏表だという考え方。易経の最後は火水未済で、事がいまだ完成していないことをいう。2026/01/07
デビっちん
30
再読。今まで読んだ本に少なからず記載されていたので、吉凶判断が易学習の1つの柱だと思っていました。しかし、易には道徳も善悪 も、良い卦、悪い卦というものもなく、ただ陰と陽の変化の様式があるだけだとわかりました。ここから、八つの卦をもって、宇宙間の一切の物・現象を象り、表現することが易なんだとも知りました。もう1つスッキリしたことは、易には思想・哲学の側面と占いとしての側面があるということです。前者ばかり学んでいると理に傾きやすく、後者ばかりですと象・数に傾きやすいようです。2017/10/18
デビっちん
27
著者は「序卦伝」という書の読み下し文から易の初学を始めることを勧めています。易の本ではよくある、乾の卦から学習を始めると、挫折しやすいからです。「序卦伝」は短い文章の中に易の配列にしたがって、卦の名前とその代表的な意味が記載されていますから、全体像の把握に役立ちます。卦の解説は少ないながらも、巻末には易が伝承された歴史や日本での発展の様子が人物とともに記載されていて、特に日本での易史は初めてだったので新鮮でした。+部分の分析の前に全体像をとらえているだろうか?2017/10/17
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
3
黒岩門下生の方に診てもらったら読みがすごかったので、どんなものかと手にとりました。次に3巻の全釈が控えているので、そこにいたるまでの触り。これなら本田済の易のほうがおすすめ。2020/02/19
koHey
0
“『易経』を読むために知っておくこと”の章は、初心者の自分にとって、これから理解するのに大変なヒントとなりました。まずは、「周易序卦伝」の読み下し文を何度も読み直したいと思います。2015/07/25
-
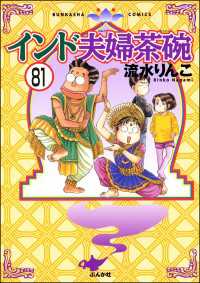
- 電子書籍
- インド夫婦茶碗(分冊版) 【第81話】…
-
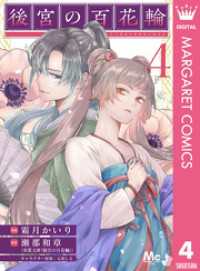
- 電子書籍
- 後宮の百花輪 4 マーガレットコミック…
-
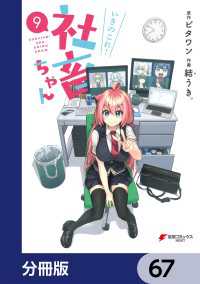
- 電子書籍
- いきのこれ! 社畜ちゃん【分冊版】 6…
-
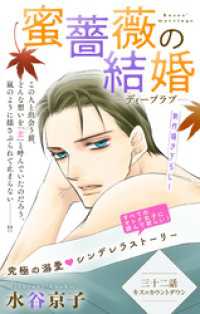
- 電子書籍
- Love Silky 蜜薔薇の結婚 s…
-
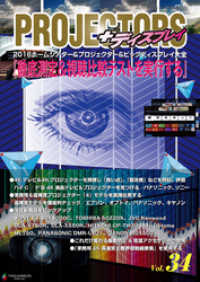
- 電子書籍
- PROJECTORS Vol.34




