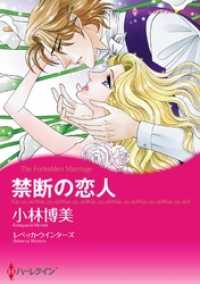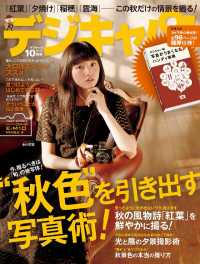内容説明
大正元年から昭和二〇年の敗戦まで、およそ三四年間に福祉の分野は時代の大きな波をかぶっている。明治期の流れを残していた慈善事業、大正デモクラシーと共にひろがって行った社会事業、昭和一三年の厚生省の設置とともに総力戦体制の一翼を担った厚生事業、日本の福祉の近代史の中ですでに事業の名称が確定しているこれらの時代、その時期に青春を送り、壮年期を過ごした人びとは、深い使命感と強いエネルギーを存分に発揮して、今日でいう福祉活動に取り組んでいた。
目次
1 ひろがる生活・ひろがる消費―大正デモクラシーを背景に(東京の米騒―日比谷公園;公設市場・公設食堂―渋谷・神楽坂;消費組合「西郊共働社」―中野・高円寺)
2 地域に展開した若者エネルギー―託児所そしてセツルメント(日本女子大桜楓会託児所―小石川から大塚へ;東京帝大セツルメント―本所・錦糸町・押上)
3 施設の暮らし―公立救済施設の移り変わり(財団法人浴風会―杉並・高井戸;東京市養育院―大塚から板橋へ)
4 スラム街の拡散―新宿へ・板橋へ(新宿・旭町―新宿駅前;板橋・岩の坂―板橋本町)
著者等紹介
河畠修[カワバタオサム]
1935年東京生まれ。60年東京大学文学部卒業。NHKのディレクターとして福祉系番組の制作に従事。93年愛知みずほ大学人間福祉学部教授。97年浦和短期大学教授、2003年浦和大学総合福祉学部教授(高齢社会論・福祉文化論担当)を歴任。07年3月定年退職。この間、日本福祉文化学会副会長なども務める。現在、世田谷区福祉人材育成・研修センター長。京都女子大学大学院講師。日本エッセイストクラブ会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。