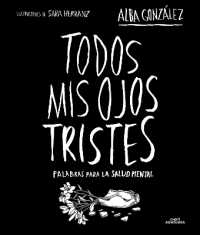内容説明
一八世紀後半から一九世紀初頭の徳川期日本においてひとつの潮流を形成した本居宣長の古学古道論が、「世界を再‐結集する」信条や世界観をどのように創出しようとしたのかを、差異と反復をめぐる新たな思考を通して考察する。
目次
序章 本居宣長における反復という問題(『真暦考』;「数む」と「賦む」;横領と形式性)
第1章 始原の言葉(始原の言葉;「ツギツギニ」―前‐テクストの構成規則の論理化;神代と人代;修辞学的飛躍)
第2章 歌論の位相(『あしわけをぶね』の情‐辞と「文」;『石上私淑言』における「文」と「ウタフ/ヨム」)
第3章 「もののあはれ」の美学的構造とその反‐可能性(宣長「もののあはれ」論の形式性;「物の哀をしらする」の論理;「好」とナショナル・ペタゴジーの成立;美的体験の再構成)
終章 古道と権道(「御契約」と「御民」;古道と権道;「泣き悲しみこがれる」主体;おわりに)
著者等紹介
友常勉[トモツネツトム]
1964年、生まれ。1989年、法政大学文学部卒業、東京外国語大学大学院地域文化研究科博士後期課程中退。2004年、博士(学術)取得(東京外国語大学)。専攻、日本近代史・日本思想史。現在、廈門大学外文学院専家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
皆様の「暮らし」を応援サポート
10
『玉勝間』の「やしなひ子」における「非連続性の承認」を水戸学や太宰春台の血統主義と「ナショナリズムの言説を構成する表裏一体の議論」とし、その再結集=「養子縁組」を企む本居宣長の思想を、めっちゃ晦渋な文章で解説し、宣長の解明した「〈生〉がつねに断絶する〈反復〉という線分から構成されている」ことが「歴史における〈生〉の充溢の根拠をしめす」ので、それをナショナリズムに横領する宣長から奪い返し「ひとびとにとって普遍的な〈生〉の歴史的瞬間を正当に位置づけること」で対抗しよう!という本‥‥‥ほら、めっちゃ晦渋でしょ?2025/03/21
-
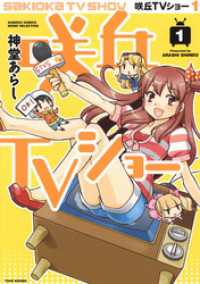
- 電子書籍
- 咲丘TVショー(1) バンブーコミック…