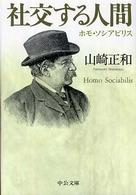出版社内容情報
執筆者一覧(執筆順)
田中敦夫 京都大学 工学部 工業化学科
(現) 同大学院 工学研究科 合成・生物化学専攻 教授
飯田高三 関西ペイント(株) 技術研究所 第3部
(現) 新潟大学 工学部 機能材料工学科 教授
牧島亮男 科学技術庁 無機材質研究所
(現) 北陸先端科学技術大学院大学 新素材センター 教授
原 龍男 科学技術庁 無機材質研究所 ;神鋼ファウドラー(株)
(現) 神鋼パンテック(株) 技術研究所 技術開発本部 開発企画室 主任研究員
朝倉哲郎 東京農工大学 工学部
浦上 忠 関西大学 工学部
梅澤昌兵 早稲田大学 理工学部 応用化学科
平田 彰 早稲田大学 理工学部 応用化学科 教授
平野二郎 日本油脂(株) 取締役 筑波研究所 所長
船田 正 日本油脂(株) 筑波研究所
中島寛樹 京都大学 工学部 工業化学科
橋本健治 京都大学 工学部 化学工学科
(現) 福井工業大学 工学部 応用理化学科 教授
白井義人 京都大学 工学部 化学工学科
(現) 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能専攻 教授
高藤慎一 雪印乳業(株) 技術研究所
中西弘一 キリンビール(株) 技術開発部
(現) 同・研究開発部 応用開発センター 主任研究員
堀津浩章 岐阜大学 農学部
中島良和 三井製糖(株) 研究開発部
山崎幸苗 工業技術院 微生物工業技術研究所
(現) 産業技術総合研究所 生物遺伝子資源研究部門 生理活性物質開発研究グループ グループ長
梶原 茂 工業技術院 微生物工業技術研究所
(現) 産業技術総合研究所
吉川展司 三菱化成(株) 総合研究所
(現) ファイザー製薬(株) 中央研究所 主任研究員
光田 賢 住友化学工業(株) 宝塚総合研究所
(現) 農業化学品研究所 グループマネージャー
永井史郎 広島大学 工学部 醗酵工学科
(現) 同・ヤエガキ醗酵技研(株) 技術開発研究所 所長;専務取締役
西尾尚道 広島大学 工学部 醗酵工学科
(現) 同・大学院 先端物質科学研究科 分子生命機能科学専攻 教授
森 直道 日立プラント建設(株) 研究所第一部
(現) 環境装置事業部 開発部 主管技師
角野立夫 日立プラント建設(株) 研究所第一部
中村裕紀 日立プラント建設(株) 研究所第一部
中島一郎 日立プラント建設(株) 研究所第三部
藤原信明 大阪府立産業技術総合研究所 化学部
都宮孝彦 日本化学機械製造(株) 技術開発研究室
島田和武 東北大学 薬学部 薬品分析化学教室
(現) 金沢大学 薬学部 薬品分析学研究室 教授
南原利夫 東北大学 薬学部 薬品分析化学教室
(現) 東北大学名誉教授;星薬科大学名誉教授
(所属は1988年8月時点。( )内は2001年11月現在)
構成および内容
第1章 固定化生体触媒-最近の進歩 田中渥男
1.はじめに
2.研究開発動向
3.進歩の評価と展望
第2章 新しい固定化法
1.光硬化性樹脂による包括固定化 飯田高三
1.1 はじめに
1.2 光硬化性樹脂と光架橋反応
1.3 光硬化性樹脂を用いる固定化装置
1.4 適用例
1.4.1 酵素の固定化
1.4.2 エタノール発酵
1.4.3 Ara A の生成
1.4.4 排水処理への適用
1.4.5 油脂,脂肪酸の反応
1.4.6 ステロイドの変換
1.4.7 酵素,微生物膜センサー
1.5 スチルバゾリウム系光硬化性樹脂
1.6 おわりに
2.多孔質セラミックスへの固定化 牧島亮男・原龍男
2.1 はじめに
2.2 バイオプロセス用のバイオセラミックスの特長
2.3 応用例
2.3.1 固定化酵素
2.3.2 微生物の固定化
2.3.3 分離,精製への応用
3.絹フィブロインによる固定化
3.1 はじめに
3.2 絹フィブロインの構造
3.2.1 家蚕絹フィブロインの構造
3.2.2 エリ蚕絹フィブロインの構造
3.3 絹フィブロインの構造転移
3.4 酸素固定化材料への応用
3.4.1 包括法による酸素固定化
3.4.2 担体結合法による酸素固定化
3.5 企業の動向
3.6 今後の展望
第3章 新しいバイオリアクター 浦上 忠
1.酵素固定化分離機能膜
1.1 酵素固定化分離膜の必要性
1.1.1 酵素の固定化
1.1.2 酵素固定化膜
1.2 酵素固定化膜の調製
1.2.1 担体結合法
1.2.2 橋かけ法
1.2.3 包括法
1.3 酵素固定化膜の性質と性能評価
1.3.1 安定性
1.3.2 基質特異性
1.3.3 pH依存性
1.3.4 電極による性能評価
1.3.5 動力学的性能評価
1.3.6 膜透過性による性能評価
1.4 酵素固定化分離機能膜の種々の分野への応用の可能性
1.4.1 加水分解反応への応用
1.4.2 分析への応用
1.4.3 医療への応用
1.4.4 環境浄化
1.4.5 濃縮輸送への応用
1.5 将来展望と問題点
1.5.1 将来展望
1.5.2 問題点
2.生成物分離を伴うバイオリアクター 梅澤昌平・平田彰
2.1 はじめに
2.2 バイオプロセスにおける反応-背生物分離同時操作に関する既往研究
2.2.1 固定化酵素反応-吸着分離同時操作法
2.2.2 発酵-浸透気化膜分離同時操作法-エタノールの製造-
2.2.3 固体発酵-ガス放散同時操作法-エタノールの製造-
2.2.4 固体化酵素反応-含浸液膜分離同時操作法-光学異性体の分離-
2.2.5 発酵-水性二相分配法同時操作-ステロイドの変換-
2.2.6 固定化酵素反応-溶解同時操作-グリセドの連続合成および油脂の加水分解
2.3 アスパルテーム前駆体(Z-APM)の連続合成
2.3.1 固定化酵素反応-晶析同時操作(水-相系反応)
2.3.2 固定化酵素反応-正抽出-晶析同時操作(水-酢酸エチル二相系反応)
2.4 おわりに
3.多段式不均一系バイオリアクター 平野二郎・船田正
3.1 はじめに
3.2 バイオリアクターの現状
3.2.1 均一反応と不均一系反応
3.2.2 従来の不均一バイオリアクター
3.2.3 不均一系バイオリアクターの実用化
3.3 不均一系バイオリアクターの開発
3.3.1 分散板-水中への油の分散
3.3.2 FN-1 型バイオリアクター(単段式不均一バイオリアクター)
3.3.3 FN-2型バイオリアクター(多段式不均一バイオリアクター)
3.3.4 FN型バイオリアクターの特徴
3.4 応用展望
3.5 おわりに
4.固定化植物細胞 中島寛樹・田中渥男
4.1 はじめに
4.2 固定化の意義
4.3 固定化方法
4.4 固定化植物培養細胞による有用物質の生産例
4.4.1 生化学的変換
4.4.2 サルベージ合成
4.4.3 新生合成
4.5 固定化ラベンダ培養細胞による青色色素の生産
4.5.1 固定化に用いる細胞懸濁液の調製
4.5.2 固定化担体の選択
4.5.3 固定化細胞の増殖
4.5.4 固定化細胞の色素生産と担体の効果
4.5.5 固定化細胞の繰り返し使用
4.6 おわりに
5.固定化ハイブリドーマによるモノクローナル担体の生産 橋本健治・白井義人
5.1 はじめに
5.2 従来の動物細胞培養法の問題点
5.3 高密度培養法
5.4 固定化ハイブリドーマの現状
5.4.1 包括固定化法
5.4.2 ホローファイバー法
5.4.3 その他
5.5 固定化ハイブリドーマの特徴
5.5.1 固定化担体内での動物細胞の生育
5.5.2 モノクローナル抗体連続生産実験
5.6 固定化ハイブリドーマの問題点と展望
5.6.1 包括固定化法
5.6.2 ホローファイバー法
5.7 おわりに
第4章 バイオリアクターの応用
Ⅰ 食品
1.乳製品(乳糖分解乳,カゼイン分解物) 高藤慎一
1.1 はじめに
1.2 乳糖分解乳の製造
1.2.1 固定化β-ガラクトシダーゼ
1.2.2 スナム社の固定化β-ガラクトシダーゼ
1.2.3 住友化学工業社の固定化β-ガラクトシダーゼ
1.3 カゼインの分解物の製造
1.4 おわりに
2.ビール 中西弘一
2.1 はじめに
2.2 固定化酵母によるビール醸造
2.2.1 固定化酵母によるビール醸造の利点と欠点
2.2.2 ビール香味の問題
2.2.3 新しいビール醸造用バイオリアクターシステム
2.3 今後の展開と課題
2.3.1 固定化担体の問題
2.3.2 雑菌汚染対策
2.3.3 その他の課題
2.4 おわりに
3.醤油 堀津浩章
3.1 はじめに
3.2 醤油産業の近代化
3.3 これからの醤油
3.4 現在の醤油製造法
3.4.1 製麹
3.4.2 諸味
3.4.3 製成
3.5 バイオリアクター工程を新機軸に導入した新しい醤油製造法
3.5.1 標的
3.5.2 酵母発酵原液の調製
3.5.3 醤油酵母Z.rouxii および C.versatilis 固定化増殖菌体直列二連式発酵法による発酵試験
3.6 おわりに
4.パラチノース 中島良和
4.1 はじめに
4.2 固定化酵素の調整法
4.3 固定化酵素の性質
4.4 パラチノースの製造法
4.5 結晶パラチノースおよびパラチノース蜜の特性
4.6 虫歯予防用代替甘味料としての有用性
4.7 おわりに
Ⅱ 化学品
5.(-)-マンデル酸 山崎幸苗・梶原茂
5.1 はじめに
5.2 共役酸化還元酵素反応による(R)-マンデル酸の生産
5.2.1 NADH再生反応用酵素
5.2.2 主反応用ベンゾイルギ酸還元酵素の開発
5.2.3 共役酵素系の固定化と連続反応
5.3 実用化への課題と展望
5.3.1 ベンゾイルギ酸の製造
5.3.2 高比活性の FDH
5.3.3 ベンゾイルギ酸の製造
6.シス,シスムコン酸 吉川展司
6.1 はじめに
6.2 ムコン酸を中心とする安息香酸の発酵分野での利用研究
6.2.1 国内の研究
6.2.2 海外の研究
6.3 安息香酸からムコン酸生産条件への変換反応
6.4 これまでの研究成果
6.4.1 スクリーニングと菌株育種
6.4.2 安息香酸からムコン酸生産条件の検討
6.4.3 連続型リアクター化の検討
6.5 シス,シス-ムコン酸の用途
6.5.1 特徴
6.5.2 用途
7.殺虫剤-光学活性なピレスロイド系殺虫剤- 光田 賢
7.1 はじめに
7.2 天然ピレトリン類
7.3 合成ピレスロイド
7.4 合成ピレスロイドの立体構造と効力の相関
7.5 光学活性化
7.6 (S)-4-Hydroxy-3-metyl-2-(2-propynyl)cyclopentenone の製造
7.6.1 酵素によるHMPC 光学分割
7.6.2 酵素反応と化学反応の組み合わせによる(S)-HMPC の製造
7.7 (S)-α-Cyano-3-phenoxy-benzylalcohol(CPBA) の製造
7.8 おわりに
8.メタン生成細菌による有用物質の生産 永井史郎・西尾尚道
8.1 はじめに
8.2 休止菌体による有用物質の生産
8.2.1 NADPH の生産
8.2.2 ギ酸の生産
8.2.3 水素ガスによるキシロースのキシリトールへの生化学的変換
8.3 増殖菌体による有用物質生産
8.3.1 メタン生成反応とビタミンB12 ,F430
8.3.2 メタン生成細菌によるビタミンB12生産
8.3.3 各種テトラピロール化合物の生産
8.4 おわりに
Ⅲ その他
9.廃水処理技術 森 直道・角野立夫・中村裕紀・中島一郎
9.1 はじめに
9.2 微生物の固定化
9.2.1 固体化担体・材料
9.2.2 固定化材料の選択
9.3 水処理への適用
9.3.1 BOD の処理
9.3.2 BOD・窒素(N)処理について
9.4 水処理における固定化微生物の課題
9.4.1 固定化微生物によるSS 除去
9.4.2 酵素および基質の透過性
9.5 おわりに
10.フィルムからの銀の回収 藤原信明・都宮孝彦
10.1 はじめに
10.2 X線フィルムからの銀回収の現状
10.3 新しい酵素処理法
10.3.1 酵素
10.3.2 市販酵素との比較
10.3.3 分解の経過
10.3.4 分解条件
10.3.5 繰り返し処理
10.4 銀回収の連続処理システム
10.4.1 装置の構成と工程
10.4.2 装置に関しての考察
10.5 今後の展望
10.6 おわりに
11.高速液体クロマトグラフィー検出システム 島田和武・南原利夫
11.1 はじめに
11.2 酵素の固定化
11.3 各種化合物分析への応用
11.3.1 ステロイド化合物
11.3.2 各種抱合体
11.3.3 アセチルコリン類
11.3.4 クレアチンキナーゼ・アイソザイムの活性測定
11.3.5 その他の化合物
11.4 おわりに
内容説明
本書は、月刊『BIO INDUSTRY』をはじめ、シーエムシーが保有する有効な技術情報を編集して、1988年当時、最新のバイオリアクターの研究開発の状況をまとめたものである。
目次
第1章 固定化生体触媒―最近の進歩(研究開発動向;進歩の評価と展望)
第2章 新しい固定化法(光硬化性樹脂による包括固定化;多孔質セラミックスの固定化 ほか)
第3章 新しいバイオリアクター(酵素固定化分離機能膜;生成物分離を伴うバイオリアクター ほか)
第4章 バイオリアクターの応用(食品;化学品 ほか)
-

- 電子書籍
- 主人公と悪役の育成をしくじりました【タ…
-

- 電子書籍
- フレンシアの華【タテヨミ】第36話 p…