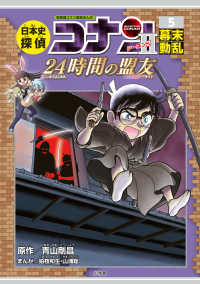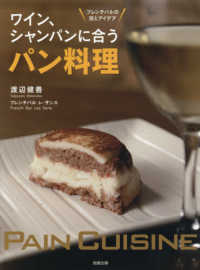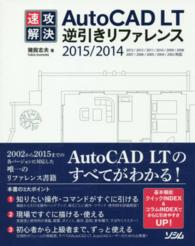出版社内容情報
★エレクトロニクスに無くてはならない基板材料と最新技術の解説
★素材・基材・受動素子内蔵基板,フレキシブル基板,多層基板等を網羅
刊行にあたって
1980年から90年代のPCを中軸としたデジタル革命第1波が飽和状態に達し,PCと家電が融合したデジタル情報家電を中軸とする第2波が2000年から10年にかけて飛躍の段階を迎えている。デジタルビデオデスク(DVD),デジタルスチールカメラ(DSC),そしてプラズマディスプレイ(PDP)に情報交換機能が付与されてネットワーク化が進んでいる。携帯電話,パーソナルデジタルアシスタンツ(PDA),カーナビ等のユビキタス社会を支えるモバイル電子機器は,その機能を融合させて究極のウエアラブル携帯情報端末へと進化すると予想されている。従って,多機能,且つ大容量のデータを高速に伝送する高い性能を兼ね備えた機器を小型・軽量・薄型で実現することが必要不可欠となっている。このような背景から,デジタル情報家電を中軸とするデジタル革命第2波では,LSIのより一層の高速・大容量化等の性能向上とロジックからメモリまでシステムとしてまとめるシステム・オン・チップ(SoC)としての高機能化が進む。これと同時に,これらLSIの実装方式も各種機能を有するLSIを1つのパッケージにシステムとしてまとめるシステム・イン・パッケージ(SiP),メモリチップを三次元に積層して大容量化を実現し,更には三次元方向に機能をシステム化したスタック型SiPへと加速度的に進化している。これらを支える主要技術としてLSIと並び多層プリント配線板が有り,SiPのインターポーザから部品実装の母体となるマザーボードまで,多種,多様の基板が開発されている。
プリント配線板は"電気絶縁性基板の表面又はその内部電気設計に基づく導体パターンを導体性材料で形成し固着したもの"と定義され,20世紀初頭に提案された。その後,20世紀中期に発展期に入り,1960年頃から導体パターンを2層,3層と多層化した基板が出現している。カメラ一体型ビデオ等の家電製品から大型計算機等の産業機器まで用途に応じた多層プリント配線板が開発されてきた。大型計算機では,究極の高密度配線を実現するため46層の多層化が進められた。使用される材料もエポキシ樹脂から耐熱性の優れたポリイミド樹脂,更には,信号伝送性向上のために低誘電率樹脂が開発された。1990年に入り,配線効率を上げるため,配線を一層ごとに逐次に形成して,必要な個所だけビアホールで接続するビルドアップ多層板が適用され始めた。これを可能にするため,フォトでビアホールが形成でき,そのまま絶縁層として使用できる感光性樹脂が開発された。この間,導体材料である銅箔の極薄化,ロープロファイル化,補強材料であるガラスクロスの低誘電率化,低熱膨張化等の高性能化も進められた。ここ数年は,総論で詳述される多岐に亘るインターポーザ用配線基板が開発され,SiPに要求される多様な機能を実現している。
"エレクトロニクス実装用高機能性基板材料"と題した本書は,プリント配線板の基本に立ち返ると共に,その急激な変革を支えている材料の最新技術をまとめたものである。貴重な時間を割いて各章を担当して戴いた方々に深謝すると共に,本書が更なる技術革新への一助となることを祈念している。
柿本雅明,高橋昭雄
--------------------------------------------------------------------------------
高木清 高木技術士事務所
坂本勝 (株)日鉱マテリアルズ GNF開発センター センター長
宮里桂太 日東紡績(株) 技術開発部 加工開発グループ 課長
吉澤正和 大日本インキ化学工業(株) 機能性ポリマ技術本部 エポキシ樹脂技術グループ 主任研究員
池田謙一 日立化成工業(株) 下館事業所 配線板材料ビジネスユニット 下館プロダクトセンタ 開発グループ 主任研究員
米本神夫 松下電工(株) 電子材料分社 電子基材事業部 商品技術グループ 課長
近藤至徳 三菱ガス化学(株) 東京研究所 主席研究員
天羽悟 (株)日立製作所 材料研究所(日立研究所内) 電子材料研究部 研究員
片寄照雄 旭化成エレクトロニクス(株) 電子材料事業部 技術部長
藤原弘明 松下電工(株) 電子材料本部 電子材料R&Dセンター 主査技師
吉川淳夫 (株)クラレ 機能材料事業部 電材事業推進部 材料開発グループ グループリーダー
竹澤由高 (株)日立製作所 日立研究所 電子材料研究部 主任研究員
平石克文 新日鐵化学(株) 電子材料研究所 マネジャー
中道聖 住友ベークライト(株) 回路材料研究所 研究部 主任研究員
本多進 基板・実装技術NPO法人 サーキットネットワーク 理事
宝蔵寺智昭 デュポン(株) エレクトロニクステクノロジーズ マーケットデベロップメントスペシャリスト
山本和徳 日立化成工業(株) 総合研究所 主管研究員
島田靖 日立化成工業(株) 総合研究所 主任研究員
島山裕一 日立化成工業(株) 総合研究所 研究員
平田善毅 日立化成工業(株) 総合研究所 研究員
神代恭 日立化成工業(株) 総合研究所 研究員
--------------------------------------------------------------------------------
序論 総論
第1章 プリント配線板および技術動向(高木清)
1. プリント配線板とは
2. 電子機器の実装とプリント配線板の特性
2.1 実装階層
2.2 プリント配線板の配線ルール
2.3 電気特性
2.3.1 直流的特性
2.3.2 交流的特性
3. 多層プリント配線板における接続
3.1 表面パターンの接続
3.2 Z方向の接続
4. 多層プリント配線板のプロセス
4.1 めっきスルーホール法
4.2 パネルめっき法とパターンめっき法
4.3 めっきを用いたビルドアッププロセス
4.4 導電性ペーストを用いるビルドアッププロセス
4.5 一括積層法
4.5.1 片面銅張積層板-めっき柱による一括積層方法
4.5.2 パターン転写による一括積層法
4.5.3 めっきによるパターンの転写‐フラックス性樹脂接着による一括積層法
4.6 フレキシブルプリント配線板
5. プリント配線板の製造における最近の技術
5.1 スタックビアの接続技術
5.2 平坦面への絶縁層,導体層接着
5.2.1 導体上への絶縁体の接着
5.2.2 樹脂上への無電解銅めっきの接着
6. プリント配線板の信頼性
6.1 接続の信頼性
6.2 絶縁の信頼性
7. おわりに
第1編 素材
第2章 プリント配線基板の構成材料
1. 銅箔(坂本勝)
1.1 プリント配線板用銅箔
1.2 リジッドプリント配線板用銅箔
1.3 フレキシブルプリント配線板用銅箔
2. ガラス繊維とガラスクロス(宮里桂太)
2.1 はじめに
2.2 種類
2.3 製造方法
2.4 基本特性と最近の要求特性
3. 樹脂(吉澤正和)
3.1 はじめに
3.2 エポキシ樹脂の構造と特徴
3.3 エポキシ樹脂の製造方法
3.3.1 フェノール性OH基とECH(エピクロルヒドリン)の反応による製造方法(1段法)
3.3.2 エポキシ樹脂中のエポキシ基を一部他の化合物で変性する製造方法(2段法)
3.4 プリント配線基板に使用されるエポキシ樹脂/硬化剤(含む封止剤用途)
3.4.1 臭素系エポキシ樹脂
3.4.2 多官能型エポキシ樹脂
3.4.3 その他特殊エポキシ樹脂
3.4.4 硬化剤
3.5 プリント配線板用樹脂に求められる特性
3.5.1 低誘電率/低誘電正接
3.5.2 耐熱性(Tg)
3.5.3 耐熱分解性
3.5.4 低線膨張率
3.5.5 耐湿性(低吸水率)
3.5.6 その他
3.6 最近のトピックス
3.6.1 環境対応材料
3.6.2 その他
3.7 おわりに
第2編 基材
第3章 エポキシ樹脂銅張積層板(池田謙一)
1. はじめに
2. エポキシ樹脂
3. 硬化剤ほか
4. ガラス布
5. 銅箔
6. 銅張積層板の製造方法
7. 規格
8. 技術動向
9. FR-4エポキシ基板材料
10. CEM-3,CEM-1,FR-3基板材料
11. 環境対応多層材料
12. 高Tgガラスエポキシ多層材料
13. 高Tg高弾性低熱膨張多層材料
14. おわりに
第4章 耐熱性材料
1. ガラス布基材ポリイミド樹脂銅張り積層板(米本神夫)
1.1 動向
1.2 ポリイミド樹脂材料の特徴
1.3 特性
1.4 多層化成形条件
1.5 今後の動向
2. BTレジン材料(近藤至徳)
2.1 BTレジンとは
2.2 シアネート化合物
2.3 BTレジンの製法
2.4 BTレジンの特徴
2.5 BTレジン銅張積層板
2.5.1 パッケージ材料用BTレジン銅張積層板 CCL-HL830,CCL-HL832,CCL-HL832EX,CCL-HL832HS
2.5.2 高速・高周波回路用BTレジン銅張積層板および積層用材料 CCL-HL950K,CCL-HL870TypeM,GMPL195
2.5.3 ICカード・LED用BTレジン銅張積層板CCL-HL820,CCL-HL820W,CCL-HL820WTypeDB
2.5.4 バーンインボード用BTレジン銅張積層板 CCL-HL800
2.5.5 ハロゲンフリーBTレジン銅張積層板 CCL-HL832NB,CCL-832NX
2.6 樹脂付き銅箔材料CRS-401,CRS-501,CRS-601
2.7 今後の展開
第5章 高周波用材料
1. 多官能スチレン系高周波用材料(天羽悟)
1.1 はじめに
1.2 多官能スチリル化合物の構造と特性
1.3 多官能スチリル化合物の改質
1.4 おわりに
2. 熱硬化型PPE樹脂(片寄照雄)
2.1 市場動向
2.2 電子材料としての高分子
2.2.1 高分子の誘電特性
2.2.2 銅張積層板の誘電特性
2.2.3 高周波領域の誘電特性の評価方法
2.3 熱硬化型PPE樹脂
2.3.1 熱可塑性PPE樹脂
2.3.2 熱硬化性PPE樹脂
2.4 熱硬化型PPE樹脂銅張積層板
2.4.1 プリプレグ
2.4.2 銅張積層板
2.5 ビルドアップ用熱硬化型PPE樹脂
2.5.1 ビルドアップ法とは
2.5.2 APPE樹脂付き銅箔の特徴
2.5.3 絶縁材料としての特性‐電気特性/耐熱性/吸水率‐
2.5.4 加工特性
2.5.5 ビルドアップ多層配線板の信頼性
2.6 今後の展望
3. 高周波用の材料(藤原弘明)
3.1 はじめに
3.2 高周波対応基板の開発コンセプトと材料選定
3.3 高周波対応基板の特性とその評価技術
3.3.1 低誘電率多層板材料(MEGTRON5(R-5755))
3.3.2 低熱膨張タイプ低誘電率多層板材料
3.4 おわりに
第6章 低熱膨張性材料-基板材料としてのLCPフィルム(吉川淳夫)
1. はじめに
2. ベクスターの製品ラインナップ
3. ベクスターの特長
3.1 高寸法安定性(低熱膨張係数,熱膨張係数の整合性)
3.2 高耐熱性
3.3 力学特性
3.4 高周波電気特性
3.5 低吸湿性・低吸水性・低吸湿寸法変化率
3.6 耐薬品性
3.7 環境適合性(ノンハロゲン,リサイクル性)
3.8 高ガスバリア性
3.9 耐放射線性
3.10 低アウトガス
3.11 穴あけ加工性とメッキ性
3.12 耐折性
4. ベクスターの具体的用途と性能
4.1 銅張積層板
4.2 多層フレキシブル配線板
4.3 高速伝送用フレキシブルケーブル
5. おわりに
第7章 高熱伝導性材料(竹澤由高)
1. はじめに
2. 高熱伝導性付与の考え方
3. モノメソゲン(ビフェニル基)型樹脂の諸特性
4. ツインメソゲン型樹脂の諸特性
5. 高熱伝導エポキシ樹脂を用いた積層板の試作検討
6. おわりに
第8章 フレキシブル基板材料「エスパネックス」(平石克文)
1. フレキシブル基板
2. 2層CCL「エスパネックス」
3. ポリイミドCCL
3.1 概要
3.2 エスパネックスSシリーズ
3.3 エスパネックスMシリーズ
4. LCP-CCL エスパネックスLシリーズ
4.1 高周波電気特性
4.2 回路基板一般特性
第9章 ビルドアップ用材料(中道聖)
1. はじめに
2. ビルドアッププロセスの特徴
2.1 めっき法プロセス
2.2 非めっき法プロセスの概要
2.3 一括積層法プロセスの概要
3. ビルドアップ基板の技術動向
3.1 次世代ビルドアップ材料への対応
3.2 環境対応ビルドアップ材料
3.3 低誘電対応ビルドアップ材料
4. おわりに
第3編 受動素子内蔵基板
第10章 受動素子内蔵基板
1. 総論-電子部品内蔵基板-(本多進)
1.1 従来の高密度実装の動き
1.2 電子部品内蔵基板の位置付け
1.3 電子部品内蔵基板の特徴と分類
1.4 セラミック系はモジュール・パッケージで応用拡大が進む
1.5 樹脂系は受動・能動部品内蔵基板による究極の3次元実装構造へ
1.5.1 受動部品内蔵基板
1.5.2 受動・能動部品内蔵基板
1.6 おわりに
2. 受動素子内蔵基板材料‐焼成タイプ-(宝蔵寺智昭)
2.1 はじめに
2.2 受動素子内蔵基板材料
2.3 焼成タイプ厚膜ペースト
2.3.1 焼成タイプ厚膜ペーストによる受動素子内蔵プロセス
2.3.2 焼成タイプ厚膜ペーストを用いた抵抗部品内臓
2.3.3 焼成タイプ厚膜ペーストを用いたキャパシタ部品内臓
2.4 焼成タイプ厚膜ペーストによる受動素子内臓のまとめ
3. 受動素子内蔵基板材料-ポリマコンポジットタイプ-(山本和徳,島田靖,島山裕一,平田善毅,神代恭)
3.1 はじめに
3.2 受動素子内蔵基板のコンセプト
3.3 ポリマコンポジットタイプキャパシタ材料
3.3.1 キャパシタ材料の例
3.3.2 キャパシタ材料の設計
3.4 キャパシタ内蔵基板の適用例
3.4.1 携帯電話用パワーアンプ(PA)モジュール基板
3.4.2 フィルタ機能ブロック内蔵基板
3.5 おわりに
内容説明
本書は、プリント配線板の基本に立ち返ると共に、その急激な変革を支えている材料の最新技術をまとめたものである。
目次
序論 総論(プリント配線板および技術動向)
第1編 素材(プリント配線基板の構成材料)
第2編 基材(エポキシ樹脂銅張積層板;耐熱性材料;高周波用材料 ほか)
第3編 受動素子内蔵基板