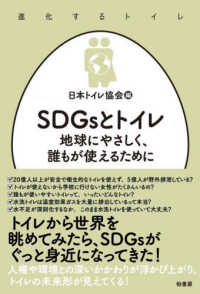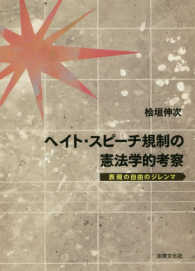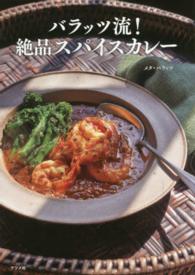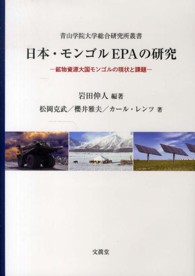- ホーム
- > 和書
- > 理学
- > 環境
- > 資源・エネルギー問題
出版社内容情報
★持続的工業原料としての森林資源にアプローチ!複合体,機能性分子としての利用技術を集約した一冊。
★成分分離技術,リグニン・糖質・抽出成分の応用,そして持続的工業システムの展開と最新技術を網羅。
刊行にあたって
--------------------------------------------------------------------------------
『人間活動と環境の調和』,『持続的発展』………21世紀に生きる私たちが早期に達成しなければならない重要なキーワードである。これを受け,環境負荷の小さい製品開発,製品のリサイクル活用等に関する活発な論議が連日展開されている。中でも,地下隔離炭素資源(化石資源)から生態系循環資源(バイオマス)への社会基盤の転換は,石油が枯渇する前に確立しなければならない最優先課題であり,糖質のアルコール発酵によるエネルギー変換,乳酸発酵による生分解性プラスチックの創製,木質バイオマス発電などは,日本のみならず欧米諸国においても大規模なプロジェクトが組織されている。
しかし,環境共生型の持続的社会が生態系を攪乱しない社会であることを考えるとき,20世紀に引き起こした生態系と人間活動の不協和音を繰り返さないために,バイオマスを原料とする大規模な活動を開始する前に,我々はまず生態系の基本システムについて深い認識を持つ必要がある。
生態系の基本………それは『多機能性』と『流れ』の認識である。『多機能性』とは,生態系に孤立せず構造を転換しながら持続的に機能を発現する生物素材の基本特性であり,それを動きとして捉えると炭酸ガスを起点と終点とする一方向の炭素の『流れ』となる。炭酸ガスが太陽をエネルギー源とする光合成システムにより集合化し(分子集合系),精密な分子複合系へと組み上げられた一形態,それが樹木であり,これはその後壮大な年月をかけ再び解体され,最終的に炭酸ガスへと転換される(分子拡散系)。一方,同じ植物であっても草の流れは非常に速く,通常一年で完結する。すなわち,生物素材は個々に固有の流れを持っており,それによって生態系におけるマテリアルネットワークと炭素の絶妙の気―固バランスが形成されている。しかし,我々はこの流れの『時間』の違いを認識し,素材個々に使い分けているであろうか。樹木を木材,紙として利用後,廃棄するという行為は,樹木系炭素の流れをそのポテンシャルが最大に達したステップから一気に終端分子(炭酸ガス)へと短絡させているということを認識しているであろうか。
本書では,地球生態系の基盤をなす森林資源を分子の流れとして捉え,複合体としての利用から,さらに機能性分子へと材料として持続的かつなめらかに流すために必要な最新の技術について整理,解説した。特に,リグノセルロース資源の循環速度を高度に制御する長期循環資源であり,石油に替わる次世代の芳香族系分子素材としてのポテンシャルを有しながら,構造の多様性・複雑性からそのほとんどが廃棄されている『リグニン』について,『循環』というキーワードのもとに最新の精密分子構造制御とその持続的活用技術を集約した。
全く新しい切り口から木質資源にアプローチする本書が,21世紀における石油に替わる持続的工業原料としての森林資源に対する認識を高め,化石資源に依存しない新しい持続的工業システムの確立に寄与することを願っている。
2005年1月 舩岡正光
--------------------------------------------------------------------------------
舩岡正光 三重大学 生物資源学部 教授
永松ゆきこ 三重大学 生物資源学部 ;科学技術振興機構 研究員
坂 志朗 京都大学 大学院エネルギー科学研究科 教授
青柳 充 舩岡研究グループ(CRESTJST)JSTCREST研究員
浦木康光 北海道大学 大学院農学研究科 応用生命科学専攻 助教授
渡辺隆司 京都大学 生存圏研究所 教授
三亀啓吾 住友林業(株) 筑波研究所 研究員
関 範雄 岐阜県生活技術研究所 試験研究部 主任研究員
伊藤国億 岐阜県生活技術研究所 研究員(現在 岐阜県庁農林商工部商工業室 技師)
吉田 孝 北見工業大学 工学部 化学システム工学科 教授
大前江利子 三重大学 生物資源学部 木質分子素材制御学研究室 技術員
井上勝利 佐賀大学 理工学部 機能物質化学科 教授
Durga Parajuli 佐賀大学 大学院博士後期課程
牧野賢次郎 (有)山曹ミクロン
藤田修三 青森県立保健大学 健康科学部 教授
門多丈治 大阪市立工業研究所 加工技術課 研究員
長谷川喜一 大阪市立工業研究所 加工技術課 研究副主幹
原 敏夫 九州大学大学院 農学研究院 助教授
寺田正幸 新神戸電機(株) 技術開発本部 電池技術開発所 主任研究員
喜多英敏 山口大学 工学部 教授
鈴木 勉 北見工業大学 工学部 化学システム工学科 教授
矢野浩之 京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野 教授
Antonio Norio Nakagaito 京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野
岩本伸一朗 京都大学 生存圏研究所 生物機能材料分野
能木雅也 京都大学 国際融合創造センター 研究員
志水一允 日本大学 生物資源科学部 森林資源科学科 バイオマス科学研究室 教授
安戸 饒 協和発酵工業(株) 東京研究所 林野庁国家プロジェクト 技術担当
谷田貝光克 東京大学 大学院農学生命科学研究科 農学国際専攻 教授
大原誠資 独立行政法人 森林総合研究所 樹木化学研究領域 領域長
松村幸彦 広島大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 助教授 ;同 バイオマスプロジェクト研究センター 幹事
近藤和博 (株)荏原製作所 環境エンジニアリング事業本部 水環境・開発センター 新規事業開発室 室長
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 木質系有機資源の潜在量と循環資源としての新しい視点(舩岡正光)
1. はじめに
2. 森林資源の蓄積量とそのポテンシャル
3. 生態系における物質の流れ
4. 森林資源の材料としてのなめらかな流れをつくる―そのBreakthrough pointとkey material―
5. 持続的工業ネットワーク
6. おわりに
第2章 細胞壁分子複合系の新展開
1. 循環型ウッドプラスチックの設計と誘導(永松ゆきこ,舩岡正光)
1.1 はじめに
1.2 加水分解制御型相分離系変換システムによるLC複合体の誘導
1.2.1 循環型ウッドプラスチックとしてのLC複合体の特性
1.2.2 LC複合体の逐次機能コントロール
1.3 おわりに
2. 無機質複合化による機能開発(坂 志朗)
2.1 はじめに
2.2 ゾル-ゲル法
2.3 諸機能発現のトポ化学
2.3.1 無機物の細胞内分布
2.3.2 吸水防止性(撥水性)
2.3.3 防菌・防かび性
2.3.4 耐蟻性
2.3.5 光劣化抵抗性
2.4 おわりに
3. 機能性塗料の新展開(青柳 充, 舩岡正光)
3.1 はじめに
3.2 リグノフェノール表面コーティング剤(三重県科学技術振興センター工業研究部)
3.3 リグノフェノール機能性塗料((株)ウッドワン,林野庁機能性木質新素材技術研究組合)
3.4 リサイクル性について
第3章 植物細胞壁の精密リファイニング
1. 界面制御反応による精密リファイニング(舩岡正光)
1.1 天然リグニンの基本構造と循環型リグニン系素材の設計
1.2 植物系分子素材の選択的変換・分離系の開発(相分離系変換システム)
1.3 リグノセルロース系素材の変換・分離特性
1.3.1 リグニンの変換特性
1.3.2 炭水化物の変換特性
1.3.3 素材変換・分離系の効率化
1.4 変換システムプラントの構築
2. 成分分離技術としてのパルピング手法の新展開(浦木康光)
2.1 はじめに
2.2 工業的化学パルプ化による成分分離と分離成分の利用
2.2.1 サルファイトパルプ(SP)化
2.2.2 クラフトパルプ(KP)化
2.3 オルガノソルブパルプ化
2.3.1 オルガノソルブパルプ化の動向
2.3.2 オルガノソルブパルプ化による成分分離と木材成分の総合利用
3. 超臨界流体による細胞壁成分の分離技術(坂 志朗)
3.1 はじめに
3.2 超臨界流体とは
3.3.1 超臨界水処理
3.3.2 セルロースおよびヘミセルロース
3.3.3 リグニン
3.4 超臨界メタノールによる木質細胞壁成分の分離および総体利用
3.4.1 木質バイオマスの超臨界メタノール分解
(1) セルロースの分解挙動
(2) リグニンの分解挙動
3.4.2 メタノール可溶部の液体燃料としての可能性
3.5 おわりに
4. 生体触媒による分子変換制御技術(渡辺隆司)
4.1 はじめに
4.2 白色腐朽菌によるリグニン分解
4.3 白色腐朽菌によるバイオパルピングプロセス
4.4 セルラーゼおよびその他の植物細胞壁多糖加水分解酵素
4.5 白色腐朽菌前処理を組み込んだ木材の糖化発酵プロセス
第4章 リグニン応用技術の新展開
1. 天然リグニンの精密機能制御システム(舩岡正光)
2. 機能性バイオポリマーとしての新展開
2.1 酵素複合系の機能変換(三亀啓吾,舩岡正光)
2.1.1 はじめに
2.1.2 リグノフェノールとタンパク質のアフィニティー
2.1.3 リグノフェノールの固定化酵素担体への応用
2.2 HIVプロテアーゼ活性阻害剤としての機能(関 範雄,伊藤国億,舩岡正光)
2.2.1 はじめに
2.2.2 リグノポリフェノールのHIVプロテアーゼ活性阻害機能
2.2.3 カルボキシメチル化リグノフェノールのHIVプロテアーゼ活性阻害機能
2.2.4 リグノフェノールの特異的HIV-1プロテアーゼ活性阻害
2.2.5 リグノフェノールの抗HIV活性
2.3 酵素による重合制御(吉田 孝,舩岡正光)
2.3.1 はじめに
2.3.2 リグノフェノールの酵素重合
(1) リグノフェノールのペルオキシダーゼ酵素重合性の検討
(2) IRスペクトルによる重合機構の推定
(3) 熱分解GC-MSスペクトルによる重合機構の推定
(4) ポリリグノクレゾールの熱的性質
2.3.3 おわりに
2.4 バイオポリエステル可塑剤への応用(大前江利子,舩岡正光)
2.4.1 はじめに
2.4.2 リグノフェノール複合フィルムの機械的特性
2.4.3 複合フィルムの熱的特性
2.4.4 複合フィルムの生分解性
2.4.5 おわりに
2.5 金属元素吸着固定化体としての機能(井上勝利,Durga Parajuli,牧野賢次郎,舩岡正光)
2.5.1 はじめに
2.5.2 各種のリグノフェノール誘導体によるアンチモン(III)の吸着
2.5.3 リグノカテコールによる各種の重金属イオンの吸着特性
2.5.4 リグノカテコールを充填したカラムによる鉛と亜鉛の分離
2.6 持続的抗酸化剤としての機能(藤田修三,舩岡正光)
2.6.1 要約
2.6.2 はじめに
2.6.3 試料と実験方法
2.6.4 結果および考察
(1) POVおよびTBA法による抗酸化効果評価
(2) 抗酸化効果の長期的観察
3. 樹脂への応用
3.1 リグノセルロース系循環材料への展開(永松ゆきこ,舩岡正光)
3.1.1 はじめに
3.1.2 リグノフェノール-古紙ファイバー複合材料の創製とその機能制御
3.1.3 おわりに
3.2 有機・無機質集合化材への展開(永松ゆきこ,舩岡正光)
3.2.1 はじめに
3.2.2 リグノフェノールをマトリクスとする複合材料の特性と機能
(1) リグノフェノール-セルロース複合系
(2) リグノフェノール-無機複合系
3.2.3 おわりに
3.3 機能性接着剤への展開(門多丈治,長谷川喜一,舩岡正光)
3.3.1 リグノフェノールを機能性接着剤へ
3.3.2 木材用接着剤
3.3.3 ネットワークポリマー型接着剤
3.4 感光性材料への展開(門多丈治,長谷川喜一,舩岡正光)
3.4.1 リグノフェノールをフォトレジストへ
3.4.2 印刷用フォトレジスト
3.4.3 プリント配線用フォトレジスト
3.5 高吸水性樹脂の設計と機能(関 範雄,伊藤国億,原 敏夫,舩岡正光)
3.5.1 はじめに
3.5.2 リグノフェノール系高吸水性樹脂の設計
3.5.3 リグノフェノール系高吸水樹脂の機能
4. 電子伝達系への応用
4.1 光電変換デバイスの設計と構築(青柳 充, 舩岡正光)
4.1.1 はじめに
4.1.2 リグノフェノールの基礎物性
4.1.3 ナノ粒子酸化チタンとの錯体形成
4.1.4 リグノフェノール-酸化チタン光電変換デバイスの光電変換特性
4.1.5 光電変換能力に対するLPの構造の影響
(1) 樹種特性
(2) フェノール種の影響
(3) 水酸基の影響
(4) リサイクル型リグノフェノール
4.1.6 推定メカニズム
4.1.7 まとめ
4.2 鉛蓄電池負極素材への応用(寺田正幸,舩岡正光)
5. 高密度炭素骨格の応用
5.1 機能性分離膜の創製(喜多英敏,舩岡正光)
5.1.1 はじめに
5.1.2 膜分離技術
5.1.3 リグニン系分子ふるい炭素膜
5.1.4 おわりに
5.2 電磁波シールド材料の開発(鈴木 勉)
5.2.1 はじめに
5.2.2 電磁シールドと結晶炭素
(1) 電磁シールド材
(2) 電磁波シールド性能
(3) 結晶炭素
5.2.3 リグニンのNi触媒炭化によるT成分の製造と炭化物のEMS性能
(1) 実験方法
(2) LCのT成分原料としての適性
(3) カルシウムの助触媒効果
(4) カルシウムの作用機構(I)
(5) カルシウムの助触媒効果(II)
(6) カルシウムの助触媒効果(III)
5.2.4 おわりに
第5章 糖質の新しい応用技術
1. バイオナノファイバー:セルロースミクロフィブリルの可能性
(矢野浩之,アントニオ・ノリオ・ナカガイト,岩本伸一朗,能木雅也)
1.1 未来型資源:木質
1.2 木質の本質 -高強度,低熱膨張,環境調和性-
1.3 高強度木材
1.3.1 樹脂含浸・圧密木材
1.3.2 音速による原材料の選別
1.3.3 脱成分処理
1.4 ミクロフィブリル化植物繊維成型材料
1.4.1 ミクロフィブリル化植物繊維
1.4.2 MFC・フェノール樹脂複合成型物
1.4.3 MFCのみでの成型物製造
1.4.4 MFC・酸化デンプン,MFC・ポリ乳酸樹脂複合成型物
1.4.5 バクテリアセルロース・フェノール樹脂複合成型物
1.4.6 他材料との比較
1.5 ナノファイバー繊維強化透明材料
1.6 おわりに
2. 糖質の機能開発(志水一允)
2.1 はじめに
2.2 木材ヘミセルロースの化学構造
2.2.1 キシラン
2.2.2 グルコマンナン
2.2.3 ガラクタン
2.2.4 アラビノガラクタン
2.2.5 リグニン・炭水化物複合体(lignin-carbohydrate complex)
2.3 木材ヘミセルロースの抽出方法
2.4 木材ヘミセルロースからのオリゴ糖の製造方法
2.4.1 広葉樹キシランからのオリゴ糖
(1) 広葉樹キシランから酸加水分解によって得られるオリゴ糖
(2) 広葉樹キシランから酵素加水分解によって得られるオリゴ糖
(3) 蒸煮によるオリゴ糖の製造
2.4.2 針葉樹からのオリゴ糖
(1) 針葉樹キシランからのオリゴ糖
(2) 針葉樹グルコマンナンからのオリゴ糖
2.5 木材ヘミセルロースの機能開発
2.5.1 広葉樹キシランのキシロース,フルフラールとしての利用
2.5.2 ヘミセルロースのヒドロゲル,フィルム,プラスチックとしての利用
2.5.3 ヘミセルロースの生理活性物質としての利用の可能性
(1) ヘミセルロースの抗腫瘍活性
(2) ヘミセルロースの食物繊維(DF)としての生物活性
(3) ヘミセルロース由来のオリゴ糖の食品としての機能
(4) ヘミセルロース由来のオリゴ糖の植物生理への作用
2.6 おわりに
3. 工業原料への転換利用
3.1 糖質の精密制御(三亀啓吾,舩岡正光)
3.1.1 はじめに
3.1.2 従来のリグノセルロース分離法
3.1.3 リグノセルロース分離の新しい試み
3.1.4 相分離変換システムにおける炭水化物の分離挙動
3.2 糖質の転換利用(安戸 饒)
3.2.1 バイオマス糖化液からの有用物質の生産
3.2.2 バイオマスの糖化方法について
3.2.3 バイオマスの構成成分について
3.2.4 具体例
(1) アルコール(エチルアルコール,エタノール)発酵
(2) 乳酸発酵
(3) アセトン・ブタノール発酵
3.2.5 おわりに
第6章 抽出成分の新展開
1. 生理機能性物質としての新展開(谷田貝光克)
1.1 はじめに
1.2 生理機能性物質に関する最近の研究の動向
1.3 実用化に向けての技術開発
1.3.1 抽出成分関連技術研究組合による研究成果
1.3.2 樹木抽出成分に関連する最近の公開特許
1.4 おわりに
2. 工業原料としての新展開(大原誠資)
2.1 はじめに
2.2 テルペン
2.2.1 モノテルペン
2.2.2 トリテルペン
2.3 フラボノイド
2.4 フェノール酸
2.5 タンニン
2.5.1 抗酸化性食品
2.5.2 VOC吸着材
2.5.3 抗菌・消臭繊維
2.5.4 ポリウレタンフォーム(PUF)
2.5.5 住環境向上資材
2.5.6 重金属吸着材
第7章 炭素骨格の新しい利用技術(鈴木 勉)
1. はじめに
2. 高ガス化反応性木炭の製造
3. 気相水素化触媒の調製
4. 電磁波遮蔽材の製造
5. おわりに
第8章 新しいエネルギー変換技術(松村幸彦)
1. はじめに
2. 木質ペレット
3. 混焼
4. 木炭
5. ガス化
6. エタノール生産
7. 超臨界メタノール処理
8. 直接油化
9. 急速熱分解
10. スラリー燃料化
11. おわりに
第9章 持続的工業システムの展開(近藤和博,舩岡正光)
1. 持続的社会、物質循環型社会への期待の背景
2. 持続的工業システムの要件
3. 相分離システムを主体とするバイオマス循環利用システム
4. バイオマス循環利用システムの実証プラント
5. 持続的工業システム展開への課題
--------------------------------------------------------------------------------
目次
第1章 木質系有機資源の潜在量と循環資源としての新しい視点
第2章 細胞壁分子複合系の新展開
第3章 植物細胞壁の精密リファイニング
第4章 リグニン応用技術の新展開
第5章 糖質の新しい応用技術
第6章 抽出成分の新展開
第7章 炭素骨格の新しい利用技術
第8章 新しいエネルギー変換技術
第9章 持続的工業システムの展開
著者等紹介
舩岡正光[フナオカマサミツ]
三重大学生物資源学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。