出版社内容情報
構成および内容
第1章 総論―水性コーティングの新しい技術と開発 桐生春雄
1 はじめに
2 新しい機能性塗料の開発
3 複合化による性能と機能
4 塗料系ポリマーの設計とその手法
5 機能化のための物性の基礎と展開
5.1 粘弾性
5.2 付着性
6 最近の機能性塗料について
6.1 シリコーン系マクロモノマーの機能化
6.2 水系ポリマーエマルジョン
6.2.1 中空ポリマー粒子
6.2.2 フッ素/アクリル複合粒子
6.2.3 アクリル/シリコーン複合粒子
6.2.4 超微粒子
6.3 複層粉体塗料
6.4 光触媒による大気浄化塗料
6.5 抗菌・防カビ塗料
6.6 ミクロ構造をもつ粒子分散系塗料
6.7 ハーコート塗料
6.8 セラミック複合建築用塗料
7 おわりに
〈第1編 塗料用樹脂〉
第2章 アクリル系樹脂 池林信彦
1 はじめに
2 アクリル樹脂とは
3 アクリル樹脂の水系化
4 アクリル系合成樹脂エマルジョン
4.1 ソープフリー系アクリルエマルジョン
4.2 架橋系の導入された水系アクリル樹脂
4.2.1 一液常温架橋システム
4.2.2 アクリルシリコーン
4.3 アクリルエマルジョンの粒子径制御
4.4 アクリルエマルジョンの異相構造化
5 おわりに
第3章 アルキド・ポリエステル系樹脂 シーエムシー編集部
1 はじめに
2 アルキド樹脂の各種成分と水性化
3 ミクロゲル粒子形成アルキド樹脂と水性化
第4章 ポリウレタン樹脂 桐原 修
1 水性ポリウレタン樹脂とは
2 水性ポリウレタン系塗料原料
2.1 PUD
2.2 架橋剤
2.2.1 水性ブロックイソシアネート
2.3 水性2液型ポリウレタン塗料原料
2.3.1 ポリオール
2.3.2 ポリイソシアネート
第5章 フッ素系樹脂 高柳敬志
1 はじめに
2 環境対応の今日的な意味
2.1 地球を取り巻く環境
3 塗料塗膜での対応
4 人間環境保全の実現
5 塗料用フッ素樹脂の特性
6 環境への因子を弱くする水系以外の塗料用形態
6.1 弱溶剤品種
6.2 粉体、水溶性、電着品種
7 水性塗料用フッ素樹脂
7.1 フルオロオレフィンビニルエーテルエマルジョン品種
第6章 水系UV/EB硬化樹脂 鈴木直文、菅原輝明
1 水系UV/EB硬化樹脂が必要とされる背景
2 水系UV/EB硬化樹脂の種類と特徴
2.1 水溶性UV/EB硬化樹脂
2.2 強制乳化型UV/EB硬化樹脂
2.3 自己乳化型UV/EB硬化樹脂
3 水系UV/EB硬化樹脂の構成成分
4 特許にみられる水系UV/EB硬化樹脂の種類
4.1 水溶性UV/EB硬化樹脂
4.2 強制乳化型UV/EB硬化樹脂
4.3 自己乳化型UV/EB硬化樹脂
5 水系UV硬化樹脂に使用されている光重合開始剤の種類
6 水系UV/EB硬化樹脂の応用例
6.1 水系UV/EB硬化樹脂の性状
6.2 水系UV硬化樹脂に使用される重合開始剤
6.3 紙の表面加工用途への応用例
7 おわりに
〈第2編 塗料の処方化〉
第7章 アクリル系塗料 谷口 仁
1 はじめに
2 水系塗料の特徴
3 水系アクリル樹脂塗料について
3.1 水系塗料用アクリル樹脂の特徴
3.2 硬化形式
3.2.1 常温乾燥・硬化型
3.2.2 焼付型
3.3 共溶剤と中和剤
3.4 レオロジーコントロール剤
3.5 その他
4 水系アクリル樹脂系塗料の用途
5 今後の展開
第8章 アルキド系塗料 桐生春雄
1 はじめに
2 水性化されたポリマーと塗料化
2.1 アルキド樹脂の水性化と粒子分散型アルキド樹脂塗料
2.2 自己乳化型水性アルキド樹脂塗料
2.3 ミクロゲルを含有した脂肪酸変性水性アルキド樹脂塗料
2.4 ミクロゲル含有水性アルキド樹脂塗料の物性
3 水性化アルキド樹脂塗料の種類と位置
4 おわりに
第9章 ポリウレタン系塗料 桐原 修、片村広一
1 はじめに
2 タイプ別処方
2.1 水性1液型ポリウレタン塗料処方
2.2 水性2液型ポリウレタン塗料処方
3 自動車塗料用処方
3.1 水性1液型塗料
3.2 水性2液型塗料
4 建築用塗料処方
5 その他の用途
6 今後の課題
第10章 エポキシ系塗料 石毛和夫
1 はじめに
2 水性エポキシ樹脂の種類と用途
3 カチオン電着塗料
3.1 カチオン電着塗料樹脂
3.2 カチオン電着塗料の性能
3.3 カチオン電着塗料の動向
4.金属缶用塗料
4.1 缶用水性エポキシ樹脂
4.2 缶用水性塗料の性能
5 その他の水性エポキシ樹脂塗料
第11章 フッ素系塗料 川上昌一
1 はじめに
2 水性フッ素樹脂塗料の特性
2.1 基本的性能
2.2 塗料組成と塗装システム
3 水性フッ素樹脂塗料の応用例
3.1 一般的用法
3.2 改装用途
3.3 クリア一工法
3.4 高意匠性塗料
3.5 工場塗装用塗料
4 今後の展開
第12章 水性塗料の流動特性とコントロール 高橋誠一
1 自然との共生をはかる塗液のレオロジーコントロール技術
2 疎水性会合型シックナーの種類
3 水中における疎水性物質の挙動
3.1 疎水性水和と疎水性相互作用
3.2 疎水性相互作用に関するBen-Naimのモデル
3.3 疎水性相互作用による水和圏の重なり
4 HEURの疎水性会合状態の蛍光分析による確認
4.1 ピレンモデル化合物と会合量(エキシマー、Eximer)の定量
4.2 PAT/HEUR-1混合物中におけるエキシマーの生成と凝集数
4.3 PAT/アクリルラテックス系における会合
4.4 PAT/ラテックス系のLangmuirパラメーターの決定
4.5 せん断流動下におけるシックナーの相互作用
5 疎水結合と水素イオン濃度
6 会合性シックナーによるレオロジーコントロール
6.1 疎水基のレオロジー効果
6.2 会合性シックナーのアクリルラテックスへの吸着
6.3 会合性シックナーと界面活性剤のアクリルエマルジョンへの競合吸着
6.4 会合性シックナー分散体に及ぼす融着助剤の影響
6.5 顔料分散と疎水結合
6.6 シックナーのレオロジー特性3態
7 HEURと水性ポリウレタンディスパージョンの相互作用
7.1 PURADSとアクリルラテックスの類似性
7.2 PURADSとアクリルラテックスの相違点
7.3 PURADS/モデルHEUR系の粘性
7.4 PURADS/モデルHEUR系の動的粘弾性
8 高分子分散系の構造形成3様式
9 まとめ
〈第3編 応用〉
第13章 自動車用塗料 佐田利彦、山中雅彦
1 はじめに
2 水系塗料の特徴
3 水系塗料の分類
4 自動車塗装
4.1 化成処理
4.2 バンパー用脱脂剤
4.3 バンパー用水系プライマー
4.4 電着塗装
4.5 中塗り塗装
4.6 上塗り塗装
5 おわりに
第14章 建築用塗料 高橋 保
1 建築用塗料とは
2 建築塗装の材料と工法
2.1 JASS18塗装工事による
2.2 塗料メーカーのマニュアルによる
3 部位別塗装工法
4 建築用塗料の変遷と状況
4.1 金属系素地面用
4.2 セメント系素地面用
4.3 木質系素地面用
5 塗り替え用塗料の現況
6 環境対応と現場塗装
7 施工現場より
第15章 缶用コーティング 小島瞬治
1 金属缶の種類と塗装方法
1.1 金属缶の種類と使用形態
1.2 3ピース缶胴の塗装
1.3 DWI缶胴の塗装
1.4 缶蓋の塗装
2 缶用塗料の種類と要求性能
2.1 内面ベース塗料
2.2 内面トップ塗料
2.3 ホワイトコーティング
2.4 仕上げワニス
2.5 その他の塗料
3 缶用水性塗料開発の経緯
3.1 水溶性樹脂塗料
3.2 疎水性樹脂の水性化
3.3 疎水性樹脂粉末の水分散
3.4 アクリル樹脂による変性
3.5 相転換乳化法
4 実際の缶用水性塗料とその製法
4.1 仕上げワニス
4.2 内面塗料
4.2.1 相転換乳化型水性塗料
4.2.2 アクリルグラフトエポキシ樹脂型水性塗料
4.2.3 アクリルエステル付加エポキシ樹脂型水性塗料
4.2.4 エポキシ・アクリル・ブロック共重合体型水性塗料
5 水性塗料使用上の問題点と今後の課題
5.1 塗装作業性、塗装適性
5.2 塗膜の加工性、耐食性
5.3 焼付オーブンの排気処理
第16章 重防食用塗料 山田邦男
1 はじめに
2 アクリルエマルジョン樹脂系塗料
2.1 乳化重合の機構
2.2 乳化重合型エマルジョンポリマー
2.3 ソープフリーアクリルエマルジョン
2.4 架橋性エマルジョン
3 水溶性アルキッド樹脂塗料
3.1 水溶性アルキッド樹脂
3.2 加水分解しにくい水溶性アルキッド樹脂
3.3 水溶性アルキッド樹脂の硬化反応
4 水溶性ポリウレタン樹脂塗料
4.1 ポリウレタン樹脂
4.2 自己乳化型ポリウレタン樹脂
5 水溶性エポキシ樹脂塗料
5.1 カチオン型エポキシ樹脂
6 実施例
6.1 水系ジンクリッチペイント
6.2 タールエポキシエマルジョン塗料
6.3 架橋型ソープフリーアクリルエマルジョン塗料
6.4 塩化ビニリデン樹脂塗料
6.5 水溶性アルキッド樹脂塗料
〈第4編 廃水処理〉
第17章 廃水処理に係わる法規制等 石井 徹
1 はじめに
2 関係法規
3 環境基本法
4 水質汚濁防止法
4.1 濃度規制
4.2 総量規制
4.3 管理体制(廃水処理に限定)
5 地方公共団体条例
6 事業場における当該地域での法規制(地方公共団体条例を含む)の把握
第18章 廃水処理対策の基本 石井 徹
1 はじめに
2 排水処理体系
3 事業場(工場)での廃水処理方法の選定手順
3.1 選定手順の基本
3.2 生産工程の合理化等
3.3 汚濁水排出パターンの水質の精査
3.4 自社の処理目標水質の検討
3.5 具体的な処理方法の検討
3.5.1 有機性廃水
3.5.2 無機性廃水
3.5.3 処理施設の選定
4 廃水処理施設の設計基礎条件の把握
4.1 設計基礎条件
4.2 水質および排水量の測定
第19章 水質管理 石井 徹
1 はじめに
2 水質管理への組織
2.1 公害防止管理組織
2.2 水質管理の意義
3 日常管理
3.1 汚濁状況の把握
3.2 排出水量の把握
3.3 処理効果の確認
4 異常時の処理
4.1 電源の故障
4.2 装置の故障
4.3 水量の変動
4.4 災害発生時の対応
第20章 単位工程 石井 徹
1 はじめに
2 物理学的処理方法
2.1 事前処理
2.2 沈殿分離法
2.3 油水分離法
2.4 濾過法
2.5 浮上分離法
2.5.1 重力方式
2.5.2 加圧浮上方式
2.6 遠心分離法
2.7 イオン交換樹脂法
2.8 限外濾過法(UF)
2.9 逆浸透法(RO)
2.10 電気透析法
3 化学的処理方法
3.1 中和法(pH調整)
3.2 酸化法
3.3 塩素酸化法
3.4 凝集沈殿法
3.5 オゾン処理法
4 生物学的処理方法
4.1 好気性処理法
4.1.1 散水濾床法
4.1.2 活性スラッジ法(活性汚泥法)
4.1.3 接触曝気法
4.1.4 酸化池法(安定化池法)
4.2 嫌気性処理法(メタン発酵法)
4.3 酵母培養法
5 その他の高度処理
5.1 電解法
5.1.1 電解法の特徴
5.1.2 電解反応の機構
5.1.3 電解反応の処理例
5.2 薬品沈殿法
5.3 活性炭吸着法
5.4 泡沫分離法
5.5 超音波処理法
6 関連周辺技術
6.1 水力学
6.2 構造材料
6.3 構造設計
6.4 機械設備
6.5 装置の運転制御
6.6 装置の信頼性
6.7 装置の安全性
7 おわりに
〈第5編 市場編〉
第21章 水性塗料の市場動向 シーエムシー編集部
1 はじめに
2 塗料の種類
3 水性塗料およびエマルジョンペイント
3.1 水性塗料
3.2 エマルジョンペイント
4 水性塗料の市場動向
4.1 塗料全体の生産、出荷動向
4.2 水性塗料の市場規模
4.2.1 エマルジョンペイント
4.2.2 水性樹脂系塗料
5 塗料の輸出入動向
6 塗料メーカーの動向
7 おわりに
内容説明
コーティングの分野は、有機溶剤の削減の目的から水性コーティング材料の開発が盛んである。たとえば、水溶性塗料、エマルジョン塗料およびディスパージョン塗料などにおける高度なレベルアップが企図されている。そこで前書で好評をいただいた“水性コーティング技術”のその後の発展、最新技術と国際的な市場の開発を視野において、本書の発刊を企画したものである。
目次
第1編 塗料用樹脂編
第2編 塗料の処方化編
第3編 応用編
第4編 廃水処理編
第5編 市場編
-
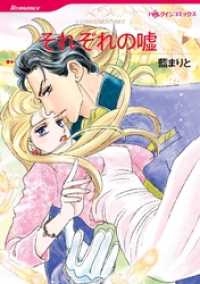
- 電子書籍
- それぞれの嘘【分冊】 11巻 ハーレク…
-

- 電子書籍
- ひみつ堂のヒミツ 1000円のかき氷を…
-
![図解入門よくわかる 最新金型の基本と仕組み[第2版]](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0582821.jpg)
- 電子書籍
- 図解入門よくわかる 最新金型の基本と仕…
-
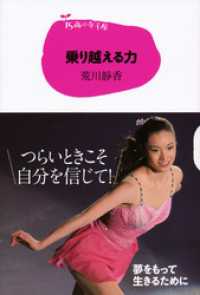
- 電子書籍
- 15歳の寺子屋 乗り越える力
-
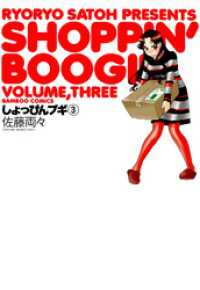
- 電子書籍
- しょっぴんブギ (3) バンブーコミッ…



