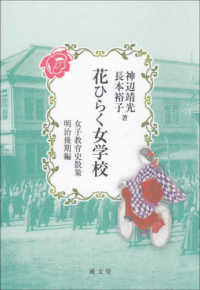- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
掘り起こすのは、遺骨と、記憶と、敵意と、徒労感と…第二次大戦中にアルバニアで戦死した自国軍兵士の遺骨を回収するために、某国の将軍が現地に派遣される。そこで彼を待ち受けていたものとは…。
著者等紹介
カダレ,イスマイル[カダレ,イスマイル][Kadare,Ismail]
1936‐。アルバニアの作家・詩人。1936年、同国南部のジロカスタルに生まれる。ティラナ大学卒業後、モスクワに留学するが、アルバニアとソ連の関係悪化をうけて帰国した。その後ジャーナリストとして活動しながら、詩や小説を発表。1963年の小説『死者の軍隊の将軍』が国際的に注目され、作家としての地位を確立する。労働党の一党体制下で制限を受けながら執筆を続けていたが、1990年にフランスへ亡命。翌年、複数政党制となった母国に帰国、現在も旺盛な執筆活動を続けている。第1回「国際ブッカー賞」受賞
井浦伊知郎[イウライチロウ]
1968年、福岡生まれ。1998年、広島大学大学院文学研究科博士課程後期単位取得退学。博士(文学)。1998~2001年、日本学術振興会特別研究員。現在、広島文教女子大学非常勤講師(ドイツ語)。専攻はアルバニア語学、バルカン言語学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
miyu
51
とても興味深く面白い作品。何より翻訳が読みやすいのに驚いた。訳者の井浦氏は原文であるアルバニア語から訳したとのこと。私たちにとっては馴染みの薄い国だが、言葉だけでなく文化にも精通した方の翻訳で読めるのはありがたい。この物語を読んでいる間、頭の中ではギリシャのテオ・アンゲロプロスの映像が浮かんでは消えていった。異国の地で散った戦士の遺骨回収という重苦しいシーンが延々と続くが、小ネタ的な話も挟まれていて退屈はしなかった。しかしやはり圧巻は第20章の婚礼のシーンからで、畳み掛けるような展開に身を固くして読んだ。2015/04/15
長谷川透
27
将軍は異国に散った同胞の遺骨を帰す為アルバニアへ赴く。異国はかつて帰属地であり又戦地でもある。終戦と共に生まれた断絶は、国境間だけではなく、同胞であった者たちの間にもある。戦火が途絶えた今日、将軍の行為は戦死者の弔いと国家間の和平をも象徴し、断絶を突き破ろうとする行為に思える。ところがかつての同胞の死霊は将軍の行為を歓迎しない。断絶を突き破ろうとする将軍は、生者と死者の断絶を突き破り死者たちの国、憎悪を呪いが渦巻く異界へと足へ踏み入れてしまったのだろう。寓話でありながら現代的切実な問題を孕んだ傑作である。2013/09/29
三柴ゆよし
20
政府の特命により大戦時にアルバニアで戦死した自国軍兵士の遺骨回収に向かう某国の将軍と司祭。ディスコミュニケーションの有り様はカフカ的だが、思わず噴き出してしまうような会話の応酬によって、単に重苦しいだけではない、「奇妙な翳り」を持った小説に仕上がっている。ついでながら述べると、これは「戦後」を描いた小説ではない。「戦後」とはつまるところ「戦争」の延長でしかないのだということを描いた小説である。そこに死者が在る限り、憎悪と記憶は死なないのだ。「敵は敵のままなんだな、たとえ死んでいても」。2011/05/04
秋良
16
血の復讐の掟に怯えて、学校に行けない子供がいる(見つかると殺されるから)って聞いたことがあるのは、アルバニアだったか…?WW IIから二十年後、たぶんイタリアの将軍が、アルバニアの山ん中で墓穴を掘って掘って掘る。遺骨を祖国へ持ち帰るために。骨を持って帰っても彼らが生き返るわけじゃない虚しさ。過ぎ去ってしまったことに対して今さら足掻く徒労感。戦争が終わったからって消えない恨み。時おり顔を出す差別。全編通して灰色の陰鬱な雰囲気で、墓ばかり探すことに疲れるけど読むのが止まらない。2018/11/05
ふるい
16
戦争好きで、常に血と復讐を求めるアルバニア人、というイメージを登場人物のひとりである異国の司祭に語らせるアルバニア人の著者カダレはどんな気持ちで書いたんだろう…興味深い。最初は名誉ある職務だと張り切っていた将軍が、遺骨回収という作業の徒労感や虚無感に苛まれていき、知らず知らずのうちに死者たちの暗い影に追いかけられているようで、特に婚礼の場面は恐ろしかった。さくさく読み進められますが、読後感は重い作品でした。2018/01/21