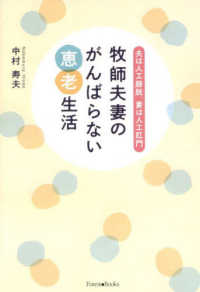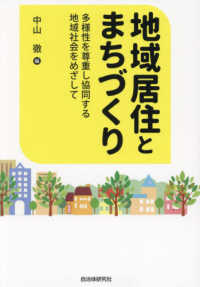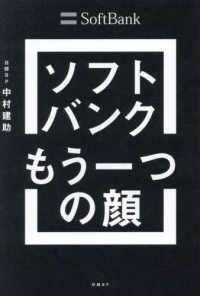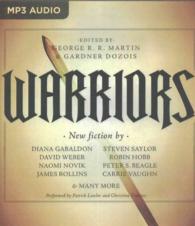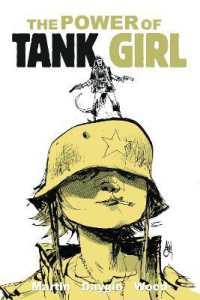内容説明
夏の暑い日、見知らぬ男12人が一室に集まった。彼らには一人の少年の命が委ねられていた。誰もが有罪と信じた評決が、一人の陪審員の粘り強い説得によって徐々にくつがえっていく。息づまる展開、浮きぼりにされていく人間のさまざまな偏見や矛盾…。シドニー・ルメット監督、ヘンリー・フォンダ、リー・J・コッブなどによって映画化された不朽の名作の戯曲版。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
92
被告が有罪であることが合理性に欠ける時は無罪とする推定無罪の原則。「疑わしきは罰せず」だ。裁判において検察が実証し、弁護側もさほど弁護しなかった、父親殺しの疑いのかかった少年。彼は本当に有罪かを狭い部屋で12人の陪審員が話し合うドラマの脚本。名前はなく、数字の1~12で示されるだけの陪審員達のやり取りを、巻頭の写真と人物の紹介を手助けに読んでいくわけだが、その煩わしさが気にならない面白さ。最初はたった一人で無罪を主張した8番が主張し続ける不合理さ。彼は果たして11名を納得させられるのか。面白かった。2015/02/09
市太郎
67
一気読み確実のすこぶる面白い戯曲でした。話は単純で場面も一室しかないのですが、この読ませるドラマ性には驚く。とある少年犯罪の判決を決めるため、12人の陪審員が話し合うわけなんですが、無罪を主張したのは一人だけ。読み終わった後でいかに人が偏見と感情に支配されているかが痛感できました。面白いのは感情と偏見で有罪を求めてた連中が段々と論理的に答えを導こうとし始めるところ。段々と細かく深い話合いになっていくところ。間違っている(と思われる)論理には矛盾が生まれるところ。我々は窓を閉めるかどうかすら決められない。2015/04/16
HANA
47
12人の陪審員。事件は少年による父親殺し。法廷が舞台の戯曲であるが、眼目は陪審員同士の人間関係と事件自体より先入観の恐ろしさ。当初は無罪を主張する8番を論破するつもりだった他の人間が証拠や論理の前に無罪に傾いていくというの流れや、思い込みによる頑迷性が畳み掛けるように展開していて一気に読まされる。日本でも陪審員制度が始まり我々も人を裁くという事に無関係ではいられない昨今、その立場に立てばせめて惑わされることなく中立の立場でいたいと思わされる。ところでラストシーン、やっぱりあの人がアレって事でいいのかなあ。2015/05/02
ゆーかり
20
舞台を観に行くための予習というか復習。父親殺しの罪に問われた少年。誰もが有罪と思っていた中で疑問を投げかけた一人の陪審員。有罪か無罪か。少年の命は彼らの評決にかかっている。法廷ものや陪審員に馴染みが無くても面白くて引き込まれる。映画を思い出しながら読んだけれど、観ていなかったら登場人物名が第何号ばかりなのでイメージしにくいかもしれない。映画(テレビ)シナリオと舞台台本は少し違っていて、この翻訳は舞台用に映画版を取り入れたもの。ラストシーンやいくつかの点で違いがある。映画は名作だった。舞台はどんな風だろう。2018/09/06
fseigojp
19
映画原作 これとアラバマ物語はセットで視聴すべき2015/09/14