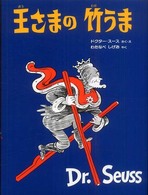出版社内容情報
学校現場での新しい教育について、先生方と共に考えるシリーズの2冊目。海外からの移住者が増え、教室に日本語が話せない児童生徒が編入してくるケースも多い。現場の教師はどう対応し行動したらいいか、Q&A形式でやさしく解説。
Q&Aの例
急に、日本語がわからない子どもを担当することになりました。どんなことに気をつければいいのでしょうか。
外国人のT君と日本人のJ君がけんかしてT君が骨折してしまいました。どのように対応すればよいでしょうか。
小学校の「総合的な学習の時間」に国際理解の授業をしたいと思いますが、どんなことをすればいいのでしょうか。
外国人の児童生徒の成績は、日本人と同じ基準で評価するのは難しいので、何か配慮をすべきでしょうか。
日本の小学校では集団の規則を守ることが要求されますが、理解できない外国人の子どもにはどう説明すべきですか。
外国人生徒の日本語の読み書き能力の進歩が止まってしまったように見えるのですが、それはなぜでしょうか。
外国人の子どもたちに週3~5時間ほど国際教室で指導していますが、これだけで日本語を習得するのに十分ですか。
外国から来た日本語の不得意な子どもたちに対して、先進的に取り組んでいる学校の例を教えて下さい。
【著者からのコメント】
(まえがきより)
現在、日本には200万人をこえる外国人が住んでいます(入国管理局の登録外国人統計によれば、2009年末で219万人、日本の総人口の1・71%にあたります)。これらの外国人たちの中には、子どもたちと一緒に来日した人もいれば、生活がある程度落ち着いてから子どもたちを母国から呼び寄せた人もいます。子どもたちの多くが「日本語が話せない」状態で日本に来ています。子どもたちは6歳を超えているならば、通常は小学校に、12歳を超えているならば中学校に入ります。外国からの子どもたちは新しい居場所となる日本の小学校や中学校でどのような経験をするのでしょうか。日本という社会の中で自分の位置を見つけることができずに戸惑っている子どもも多いだろうと思います。
そうした子どもたちにいかに手をさしのべられるかは、教員がどの程度、予備知識や意欲を持っているかにかかっています。クラスに溶け込めずにいるのを見たとき、母語と日本語の狭間で戸惑っているとき、周囲の子どもたちとけんかしたり、いじめられているのを知ったときなど、さまざまな局面で、読者の皆さんが拠り所にできるように、この本は編まれました。
【編集者からのコメント】
最近、いわゆる外国人学校とかインターナショナルスクールではなくて、ごく普通の町の小学校、中学校などに、外国人の子どもが編入してくる生徒が増えているといいます。学校現場の教師たちは、それまで日本人の児童生徒だけを担当していたのに、急に校長先生から「来週からお願いします」と言われて戸惑うことも多いと思います。多感な子どもの成長を見守るという意味では日本人も外国人も同じですが、言葉がわからない、文化が違う、などのために考慮しなければならないことはたくさんあります。そうした事態が起きたとき、最低限の考え方と対応の仕方を周りの大人達が参考にできる本があれば、と考えました。初めての人にも理解しやすいように、一問一答形式でわかりやすく解説し、用語集もつけましたので、手元に置いて役立てていただければと思います。
内容説明
日本語が話せない子どもを突然、受け持つことになったら…?先進的な取組の事例や行政の最新動向も含めて丁寧に解説。
目次
第1部 クラス運営・生活相談編(急に外国人の子どもの担任をすることになりました。日本語があまりわからないようです。どんな準備が必要ですか。;日本人の子どもたちが、日本語がわからない子どもの存在を認め、受け入れるようにするには、どうしたらいいでしょうか。;最近、クラスに外国人の子どもを迎え入れましたが、クラスの人間関係ではどんな点に気をつけたらいいですか。 ほか)
第2部 日本語指導編(語彙・音声・文法)(日本語教室の担当となりました。子どもたちの言語、フィリピノ語や中国語をある程度は私も勉強すべきでしょうか。;子どもたちに対する日本語の音声教育はどのように行うべきでしょうか。;日本語の理解が難しい子どもたちに、社会、算数、理科などの教科で日本語学習をどのように絡めたらいいでしょうか。 ほか)
第3部 社会・制度編(そもそも日本語の指導が必要な子どもは全国で何人ぐらいいますか。私たちはどんなことを心がけるべきですか。;日本語の学習指導や補助は、制度的にどのようになっていますか。;日本語指導が必要な子どもが散在する地域で行われているという「巡回指導」について、具体的に教えてください ほか)
著者等紹介
河原俊昭[カワハラトシアキ]
京都光華女子大学教授
山本忠行[ヤマモトタダユキ]
創価大学教授
野山広[ノヤマヒロシ]
国立国語研究所日本語教育研究・情報センター准教授、政策研究大学院大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。