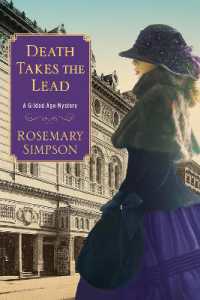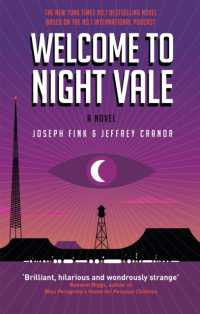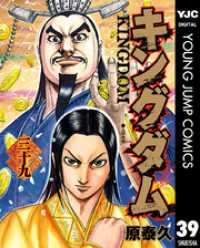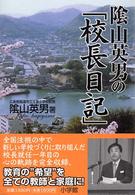- ホーム
- > 和書
- > ビジネス
- > 仕事の技術
- > 話し方・コミュニケーション
内容説明
“正解のない問題”を解決するのに必要なのは「答え」ではなく「問い」である。ワークショップ、授業、会議、プレゼン、セールス、商談、ミーティングetc.最強ファシリテーターが教える「機能する問い」のつくり方。
目次
序章 「問う力」が最強の思考ツールである(3種類の「問う力」;問う力の2つの要素 ほか)
第1章 1人称の問い―自分の思考を整理する(すべての思考の基礎となる「1人称の問い」;対象となるモノからさまざまな問いをつくろう ほか)
第2章 2人称の問い―相手の思考を引き出す(相手の情況が最大のポイントとなる「2人称の問い」;会話の質と自己開示 ほか)
第3章 3人称の問い―複数人の思考をまとめる(複数人の思考をまとめ、対話によって新たなステージへ進める「3人称の問い」;会議の場面での「全体の問い」をつくろう―会議のテーマを問いで提示する ほか)
第4章 ワークショップにおける問いの実践(ワークショップの目的と目標;ゴールイメージを明確化する対話例 ほか)
著者等紹介
井澤友郭[イザワトモヒロ]
こども国連環境会議推進協会事務局長。アエルデザイン株式会社代表取締役。NGOの事務局長をしながら、企業研修やファシリテーター育成を行なう会社を経営
吉岡太郎[ヨシオカタロウ]
株式会社エイチ・アール・ディー研究所主席研究員。BEYOND/Cラーニングデザイナー・ファシリテーター(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しょうご
11
オンライン読書会の課題本として読みました。仕事柄カウンセリング等で質問をすることが多いので知っていることもありましたが、まだまだ使えていない役立てそうなものがありました。ワークを除いてまずは一読したのでやりながら再読をします。2020/09/18
読書実践家
4
問いの重要性を再認識できる一冊。2021/05/21
Erina K
4
問う力、質問力を改善したくて手に取った本。日頃の子供に対して「なんで片付けられへんの」とか言い続けていたが、全く相手に響かないし、質問でもなんでもないことに改めて気づいた(汗)これまで発していた質問の大半は、相手の答えにくい曖昧なものばかりだったかもしれない。主語や修飾語など5w1hの具体的な表現を加えて、一人称二人称三人称で質問を組み立てることを覚えておこう。タイトルにあるが、問う力が問題解決力に繋がるのは、確かにそうかも。家でも業務でも活かしたい2021/04/30
Yuko
2
AIを敬遠するばかりでなく、少しは歩み寄らねばとの気持ちから、、また時代に取り残されないようにとの思いもあって、著者の生成AIのWSに参加。 求めているレベルの答えが返ってこないのは、それは「問い」が悪いから。具体的に、「だれが?」「なにを?」「いつ?」「どこで?」「どのように?」を意識して。 何度も何度も問いを変えて投げかけることで、私のぼんやり頭もよりクリアになるし、応答もより解像度の高いものが返って来る。 人だけでなくAIにも問う力、コミュニケーション力が大切なんですね。2024/07/10
遠山莉央
1
・ORIDで対立を解消する →事実、感情、解釈や考えを促す、次の行動 ・ICEアプローチ →考え、つながり、応能 ・思考コード →知識・理解×単純/応用・論理×複雑/批判・創造×変容 ・ARCSモデル(Jケラー) →attentionの(〇〇を知っていますか)・relevance・confidence・satisfaction 2024/12/22