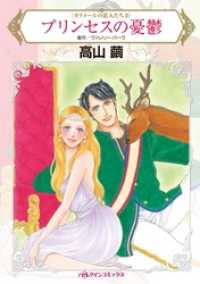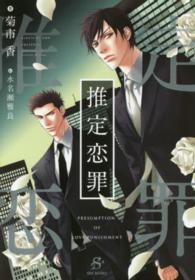内容説明
森の民に心奪われた2人の研究者が行く着く先は…。本書では、私たち二人がともに、いかにして東南アジアの狩猟採集民である森の民に魅了されるようになったのか(…)それだけでなく、そのことが今、現代世界にとって、現代日本で生きる私たちにとって、どういう意味があるのかについても考えてみたいと思う。―プロローグより。
目次
イントロダクション なぜ人類学者と言語学者は森に入るのか
プロローグ 森の民であり、日本人でもある
対談1 森の民に心奪われるとはどういうことか
論考 他者のパースペクティヴから世界を見る
対談2 狩猟採集民を知る―プナンに出会う、ムラブリに出会う
対談3 すり鉢状の世界を生きる私たちと、その外側
論考 ムラブリとして生きるということ
対談4 have notの感性にふれる
エピローグ 現代人の中にうずく「狩猟採集民的な何か」
著者等紹介
奥野克巳[オクノカツミ]
立教大学異文化コミュニケーション学部教授。1962年、滋賀県生まれ
伊藤雄馬[イトウユウマ]
言語学者、横浜市立大学客員研究員。1986年、島根県生まれ。2010年、富山大学人文学部卒業。2016年、京都大学大学院文学研究科研究指導認定退学。日本学術振興会特別研究員(PD)、富山国際大学現代社会学部講師、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同研究員などを経て、2020年より独立研究に入る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
278
『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』と『ムラブリ 文字も暦も持たない狩猟採集民から言語学者が教わったこと』の著者の共著。熱い!同じ内容を重ねるだけかもと恐れたけど、そんな事なくて。寧ろ何に根ざして語られているかを知る為にも、対談形式と違って体系的に語られているし、この2冊は読んでおいた方がより良いのかも。森の民の生き様に傾向していますね(特に伊藤さんは)。ヒトの本質的な能に繋がるのかもね。でもね個人的には科学文明も愛していて。折り合いのポイントを見極めたいよ。2024/01/21
trazom
114
閉塞感のある現代社会の向かうべき方向性を示唆するのは、哲学や経済学ではなく文化人類学ではないかと、最近つくづく思う。奥野さんはプナン(ボルネオ島)、伊藤さんはムラブリ(ラオス)で狩猟民族と一緒に暮らし、その経験に基づく二人の言葉は深い:多文化主義ではなく多自然主義、パースペクティヴィズム、「ごめんなさい」も「ありがとう」もない、専門家を作らない、分業をしない、所有という概念がない。知識やモノや金の所有をエスカレートさせる現代を生きる我々に、無所有を前提として贈与論で生きる森の民が大切なことを教えてくれる。2023/10/31
はとむぎ
16
パースペクティブ プロ奢られヤー 初めましての単語。文化人類学は、ofからwith そしてasへ。他者に成りきることで、他者を理解する。資本主義社会で、狩猟採集民族として生きることで、新たな社会を構想する。人類として発展しながら、すべての人が前向きに生きられる世界を探すということだろうか? 新たな視点が得られた興味深い本でした!2023/12/03
ぽけっとももんが
12
タイトルや装丁から想像するよりもずいぶん歯応えのある本でした。ボルネオ島のプラン、タイ・ラオスのムラブリという狩猟採集民をそれぞれ研究している著者たちの対談が主となる。研究対象についてof、with、asと変化するというのが印象的。ムラブリを、ムラブリと、ムラブリとして研究。そこまで現地の言葉を使いこなせるというのからしてすごい、くらいの残念な感想止まりなのが悲しい。2024/02/11
おさと
9
他人の視点というのも結局は「自分」が見る「他人の視点」なんだというくだりに、慄いた!2024/11/06