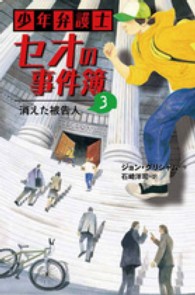出版社内容情報
短歌史のマスターピースにして批評の名著、初の現代語訳!
120年以上前の燃えるようなテキストが今、現代短歌界のトップランナー永井祐によって再生される——
正岡子規が1898年(明治31年)2月から10回にわたって新聞「日本」紙上に発表した伝説の歌論『歌よみに与ふる書』。
俳句の近代化に力を注ぎ、文学者として影響力のあった子規が、つづけて短歌を近代化すべく論じた記事は、それまでの伝統的な和歌から現在まで続く近代短歌への転機となった。
初の現代語訳となる本書では、『歌よみに与ふる書』本編のほか、読者からの質問への回答「あきまろに答ふ」「人々に答ふ」、永井祐による正岡子規10首鑑賞、解説「子規と『歌よみに与ふる書』」を収録。
短歌ブームの現在、改めて短歌という詩型を考え直すきっかけとなる、タイムレスな魅力あふれる批評の書。
内容説明
短歌史のマスターピースにして批評の名著。初の現代語訳!一二〇年以上前の燃えるようなテキストが今、現代短歌界のトップランナー永井祐によって再生される―
目次
歌よみに与ふる書 現代語訳(歌よみに与ふる書―現状について;再び歌よみに与ふる書―『古今和歌集』について ほか)
あきまろに答ふ・人々に答ふ(竹の里人に申す あきまろ;あきまろに答ふ ほか)
正岡子規+首鑑賞
解説 子規と『歌よみに与ふる書』
歌よみに與ふる書 原文
著者等紹介
永井祐[ナガイユウ]
歌人。1981年生まれ、東京都出身。2000年ごろより短歌を始める。学生時代は早稲田短歌会所属。2002年、北溟短歌賞次席。歌集に『広い世界と2や8や7』(2020年・左右社、第二回塚本邦雄賞)。2019年より笹井宏之賞選考委員
正岡子規[マサオカシキ]
1867‐1902。俳人、歌人、随筆家。本名、正岡常規。幼名は処之助、のち升と改める。慶応3(1867)年10月14日(旧暦9月17日)、伊予国温泉郡藤原新町(現在の愛媛県松山市花園町)に生まれる。明治16(1883)年、上京。明治25年、新聞「日本」に俳句論「獺祭書屋俳話」の連載を開始し、俳句革新に乗り出す。明治28(1895)年、日清戦争従軍後、帰国途中に喀血し、永い病床生活に入る。闘病のかたわら文学上の仕事は活発化し、自らの執筆のみならず、精力的に俳句の指導・添削なども行い、後進を育てた。明治31(1898)年、「歌よみに与ふる書」を発表し、短歌革新にも乗り出す。明治35(1902)年9月19日、脊椎カリエスにより死去。享年三十四(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
まー
アカショウビン
かさい
-

- 電子書籍
- 空戦魔導士候補生の教官【タテスク】 C…
-
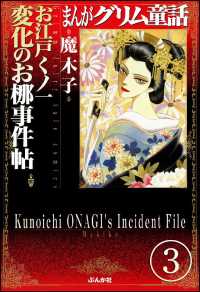
- 電子書籍
- まんがグリム童話 お江戸くノ一変化のお…