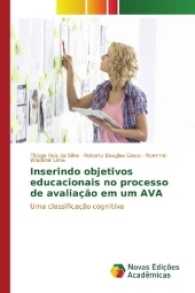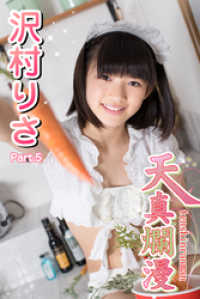内容説明
私の経験を捨象し私の意に沿わない形に解釈・編集される言説があふれる中「どうすれば私は納得できるのか」。遺伝学、弱視教育、オタク文化、当事者運動などの歴史の再構成と、語る意義を見出した「強い」主体の影に隠れた沈黙や語りがたさにもアプローチした、13人のアルビノ当事者のライフストーリーの検討をとおして、私も含めて誰も否定せず誰にとっても抑圧的ではないあり方を探索した、気鋭の社会学者、待望の単著。
目次
どうすれば私は納得できるのか?
注目すべき表現型から注目に値しない遺伝子型へ―遺伝学史におけるアルビノ
社会に働きかける「根性」「たくましさ」「精神力」の養成―弱視教育におけるアルビノ
アルビノ萌えの「後ろめたさ」からの逃走―オタク文化圏におけるアルビノ
不可視の人びとの新しい声―近年の研究動向と当事者運動の展開
新しいストーリーの生成に向けて―方法論の検討と調査概要
歴史の隙間を埋める語り
「あるあるネタ」としての問題経験
「有名な」当事者が語る目的
介入的な聞き手とマイナーな語り手
脱政治化の歴史から政治的主体化、あるいは政治からの離脱へ
著者等紹介
矢吹康夫[ヤブキヤスオ]
1979年生まれ。立教大学大学院社会学研究科博士後期課程満期退学。博士(社会学)。日本学術振興会特別研究員などをへて、現在、立教大学社会学部助教、日本アルビニズムネットワーク・スタッフ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
くさてる
21
一般的なアルビノのイメージってなんだろう。白い肌、色素の薄い髪、赤い目?そんなふわっとしたイメージをすこしずつかみ砕いてほぐしていくような一冊で、当事者である著者だからこそ書けた内容だと思う。専門的な部分も多いけれど、著者の語り口は軽やかで、飲みこみやすい。そして個人的には副題の「当事者から始める社会学」という部分がとても響いた。社会学ってなんだろうとも思った。ほかのアルビノの当事者へのインタビューを通して著者が考えたこと、そこから生まれる障害と差別への意識。ひとの声って大事だなと思った。お薦めです。2018/01/10
Mc6ρ助
4
『障害がことさらに取り出され、・・その人全体が否定されてしまうことに対して、その否定性を受け入れて改善を求める、あるいは価値を逆転させて肯定するという戦略がある。だが、問題なのはそこで良いか悪いかの選択を迫られることであり、否定性を引き受ける必要はないし、そもそもそんな問いが立てられる土俵に乗る必要もない(岡原・立岩 1995: 162; 立石 1977: 423)。(p407)』出会えたことが嬉しくなる、周りの人に読んでみてと勧めたくなる良書。2018/01/25
tu-ta
3
クリスマス前に読み終わった。 矢吹さんは 以前からの知り合いだが、 この本で紹介されている人が 同じ職場で働き始めたので、 読み始めたのだった。 世界は狭い。メモをこれから書く予定。矢吹さんの序章でのアドバイスに従って、アルビノの歴史の部分は最後に飛ばし読みした。2019/12/23
takao
1
ふむ2020/11/24
さみー
1
博士論文を書籍化したもの。縁あってアルビノの人と仕事で関わることがあるため、興味深い一冊だった。また、社会福祉系の修士課程に在籍している立場としては、問いの立て方やパラグラフの組み立て方など、得られるものが多々あった。特に、ライフヒストリーを質的に分析する際の、筆者自身がどう受け止めたか、という思考過程や、調査そのものに対する省察などが丁寧に記載されており、主観を通して客観を構築するような論構成は、とても面白かった。質的分析において語りの内容をあえて脱文脈化しないメリットが、よく分かる一冊であると感じた。2019/10/05