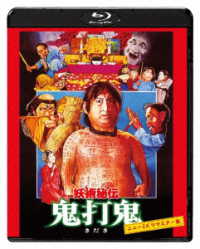出版社内容情報
超LSI研究所は1976年に設立された官民合同の技術研究組合で、競合会社(富士通、日立、三菱、日電、東芝)の技術者が共同研究する事は世界初の試みである。僅か四年の期間ではあったが、多大な成果を主に、基礎的共通的な製造装置の開発で上げ、日本が1980年代初期の半導体世界精算シェアの第一位に上り詰めるのに多大な貢献をなした。本研究所の元所員が当時を振り返る。
内容説明
超LSI共同研究所は1975年からの4年間、将来の超LSIを作る基礎的共通的な製造装置の開発を行い、1980年3月に任務を終えて解散した。開発された製造装置は、研究組合の構成会社である、富士通、日立、三菱、日電、東芝の各社に納入された。その後5社が競ってこれらを使用し、半導体素子の生産を行い、その結果、半導体デバイスの日本のシェアが急増して50%を超える事になる。その間、対米対策の不備から、米国の安全保障という壁によって反発され、「日本で使うICの20%を輸入品(当時米国製)とする」、「日本の輸出価額は米国が決める」という日米半導体協定を結ばされ、日本のシェアは下がって行くのである。しかし、半導体製造装置は健在で、世界市場シェアの多くを占めている。
目次
序論―日本の半導体は世界シェア50%を得た後、なぜ下降を辿ったのか
1章 超LSI共同研究所の設立前夜とその成果
2章 電子線源と電子光学系
3章 微細電子線描画・検査技術とその変遷
4章 可変成形ビームベクタースキャン型電子ビーム描画装置
5章 汎用型電子線描画技術とその周辺技術の開発
6章 結晶技術
7章 クリーン技術と露光技術
8章 デバイス基礎技術および試験評価基礎技術
著者等紹介
垂井康夫[タルイヤスオ]
1929年東京小石川生まれ、1951年早稲田大学第一理工学部電気工学科卒業後、工業技術院電気試験所入所。以降、IC(集積回路)の開発に従事、1965年工学博士(東京大学)ショットキーTTL素子、電子ビーム描画装置、LSIテスター等を発明、開発し、半導体産業の発展に寄与した。1976年超LSI技術研究組合共同研究所所長に就任、各メーカーら出向して来た研究員を統率し多大なるリーダーシップを発揮した。その後東京農工大学、早稲田大学において、学生、研究者の指導に当たる。東京農工大学名誉教授、現在カシオ科学振興財団理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。