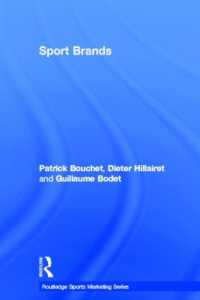内容説明
インド、ブルガリア、キューバ、スーダン、パレスチナなど、約16ヵ国の笑顔あふれる食卓。台所探検家がめぐる、小さな幸せの大切さに気づく“食と旅”のエッセイ。世界の家庭料理レシピ13品収録。
目次
アジアの台所(インドネシア―香りに包まれるココナッツオイル作り;タイ―少数民族アカ族の村のクリエイティブな野草料理 ほか)
ヨーロッパの台所(オーストリア―100年愛されるチョコケーキ レーリュッケン;コソボ―山岳地域の伝統料理蓋焼きパイ フリア ほか)
中南米の台所(キューバ―すべての人に行き渡るフリホーレス;キューバ―国民の食卓を支える黒インゲン豆 ほか)
アフリカの台所(スーダン―食事と笑顔を持ち運ぶ食卓スィニア;スーダン―切り方ひとつで三変化するオクラ料理 ほか)
中東の台所(イスラエル―イスラエル安息日の食卓は家族の歴史;パレスチナ―真っ暗な台所で思いがけぬ挽回 ほか)
著者等紹介
岡根谷実里[オカネヤミサト]
世界の台所探検家。1989年、長野県生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士修了後、クックパッド株式会社に勤務。世界各地の家庭の台所を訪れて一緒に料理をし、料理を通して見える暮らしや社会の様子を発信している。クックパッドニュース、日経DUAL等で記事やレシピを連載中。また、全国の小中高校への出張授業も精力的に行なっている。訪問国/地域は60以上(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
299
著者の岡根谷実里氏は「世界の台所探検家」を名乗る。もともとは土木工学の専門家であったようだが、いつの頃からか台所探検家に。手法は、現地で2,3日間ホームステイをさせてもらって、家庭料理を学ぶというもの。タイトルには台所を掲げるが、実際には料理に主眼が置かれている。取り上げられた国はアジア3か国、ヨーロッパ5か国、中南米2か国、アフリカ2か国、中東3か国に及ぶ。いずれもとっても興味深いが、この仕事をするからには何でも食べられないとできそうもない。パレスチナの項で、山盛りになった牛やヤギの脳みそを供される⇒ 2025/01/05
syaori
70
台所探検とは「普通の家庭におじゃまして、一緒に料理させてもら」うこと。その土地や生活、社会情勢や家族を映した料理が紹介されます。オーストリアでは祖母の代から100年以上伝わるケーキを、コロンビアでは前日の残りのスープにご飯を混ぜたカレンタードを、また内戦が続くスーダンではお手伝いの女の子が難民だったり、パレスチナの難民キャンプでは断水と断続的な停電の中で食事を作ったりというように、作る料理もその料理を作る環境も様々ですが、食卓にはいつも笑顔があって、お腹も心も満たす台所の魔法を垣間見ることができました。2024/11/29
こばまり
59
レシピも掲載されているが、私には到底現地の風味は再現できまいと眺めるだけにした。スナップ写真が小さいのと、紹介されている家族についてもう少し知りたいと思う反面、実にたくさんの国と地域が紹介されているので、むしろ満足感の高い構成となっている。2021/11/05
minami
57
「世界の台所探検家」という肩書きの著者。訪ねている国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、中東の16カ国。まさに普通に暮らす世界の人々の台所で一緒に料理を作り共に食す。世界各国の友人の紹介で実現する台所探検。もうなんて活動的なんだろうと、台所を覗くよりもそちらに驚いてしまった。でも訪ねる先々で、その地の普段食べている料理に興味津々。私にはこれは無理だと思う料理もあったけれど、食べてみたくなるいろんな料理。レシピの載っているものもある。そしてそして旅行に行きたくなる。台所は万国共通の場所と改めて実感。2021/07/18
天の川
54
台所探検家の岡根谷さん、身長148cmの小柄な身体の中はエネルギー満タン!現地でホームステイして、一緒に買い物に行って、一緒に普段の料理を作る。文字どおり「同じ釜の飯を食う」日々だ。スーダン、ボツワナ、コソボやモルドバ、パレスチナ、キューバにコロンビア。気軽には行けない国も軽々と。それぞれの国がシビアな現実を抱えながらも、人々の食事を愉しむ笑顔に偽りはない。岡根谷さんは料理を楽しみながら、社会背景にも目をそらさない。彼女の好奇心は、きっと次々に新たな課題を見つけるに違いない。2023/08/27