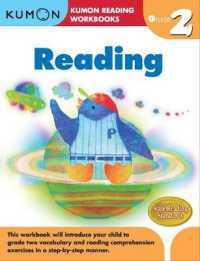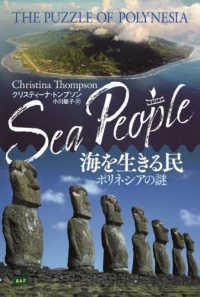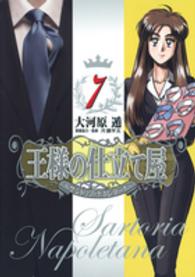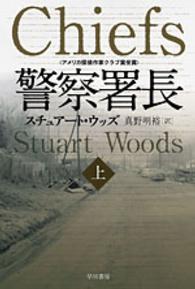内容説明
100年後、今日出会った人はほぼ全員死んでいる。本書を手にしているあなたも例外ではない。誰もが必ず死ぬ。しかし、私たちは死について、どれだけのことを知っているのだろう?死ぬとはどういうことか?人は死んだらどうなるか?ミイラや永久死体は、どうやって作られるのか?死とそれに関する研究を知ることによって、生きるということを見つめ直す。
目次
第1章 死体とはなにか(死体は人を惹きつける;魂の重さはスプーン1杯分? ほか)
第2章 人が死ぬというこう(死体を見つめた『九相詩絵巻』;死ぬと血流が止まる ほか)
第3章 ミイラに込めた願い(永久なる死体とは;日本最古のミイラ ほか)
第4章 死体をとりまく世界(死体に出会ったらどうすればよいか;死体を見ないようにする方法 ほか)
第5章 死体の利用法(死体を扱う学者とは?;死体が面白いから ほか)
著者等紹介
藤井司[フジイツカサ]
法医学者。現在は日本の研究機関に所属し、死体の身元特定方法の研究を行っている。日本では数少ない専門性をもった法医学者の1人として、各地で発見される変死体の身元確認や警察の犯罪捜査に協力している。その仕事がきっかけとなって、殺人事件が解決したこともあり、警察からも篤い信頼を得ている。何千年も昔のミイラから現代の殺人事件や葬儀事情まで、死体を取りまく文化全般に詳しい(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
GAKU
58
「まえがき」に、「死を体験したとき、その人はもう死んでいるわけだから、他人にその体験を伝えることができない。生きているあいだに、死体に関する知識をどれだけ増やしたとしても、死を本質的に理解したとはいえず、現象の入り口に立っているにすぎないのだ。」とあり、ゆえに生きている人間が死体を考える場合、結局は入門でしかないという理由で、この本は「死体入門!」という題名になっているそうです。さらに「ただ、安心してほしい。人間は誰もが死体になる。「入門」者は必ず「卒業」できることは、保証する。と結んでありました。⇒2017/10/13
いつき
5
読んで字のごとく死体に関する雑学書。でもただのトリビア寄せ集めではない。いきなりカラーの九相死絵巻から始まる。本文は九相死絵巻を交えながら死体の定義、死体の腐敗段階を図入りで説明し、さらに腐敗しない死体として3種類のミイラの作り方やその理論を解説する。4章では死体を扱う世界に触れるが、所謂雑学的な部分はここだけだ。 最後に死体がどう生者の役に立っているかを紹介してお仕舞い。特に死体の変化、動物のたかり方とその理由などを説明する2章は圧巻。2011/11/18
イカ
3
死について考えることは有益であるとよく言われる。そこで言う死は、哲学的に考える死のことである。多くの場合、そこには「死体」に関する考察は含まれていない。かくいう私自身も、死には関心があったが、死体には関心がなかった。しかし、この本を読んで、死体について知ることがどれほど重要で有意義なのかが理解できた。死体について知れば知るほど、死を客観視できるようになり、死をむやみに恐れる気持ちが薄くなり、死を明るくイメージできるようになり、何よりも、死ぬまでの生を思いきり楽しめそうな心持ちになってきた。2020/03/09
柚香
3
一時期ハヤったゾンビもののマンガ(今も連載中ですが)なんで血管の模様がでてるんだろう?って疑問がすんなり解決 マンガやサスペンスドラマを見るに当たっての知識として持っていていい内容の本 この時期こーゆー本を借りるのはちと気まずいが・・・2014/08/04
ao-king
3
人間は誰だって死体になるのだから、その死体に対して興味を持ったとしても何の不思議もない。むしろ今の日本は死体、と言うか「死」そのものを覆い隠そうという傾向がある。大震災で何人死んだ、と報道されても、実際の死体がテレビに映されることはないのだからまったくリアリティがない。これはこれで「死」を真剣に考える機会を奪っていることになるのではないかと感じた。「臭いものには蓋」していればいい、というものではない。そんなことを考えさせられた。2013/09/06