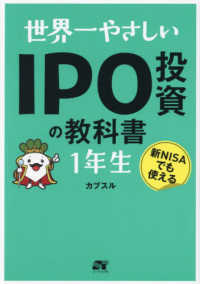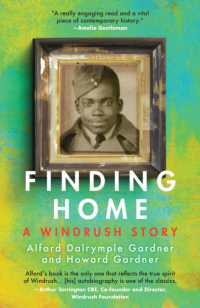出版社内容情報
鎌倉時代から明治期にいたるまで、親鸞の「物語」はどのように語り継がれてきたのか。史実ではなく「物語」としての受容や形成の視点から「親鸞伝」を読み解く。
【目 次】
はじめに―「お話」としての親鸞伝
第一章 物語型の教義書―鎌倉時代後期から南北朝時代
1『親鸞聖人御因縁』―「親鸞と玉日の物語」のはじまり/2和歌の世界からの逸脱―中世文化における和歌の意味/3聖なる人の誕生―女犯偈と成仏/4女犯偈に関わる二種の物語―中世における物語の作り方/5玉女と玉日―巫女的な女性/6読者に要求される知識―「衆」の結集と親鸞伝/7真仏因縁―「まことの仏」誕生の物語/8「真仏因縁」と『伝絵』―二元的思考の導入/9「親鸞因縁」と『伝絵』―女犯偈の意味の変更/10源海因縁―鎌倉悟真寺と荒木門徒
第二章 「正しい解釈」の追求―南北朝から室町前期
1親鸞像の父・存覚―儀式における物語の活用/2相互注釈関係―『御伝鈔』注釈史の起点/3『親鸞聖人御因縁秘伝鈔』―『御伝鈔』で『御因縁』を注釈する/4根本聖典は『御伝鈔』―彼岸から此岸へ
第三章 物語不在の時代―室町中期
1本願寺蓮如―本尊は弥陀、祖師は親鸞/2専修寺真慧―もうひとつの「全国的教団」
第四章 真宗流メディアミックス―室町後期から江戸前期
1花開く親鸞伝―注釈書から古浄瑠璃まで/2「真宗門徒の常識」の成立―知の受け皿の形成/3古浄瑠璃―門流的親鸞伝からの脱却/4『御伝鈔』注釈書―隠された意味を求めて/5『御伝照蒙記』―「正しい解釈」と「正しい史実」/6親鸞物浄瑠璃上演禁止―本願寺のダブルスタンダード/7二十四輩伝承―ヒエラルキー構築と親鸞伝説/8康楽寺の絵解き本―文字と声を架橋するシステム/9『良観和讃』―「似て非なる物語」群/10室町後期から江戸前期の「親鸞と玉日の結婚物語」
第五章 「東国の親鸞」の発見―江戸中期
1戦国末期の高田伝―三人の祖師たち/2仏光寺本『伝絵』の登場―聖典に異本があった/3出版の力―仏光寺本『伝絵』の波紋/4『高田親鸞聖人正統伝』の刊行―「実伝」の誕生/5『正統伝』における親鸞と玉日―既刊本から「秘伝」を作る/6『親鸞聖人正明伝』の刊行―『正統伝』典拠の提出/7「東国教団」の発見―真宗史における歴史認識問題の発展
第六章 読本から近代史学へ―江戸後期から明治
1赤山明神譚の在地定着―刊本から宝物が生まれる/2結城称名寺の女身堂―伝説の成長/3『玉日宮御遺状記』―平仮名絵入りの注釈書/4『親鸞聖人絵詞伝』―平仮名絵入り親鸞伝の成/5『親鸞聖人御化導実記』―語りと文字の交錯/6『親鸞聖人御一代記図絵』―江戸と明治の連続性/7近代史学の誕生―「人間親鸞」の物語
【目次】
はじめに――「お話」としての親鸞伝
『御伝鈔』への異論/深夜の箱根登山/『御伝鈔』に見る親鸞の生涯
第一章 物語型の教義書――鎌倉時代後期から南北朝時代
一 『親鸞聖人御因縁』――「親鸞と玉日の物語」のはじまり
第一話「親鸞因縁」/「月輪法皇」の創造/理論書の物語化
二 和歌の世界からの逸脱――中世文化における和歌の意味あい
題詠の時代/「親鸞の和歌」の原拠/鎮護国家の仏教からの逸脱宣言
三 聖なる人の誕生――女犯偈と成仏
玉女の誘惑/破戒する聖人たち/弥陀の化現
四 女犯偈に関わる二種の物語――中世における物語の作り方
『御伝鈔』と『経釈文聞書』/恵信尼と存覚/女犯偈の物語的性格
五 玉女と玉日――巫女的な女性
仏光寺了源の妻/女性の霊力
六 読者に要求される知識――「衆」の結集と親鸞伝
カボチャの馬車/祖像を中心とした結集/拝読・聴聞されるテクスト
七 真仏因縁――「まことの仏」誕生の物語
善光寺縁起による枠組作り/中身は聖徳太子伝/生身仏信仰/神道との親近性
八 「真仏因縁」と『伝絵』――二元的思考の導入
平太郎は弥陀ではない/門流を超える親鸞伝
九 「親鸞因縁」と『伝絵』――女犯偈の意味の変更
事実の記録めいた物語/和歌の世界への回帰
十 源海因縁――鎌倉悟真寺と荒木門徒
講式と物語/活動路線の変更
第二章 「正しい解釈」の追求――南北朝から室町前期
一 親鸞像の父・存覚――儀式における物語の活用
『御絵伝』と『御伝鈔』の創出/存覚の権威
二 相互注釈関係――『御伝鈔』注釈史の起点
『敬重絵』と『六要鈔』/異なる教義の併存
三 『親鸞聖人御因縁秘伝鈔』――『御伝鈔』で『御因縁』を注釈する
流布しない書物/存如による書写/如信の口伝
四 根本聖典は『御伝鈔』――彼岸から此岸へ
教義書と注釈書の違い/何を採り、何を捨てるか/冷泉家流『伊勢物語』注釈との関わり/法然門における正当性の主張
第三章 物語不在の時代――室町中期
一 本願寺蓮如――本尊は弥陀、祖師は親鸞
全国的教団の構想/『御俗姓御文』/曖昧さの排除
二 専修寺真慧――もうひとつの「全国的教団」
第四章 真宗流メディアミックス――室町後期から江戸前期
一 花開く親鸞伝――注釈書から古浄瑠璃まで
二 「真宗門徒の常識」の成立――知の受け皿の形成
『御伝鈔』の共通教養化/『高僧和讃』と「正信偈」 /本地物と真宗
三 古浄瑠璃――門流的親鸞伝からの脱却
内容説明
浄土真宗の祖・親鸞。本書では、歴史上の人間親鸞ではなく、鎌倉時代から明治期にいたるまで、「親鸞の物語」がどのように語り継がれてきたのかを、「親鸞と玉日の結婚物語」を主軸として、「物語」の受容や形成の視点から読み解いていく。それぞれの時代における教団の思惑やメディアの発展などによってさまざまに変化する「親鸞像」は、信者や社会が求めた親鸞であり、彼らの希望や願望の化身とも言える。時代とともに変化する「親鸞像」から、人びとが親鸞に託した思いを探る。
目次
第一章 物語型の教義書―鎌倉時代後期から南北朝時代
第二章 「正しい解釈」の追求―南北朝から室町前期
第三章 物語不在の時代―室町中期
第四章 真宗流メディアミックス―室町後期から江戸前期
第五章 「東国の親鸞」の発見―江戸中期
第六章 読本から近代史学へ―江戸後期から明治
著者等紹介
塩谷菊美[エンヤキクミ]
1957年、神奈川県に生まれる。1979年、早稲田大学第一文学部日本文学科卒業、1997年、和光大学人文学部文学科専攻科修了。2003年、早稲田大学にて学位取得。博士(文学)。現在、同朋大学仏教文化研究所客員所員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。