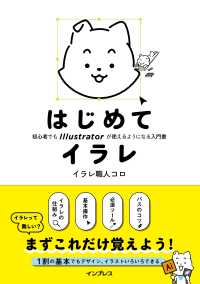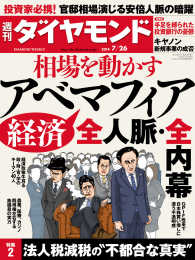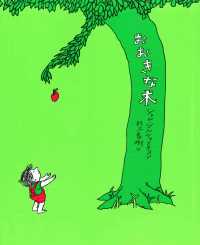出版社内容情報
7世紀のインドの僧侶は何を食べ、どんな生活をしていたのか。671年、戒律を学ぶために海路によりインドに渡った唐の僧・義浄三蔵が、留学先ナーランダー寺での衣食住にわたる戒律の実態を報告した第一級史料の現代語訳、衝撃の文庫化。
*
インドの僧侶が朝起きて、一番にすることは何か。
感染症対策万全な食事内容とその方法とは。
歯ブラシの使い方とは。
トイレのしかたとは。
私有財産の所有がほとんど許されない僧侶の遺産相続方法とは。
遠方から来た客人を、どのように接待すべきか。
葬式のきまりとは……。
*
義浄が見たインドの戒律とは、自由を縛る「べからず集」と化した戒律とは大違い。過酷な気候と限られた時間のなかで、仏道の目的到達のために、あえてしなくてもよいものを省いていく経験則の集積であった。
『南海寄帰内法伝』は、義浄が、感嘆をもって、故郷の中国や、途中寄港した東南アジアの戒律と比較しながらまとめあげた、空前絶後のインド留学レポである。
内容説明
七世紀のインドの僧侶は何を食べ、どんな生活をしていたのか―。唐の僧・義浄は、六七一年、戒律を学ぶために海路で天竺(インド)へ。留学先のナーランダー寺院で、インドの気候に即した現実的で健康第一な戒律が実践されていることに驚く。朝起きて一番にすること、歯みがきの方法、トイレのきまり、衣の着方、感染症対策を考慮した食事作法、客人の接待方法、葬式のきまり等。本書は、中国や東南アジアの風習とも比較しながら、当時の衣食住にわたる戒律の実態を報告した、第一級のインド留学レポである。
目次
仏教通史―宇宙開闢から唐代まで
破夏非小―夏安居―雨期三ヵ月の合宿―を破っても僧伽内の地位の降下はない
対尊之儀―尊像・尊者に対するきまり
食座小床―食事は小さな椅子に腰掛けてとる
餐分浄触―食事には浄・不浄区別の原則がある
食罷去穢―食後に穢れを去る
水有二瓶―浄と不浄の二種類の水がある
晨旦観虫―朝、水中の虫を観察する
朝嚼歯木―朝には歯磨きをする
受斎軌則―お斎のきまり
著者等紹介
宮林昭彦[ミヤバヤシショウゲン]
1932年、長野県生まれ。1955年、大正大学大学院文学研究科仏教学専攻修士課程修了。1978年、大正大学教授。1985~6年、大正大学より海外研修を命じられる。南方上座部仏教の戒律実態調査のため、タイ国バンコク市トンブリのワット・パクナム・パーシーチャロアンにて出家・得度、短期間の僧伽出家生活を実修。1997年、大正大学人間学部長を経て、2001年、大本山光明寺第百十二世法主就任。2014年、遷化
加藤栄司[カトウエイジ]
1948年、千葉県生まれ。1982年、大正大学大学院文学研究科宗教学専攻博士課程満期退学。1985~6年、前記タイ国バンコク市トンブリにての海外研修に同行。公益財団法人中村元東方研究所専任研究員。現在、天台宗圓宗寺住職(栃木県下都賀郡壬生町大字上稲葉)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。