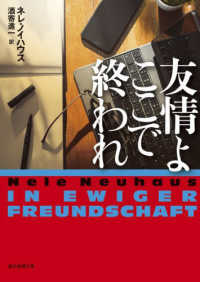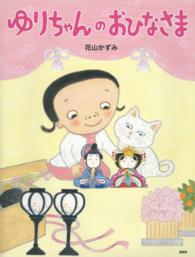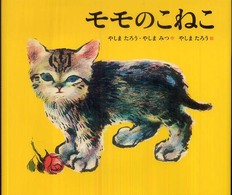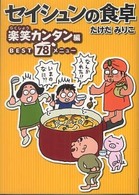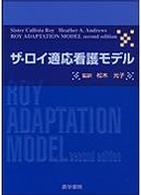内容説明
日本人の苗字の起源は、弥生時代に韓半島から渡来した人びとが祖国の地名や種族名、職能集団名を古代朝鮮語や大和ことばにあててあだ名で呼んで私称したことに始まる。縄文人は生活に必要な範囲でそれぞれ名前を付けて呼んでいたが、渡来人の鉱山・鍛冶技術や稲作技術を吸収するとともに大和ことばで自分たちのあだ名を苗字として名乗ったのである。『埼玉苗字辞典』をベースに旧説を覆し、日本人の苗字の起源を新たな視点で解読する。
目次
第1章 渡来の人々(中国江南の呉越族倭人;朝鮮半島の呉越族倭人 ほか)
第2章 古代苗字の一〇〇大姓(渡来の様子;あだ名の私称 ほか)
第3章 部民の姓氏と苗字の違い(村と郷;孔王部 ほか)
第4章 武士の名字と苗字の違い(名字と苗字;苗字の所見 ほか)
著者等紹介
宮内則雄[ミヤウチノリオ]
理学博士。昭和50年東京教育大学(現・筑波大学)物理学科卒業。昭和55年東京大学物理学専攻博士課程修了(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。