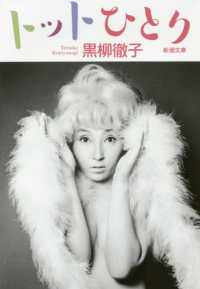出版社内容情報
日本三大祭りのひとつ、祇園祭と古代イスラエルの祭を徹底比較する前代未聞の書。最も日本的と考えられている祇園祭と、最も非日本的と考えられている古代イスラエルの祭りがなぜ、比較できるのか? 距離的にみても、7000キロメートル以上も離れ、成立年代も千年以上離れている両者が、なぜ結びつくのか? しかし、百年単位、千年単位で、メソポタミアの地から、陸や海のシルクロードを通って、メソポタミアのやシルクロードの文化と宗教を巧妙にデフォルメした形で、日本に持ち込んだ勢力が存在するのである。それはアジアに進出したイスラエル人=秦氏である。古代イスラエルの民がシルクロードにおいて東洋的ユダヤ人=秦氏に変容し、シオン祭を祇園精舎大祭、祇園祭へと変容させながら日本の祭祀文化として醸成し、京都で開花させたのである。それらを歴史・宗教・文化の多方面からの展開で説明、証明する、目からウロコの1冊!
はじめに 「祇園祭は〈王のシオン祭〉の日本的展開である」
祇園祭の歴史的、社会的分析の必要性/「祇園祭は古代イスラエルの総合祭である」
●第1章 祇園祭とシオン祭の謎
祇園祭は「日本を代表する世界の祭」/ささやかれていた祇園祭とシオン祭の類似性/祇園祭は疫病退散の祭としてはじまったが/「王のシオン祭」から仮庵祭へ/祇園とシオンとは同根か/仮庵祭がなぜ、祇園祭と関係あるのか/祇園祭と過越祭の密接な関係
●第2章 祇園神事とシオン神事の謎
仮庵祭は「イスラエルの三大祭」、祇園祭は「日本の三大祭」/イスラエルの新年祭も約一カ月の間続く/祇園祭の日程はイスラエルの新年祭にほぼ同じ/神幸祭と仮庵祭の共通点/還幸祭とホシャナ・ラバの類似点/神事済奉告祭とシュミニ・アツェレットの類似点/祇園祭の前祭はイスラエルのハヌカ(光の祭)に似ている/茅の輪くぐりはどこから来たか/祇園祭とシオン祭の驚くべき共通点
●第3章 八坂神社とイスラエル神殿の謎
八坂神社の神は新羅経由の神か/御神輿の起源は「契約の箱」にある/「契約の箱」はこうして生まれた/「契約の箱」は征服戦の先頭に立つ/「契約の箱」はアロンの杖を表している?/くじ取り式とくじの役割/仮装祭(プリム)と人形・仮面の意味/祇園祭における船と荷車の意味/ 園祭と「ノアの箱舟」の謎/「手洗井戸開き」と「水汲み場の歓喜」の謎/イスラエルの祭司と山伏の装束は似ている
●第6章 懸装品とタペストリーの謎
祇園祭の織物とイスラエルの織物の比較/祇園の染織とイスラエルの染織の比較/祇園の絹とイスラエルの絹の比較/祇園の絵画・彫刻とイスラエルの絵画・彫刻の比較/懸装品に描かれる四霊獣は中国起源だが/竜神と竜王は皇帝と天皇の象徴になった/獅子はエジプト起源のライオンがモデル/三足烏を太陽の使者として尊重する日本の神社
●第7章 祇園祭の象徴とユダヤ教の象徴の謎
祇園守紋には聖書が隠されている/祇園守紋には十字架も隠されている/秦氏と関係の深い地方公共団体とイスラエルの紋章の謎/天皇家の菊花紋のルーツはメソポタミアの太陽紋か/日本の「三種の神器」とイスラエルの「三種の神器」/御神輿の鳳凰は「契約の箱」のケルビムのことだ/なぜ、これほどまでに房にこだわるのか/なぜ、赤色と白色を尊重するのか
●第8章 桓武天皇とソロモン王の謎
古代げた
●第11章 祇園祭と諸階層の謎
祇園祭と天皇家の深い関係/祇園祭と秦氏の深い関係/さまざまな職工を輩出した秦氏/祇園祭で秦氏商人の果たした役割/祇園祭になぜ、茶道家元がかかわっているのか/祇園祭は先住民系の奴隷を使役した
●第12章 祇園祭と御神輿の伝播の謎
秦氏の植民と祇園祭の伝播/秦氏系商人も八坂神社、祇園祭を全国に伝播させる/九州では福岡県と大分県が祇園系祭の盛んな所/中国四国では、島根県、広島県が祇園系祭の盛んな所/近畿では大阪府、兵庫県が祇園系祭の盛んな所/中部甲信越では愛知県、長野県が祇園系祭の盛んな所/関東では東京都、埼玉県が祇園系祭の盛んな所/東北北海道では青森県、岩手県が祇園系祭の残る所
●第13章 祇園囃子とイスラエル音楽の謎
祇園祭の楽器とイスラエルの楽器の類似点/イスラエルの楽隊の消滅と日本の雅楽の復活/琴を弾いて出世したダビデと秦酒公/祇園祭の伝統芸能とイスラエルの歌舞音曲の類似点/山鉾のテーマになっている能、謡曲のルーツは何か/大和朝廷による先住民征服をテーマにした芸能/日本のお囃子はヘブライ語の賛歌?/祇園祭のヘブライ語の囃子と神への賛歌
[前略]
結論的なことを言えば「祇園祭は古代イスラエルの〈王のシオン祭〉の日本的展開である」「祇園祭は古代イスラエルの祭の主要なものを合わせた総合祭である」「祇園祭は〈八坂神社の祇会=古代イスラエルの過越祭〉と〈京都町衆の山鉾巡行=古代イスラエルの仮庵祭〉などからなっている」「イスラエル王国のシオン祭が、海と陸のシルクロードを通って、インドの祇園精舎(釈迦が長く滞在した仏教の聖地)に持ち込まれ、仏教やヒンズー教と習合し、それを法道(マーリヤダーンマ仙人)一行が長安、新羅、播州(兵庫県)経由で京都に持ち込んだ」というのが、本書の結論である。
なぜ、そんなことが主張できるのか。なぜ、祇園祭とイスラエルの祭が結び付くのか。なぜ、祇園会と過越祭が結び付くのか。なぜ、山鉾巡行と仮庵祭が結び付くのか。あまりにも信じがたいことではないか。そのような声が嵐のように聞こえてきそうである。
しかし、百年単位、千年単位で、メソポタミアの地から、陸や海のシルクロードを通って、日本列島に上陸した勢力が存在するのである。メソポタミアの、シルクロードの文化と宗教を巧妙にデフォルメした形で、あるいはオブラートに包んだ形で
内容説明
最も日本的と考えられている祇園祭と、最も非日本的と考えられているイスラエルの“シオン祭”が、なぜ、比較できるのか?地理的には7000キロ以上も離れ、成立年代も千年以上離れているのに、なぜ結びつくのか?遙かなるメソポタミアの地から渡来した祇園精舎大祭の歴史と伝承を解き明かす日本神仏祭祀考。
目次
「祇園祭は“王のシオン祭”の日本的展開である」
祇園祭とシオン祭の謎
祇園神事とシオン神事の謎
八坂神社とイスラエル神殿の謎
祇園祭と祇園精舎大祭の謎
山鉾と仮庵の謎
懸装品とタペストリーの謎
祇園祭の象徴とユダヤ教の象徴の謎
桓武天皇とソロモン王の謎
祇園祭とシルクロードの謎
祇園祭と諸宗教の謎
祇園祭と諸階層の謎
祇園祭と御神輿の伝播の謎
祇園祭とイスラエル音楽の謎
著者等紹介
久慈力[クジツトム]
1949年岩手県生まれ。ノンフィクション作家。縄文文化、先住民文化、東北古代史、エミシの抵抗史、日本古代史、アメリカ合衆国史、世界史に関心をもち続け、それらをテーマにした創作活動も行う。「もののけ姫」の批評をきっかけにして、懸案になっていた東北古代史の再構築、日本古代史の再構築へとりかかる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価