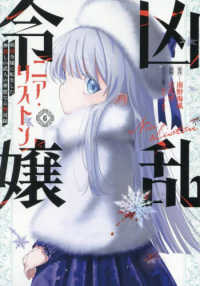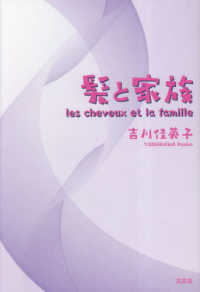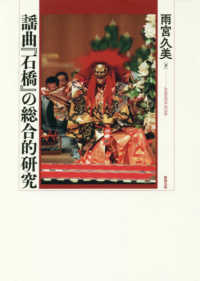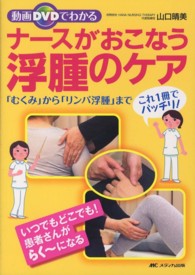内容説明
私たちの生活はさまざまな慣習・行事・言葉に満ちています。それらをていねいに分析し、日本の一般庶民の暮らしを読み解くためにはじまった学問が民俗学です。例えば、正月に餅を食べるという慣習。多くの人にとって当たり前のことになっていますが、なぜ正月に餅を食べるようになったのでしょうか。特別な行事でなくても、“黒猫を見ると不吉なことがおこる”、“人のうわさも75日”などと言われますが、このような俗信、ことわざは何を根拠に広まったのでしょうか。こういったことを考えるのが民俗学の第一歩です。本書は、民俗学のおもしろさを少しでも多くの人たちに知ってもらうために生まれました。民俗学が扱いうるありとあらゆる主題を集め、イラストとともに、わかりやすく、おもしろく解説しています。
目次
第1章 民俗学とは何か
第2章 経験的民俗学
第3章 祈願と畏怖の民俗学
第4章 人生儀礼の民俗学
第5章 暮らしとなりわいの民俗学
第6章 行事と祭の民俗学
第7章 ことばと遊びの民俗学
第8章 社会と人間関係の民俗学
第9章 民俗学の課題
著者等紹介
八木透[ヤギトオル]
1955年生まれ。仏教大学文学部教授。専門は民俗学
政岡伸洋[マサオカノブヒロ]
1964年生まれ。四国学院大学社会学部助教授。専門は民俗学
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
しちめんどくさい学説史や方法論の話はほとんど抜きに、妖怪、祭り、冠婚葬祭など、話の種として使える民俗学の雑学をたんまり集めた楽しめる入門書。季節の節目などいろいろな文化的「区切り」をつけるものとして行事があり、また妖怪や神々がある一方、現代における民話や祭りの形も語られ面白い。よさこい系の祭りは戦後生まれた「創られた伝統」だが、それだけに老若男女、マイノリティも分け隔てなく参加する点において男性中心主義的なそれまでの祭りと一線を画す、という指摘が興味深い2013/10/02
トーマ
6
図書館本。 憧れている作家や映画監督の殆んどの人が、必ず民俗学を勉強しているので、自分もガッツリ勉強しようと決意。とりあえず入門書的からと思い読んでみました。本書は様々なテーマをわかり易くまとめていて、やっぱり民俗学って面白いなぁと感じる一冊です。民俗学に興味がある人は是非読んでみてください。割と知っていたことも多く、雑学本みたいな感覚でも読めます。なんだか日本人って、本当の意味や願いは伝承されずに、「形」や「システム」、「世間体」だけで行事を行っている気がする。自分としては色々考え深いものがありました。2016/12/06
ひねもすのたり
4
民俗学といえば柳田國男だったりするわけですが、入門書のようなものがないかぁ~と探して手にした一冊です。 日常生活の中にある風習や俗信からアプローチするかたちを採っています。 簡潔でわかりやすいんだけど、あまりにも物足りません。 ただ物足りないなら他の本も読んでみれば的なスタンスだとするなら入門書として適切だろうと思います。 次はフィールドワークの民俗学者である宮本常一。 異端視される民俗学者赤松啓介を読もうと思います。2015/04/10
kassie
0
大学時代にテキストとして使用。
きずわ
0
ホントに雑学って感じですが、日頃の当たり前にやってるけど何故こんなことをやっているのか?ということが分かりやすく解説してあって楽しかったです!2012/09/09