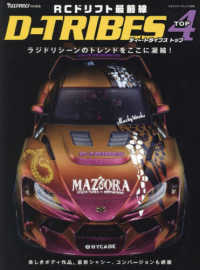内容説明
明治日本の登場から、琉球、ヴェトナム、朝鮮、チベット、モンゴルへと続く属国・藩部の再編を、沿海と草原オアシス世界の双方から掴み、現代中国の原型が浮かび上がる過程を詳述、万国公法などの翻訳概念の変容を手がかりに、誰も描きえなかった「中国」誕生の全体像に迫った渾身作。
目次
第1部 危機の時代へ(清朝の対外秩序とその変遷―會典の考察を中心に;明治日本の登場―日清修好条規から「琉球処分」へ;新疆問題とその影響―「海防」論と「屬國」と「保護」)
第2部 属国と保護のあいだ―「越南問題」(ヴェトナムをめぐる清仏交渉とその変容―一八八〇年代初頭を中心に;清仏戦争への道―李・フルニエ協定の成立と和平の挫折;清仏戦争の終結―天津条約の締結過程)
第3部 自主から独立へ―「朝鮮問題」(「朝鮮中立化構想」と属国自主;自主と国際法―『清韓論』の研究;属国と儀礼―『使韓紀略』の研究;韓国の独立と清朝―「自主」と「藩屬」)
第4部 「領土主権」の成立と「藩部」の運命(「領土」概念の形成;「主権」の生成―チベットをめぐる中英交渉と「宗主権」概念;「主権」と「宗主権」―モンゴルの「独立」をめぐって)
著者等紹介
岡本隆司[オカモトタカシ]
1965年京都市に生まれる。現在、京都府立大学文学部教授、博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
17
清朝の体制から「中国」というネイション成立に転換する過程を、対外秩序の視点から明らかにする。「朝貢」「互市」「藩部」「属国」「領土」「主権」など、漢語概念に着眼し、そうした概念をめぐる内外の認識・観念、行動、夫々の時系列的な変遷を、ベトナム、朝鮮、チベット・モンゴルなど対外交渉過程での翻訳概念を徹底的に考察する事で解き明かしていく。◆既存の研究成果に単に依拠せず、更に深堀する著者の姿勢が全章からうかがえる。研究者としての力量を見せつけられたような気分、只々圧倒された。2017/09/26
かんがく
15
各国の外交史料の引用と詳細な分析が続き、なかなか読むのに骨が折れたが、内容はとても面白かった。伝統的な朝貢冊封体制で成り立つ東アジアの国際秩序と、国際法と条約で成り立つ西洋近代の国際秩序の対立。第一部で藩部、朝貢、互市からなる清の外交秩序に触れたうえで、第二部ではベトナム(清仏戦争)、第三部では朝鮮(日清戦争)、第四部ではチベット/モンゴル(英露グレートゲーム)が扱われる。朝貢国に「属国自主」という矛盾した概念を使用する清と、実質的な統治を重視する列強。外交における翻訳の難しさも伝わった。2020/03/20
さとうしん
14
当然ながら「中国」の国号論ではなく、ネイションとしての「中国」が形成されていくさまを、清朝の外交史と、「属国」「領土」「主権」など国際政治に関わる翻訳概念と旧来からの秩序観念との折り合いをどう付けていったかを中心に追うという内容である。その折り合いは現在でも完全につけられたとは言い切れず、現在にも尾を引いているとのことだが、その問題は「中国」だけでなく、中東やアフリカも共有する普遍的な問題なのではないか、現在は世界的にその精算が迫られている時代なのではないかと思ったが…2017/03/20
MUNEKAZ
11
清末の列強との条約を詳細に分析し、「藩部」「朝貢」「互市」といった東アジア独自の外交秩序が、「領土」「主権」といった西洋由来の外交秩序に変わっていく様子が描かれる。それは不透明であった「属国」と「領土」の違いを浮き上がらせ、現在至る「中国」の領土が確定していく。西洋由来の用語を漢語に直す際の表記のゆれや概念のあいまいさ、それが次第に実態を伴っていく様は実にスリリングで面白い。現在の中国が、なぜ領土問題にあそこまで拘泥するのかの一端が見えてくる一冊であった。2020/07/27
Cheryl Wu
2
三か月もかかってようやくこの一冊を読了。とても有意義な時間を過ごした。「中国」というネイションはそもそも存在しなかった。前近代の対外秩序が近代の国際関係に適応するためにあらゆる紛争と戦争を通して、翻訳観念によってようやく近代の国民国家を転じた。岡本氏の史料解読へのこだわりに感心。とても勉強になった。2017/06/25