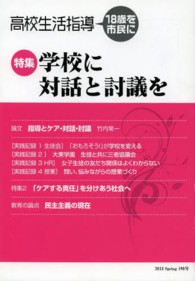内容説明
12万年前の埋葬跡から出土した貝殻ビーズ、新石器時代のストーンビーズ、縄文時代の翡翠、エジプト文明のファイアンス、インダス文明のカーネリアン、大航海時代のガラスビーズ…、その素材や細工は地域や時代によって多種多様。そして現代世界にはあらゆる素材のビーズがあふれ、まさに百花繚乱。同時にビーズは、富や威信、集団の象徴など社会的役割を担ってきた。本書では、ビーズの誕生した12万年前から現在まで、地球全域をフィールドに、ビーズを手がかりとして人類の歴史をたどる。
目次
人類とビーズ
1 ビーズの誕生とその展開(人類最古のビーズ利用とホモ・サピエンス―世界各地の発見から;新石器時代のストーンビーズ―狩猟採集・初期農耕時代の東アジア;縄文時代の装身具―多様な素材と翡翠ビーズ;先史琉球の貝ビーズ文化―豊かな素材と素朴な文化)
2 古代国家と古代文明の形成・展開(古代日本とユーラシア―ガラスビーズからみる交易;インダス文明のカーネリアン・ロード―古代西南アジアの交易ネットワーク;弥生・古墳時代の多様なビーズ―社会の複雑化と装飾;古代エジプトの社会をつなぐビーズ―王と家臣、神と人;中国文明の宗教芸術にみるビーズ―敦煌莫高窟の菩薩装身具)
3 大航海時代と世界システム(アフリカに渡ったガラスビーズ―ビーズ文化を受容した社会、しなかった社会;アイヌと北方先住民を結ぶガラスビーズ―交易の歴史と文化的役割;オセアニアのガラスビーズがきた道―航海誌・考古学・民族資料からたどる;オセアニアの貝ビーズ文化―欧米化のなかの婚資と地域通貨)
4 地域文化の持続と変容―ビーズからみた現代世界(東アフリカ牧畜社会の若者文化―ビーズにみる社会と文化の変容;台湾原住民族の文化の多様性―ビーズにみる過去と現在;現代アイヌのタマサイ―文化のシンボルとしてのビーズ;タイの若者文化と土製ビーズ―流行と衰退が映す社会の変容;日本で華開くビーズ文化―ガラスビーズ・ビーズバッグ・ビーズ織り)
著者等紹介
池谷和信[イケヤカズノブ]
国立民族学博物館教授、総合研究大学院大学教授。専門は環境人類学、人文地理学、アフリカ研究、地球学、生き物文化誌学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takao
Book shelf
Go Extreme
夏みかん
-

- 洋書
- Iman