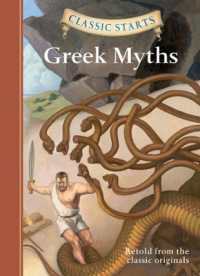内容説明
「人はなぜ遊ぶのか?」―古今東西の先人が取り組んだ命題に人類学のフィールドワーカーが挑む。遊びを知的に考察することの楽しさを分かちあう、遊び研究のエッセイ集。
目次
人の遊びをどうとらえるか―遊び論の二つの系譜
遊び研究の“むずかしさ”と“おもしろさ”―動物行動学からみた系譜
森に遊び森に学ぶ―狩猟採集民の子どもの遊び
ニホンザルの遊びの民族誌―金華山・嵐山・幸島・志賀高原のコドモたち
人間らしい遊びとは?―ヒトとチンパンジーの遊びにみる心の発達と進化
いまの子どもは本当に遊ばなくなったのか―野外体験にみる子どもたちの遊び
著者等紹介
亀井伸孝[カメイノブタカ]
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所研究員。専門は文化人類学、アフリカ地域研究。おもな著作に『アフリカのろう者と手話の歴史』(明石書店、2006年、2007年度国際開発学会奨励賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tatsuya.m
1
ニホンザル、チンパンジー、狩猟採取民の子どもの遊びに注目して、遊びとはなんなのかということを考えていくという内容でした。それぞれの種に共通する部分がたくさんあり、それを比較することでのおもしろさも感じられました。筆者の「現代の子どもたちは遊ばないように見えて、実は多彩な遊びを生む力を備えている。遊べない子どもたちという見方は…自然を排し、便利を優先させて遊びの可能性をせばめてきた社会の姿である」という部分にも納得させられました。2013/08/14
ashco
0
問題意識の種をいくつも受け取れた気がします。とりわけ明和政子さん執筆の章がおもしろかったです。2010/01/27
マッサン
0
安心できる環境だとサルの遊びは増えるというのは、当たり前かもしれないけど面白い。「この遊びはこういう機能がある」「将来的にこう役立つ」という考察は簡単だが、本当にそうなのだろうか?将来に何も役に立たないことだとしても、子ども達は関係なく楽しく遊んでるのではないか?そういう視点は丁寧で、真摯にあそびと向き合ってる気がした。遊び研究は泥沼だ!2024/05/15