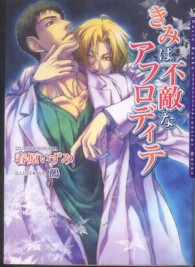内容説明
正義は暴走しないし、人それぞれでもない。「正しさ」をめぐる会話の事故はいかにして起こるのか。言語哲学から「正しいことば」の使いにくさの根源を探る。
目次
序章 正しいことばの使い方
1 「正義」というテクニック(「正義」の模範運転とジョン・ロールズ;「正義」の前提としての「公正」;道徳教育と「正しいことば」の危険運転;「道徳としての正義」とトランプ現象)
2 「正しいことば」のよりどころ(「会話」を止めるとはどういうことか;「関心」をもつのはいいことか;「自由」を大切に使う;わたしたちの「残酷さ」と政治)
3 「公正」を乗りこなす(理論的なだけでは「公正」たりえない;「公」と「私」をつらぬく正義;「公正」というシステムの責任者;正義をめぐって会話する「われわれ」)
著者等紹介
朱喜哲[チュヒチョル]
1985年大阪生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。大阪大学社会技術共創研究センター招へい教員ほか。専門はプラグマティズム言語哲学とその思想史。前者ではヘイトスピーチやデータを用いた推論を研究対象としてあつかっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はっせー
52
難しい内容であるが、読めて良かったと思う作品であった!本書はジョンロールズとリチャードローティという2人の哲学者の理論を元に話が展開されていく。キーワードは「会話を止めるな」ではないかと思う。昨今インターネット上などで論破が流行っている。これは会話を止めるわかりやすいものである。さまざまな理論などを使って現状を分析し、解決への糸口を探したい。2024/09/18
特盛
23
評価3.8/5。読書会テーマ本。著者は100分で名著のリチャード・ローティの回を担当。今回は正義論におけるロールズの概念を軸とした正義の言葉遣いに関する考察。功利主義でもなく、道徳的正義でもなく、リベラルな正義の手続きがポイントだ。善の構想でなく、公正なプロセスで調停された合意、その構想が正義とする。積極的無関心、消極的自由、残酷さへの合意としてのリベラル(シュクラー)、公私の区別(ローティ)などが紹介される。正義の議論の場で会話を終わらせないことを優先目的とし、事故(会話の終了)を防ぐかが本書の主眼だ。2024/06/28
ほし
15
ロールズ、ローティらの哲学者を参照しつつ、「正義をめぐる会話」を指向する一冊。「正義」のような日常的に使いづらい「正しいことば」を、どうしたら何とか使いこなせていけるのか。筆者はロールズの議論をもとに、「正義」は個々人の「善」とは異なるものであり、社会を成り立たせるために求められる条件とルールであるとします。個人的に印象深いのが「無関心」の重要性と「消極的自由」を論じた6、7章で、新たな視座を与えてもらえたように感じました。社会全体を不安が覆い、そこらじゅうで軋んだ音が聞こえる今、読めてよかった一冊です。2024/12/30
ちょこ
11
一般書としてわかりやすい言葉を用いて書いてあったにも関わらず、哲学って難しいなあと思ってしまった。言わんとしてることの輪郭は掴めた気がするがそこから先はまだまだ私には難しい。もっともっと読み込まないと私には本書をしっかりと理解するのは時間がかかりそうだが哲学に触れることができたのはよかったと思う。2025/08/03
はとむぎ
11
ジョンロールズ曰く正義とは、公正を前提として、人間社会を上手く回していくためのもの。 日本の学校教育では、正義は個人の内面のものとして扱われている。 だから正義が相対的な物になってしまうと。 確かに一理あるかも。2024/01/07