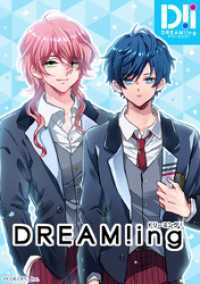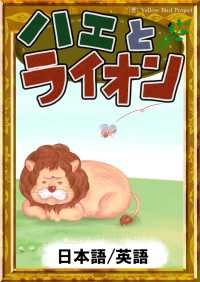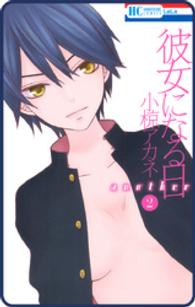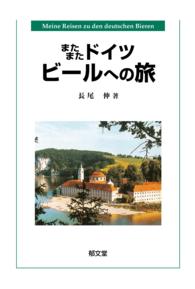出版社内容情報
中国からの漢字の輸入にはじまり、やがて主に「ひらがな」を交えた独自の文字・書風へと至り発展していく日本の書の歴史を、迫力の図版とともに「鑑賞」する人の視点から解説する。
目次
第1章 日本の書の黎明期―文字の伝来から独自の書風の萌芽(文字が日本にやってきた;王羲之書法の定式化;奈良時代の清新な書;日本語表記の工夫;三筆というエポック)
第2章 日本の書の完成―和様書・かなの完成とその展開(和様書の胎動;和様書の完成 三蹟;かな書の展開;かな書の完成 平安古筆;文字の「景色」 三色紙;王朝美の結晶 料紙装飾;新時代の表現に向けて)
第3章 日本の書の多彩な展開―和様書の類型化と中国書法の影響(和様書の展開と流儀書道;鎌倉新仏教の祖師たち「個」の表現;書と骨董品のはざま 墨蹟;書の豊穣の時代)
第4章 近現代への道程―唐様・和様の分化と現代書道の胎動(和様書の新境地 寛永の三筆;「唐様」の隆盛;書の多彩な展開;近代文化人の書;現代書道への道)
著者等紹介
田中亮[タナカアキラ]
1961年香川県生まれ。高野山大学大学院修士課程修了(密教学専攻)。書道専門出版社での書籍・雑誌の編集職を経て、現在、書・美術・東洋文化についての研究・執筆等にあたっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
お抹茶
5
書作品の表現を味わうことと書かれた文字をテキストとして読むことは別で,まずは読もうとしなくていい。中国の書は穂を紙に対して垂直にして筆線が引き締まる一方,和様書では穂の腹で紙を撫でるような運筆で,滑らかな曲線状の字画が生まれる。八世紀以降の基本となった王羲之書法を超えた筆法で,修飾的な表現も生んだのが空海,嵯峨天皇,橘逸勢。草書の崩しの限界を超えた先にひらがなが生まれ,和様書の完成と軌を一にし,日本語の美的表現の両翼を担った。武家が台頭すると,典雅な王朝風の書から直接的でシンプルな平明な表現へと展開した。2024/07/15
Tomonori Yonezawa
4
県立Lib▼'24.3/10 初版1刷▼四章95頁、黎明期、完成、多彩な展開、近現代▼日本の「書」のグラビア本って感じ。「墨」は気合い入りすぎててカンベンって号もあるが、これは気合入ってるのは分かるが抑制が効いてる感じ。ただし、薄くするためにページに写真と解説を一緒にしており、ややゴチャゴチャ感と写真がちょっと小さいな。手本にするには不向き。著者もはじめにで入り口のガイドにすぎないと述べてるように、気になった書家を調べるといいんじゃないでしょか。▼76頁、近衛家熙「蘭亭序巻」にて、本当に見事だと感服した。2024/09/22
kaz
4
中国からの漢字の輸入から始まり、やがて主に「ひらがな」を交えた独自の文字・書風へと至り発展していく日本の書の歴史を「鑑賞」する人の視点から解説。何が書かれているか読めなくても、美術品として楽しむことができる。図書館の内容紹介は『二千年余に及ぶ歴史の積み重ねがあり、多様な展開を見せる日本の書。その長い歴史から、押さえておくべきエッセンスを凝縮してまとめる。名品の誉れの高い作品を掲載し、鑑賞のためのヒントを紹介する』。 2024/04/27
takakomama
3
図書館の講座「源氏物語と和歌文学 書とひらがなをめぐって」で、漢字の歴史を聞いて、復習。料紙装飾が綺麗です。作品を前にして「読まないでください」の言葉にほっとしました。2025/11/25
白山手賀
1
書の美しさが分かる年齢になってきた。2024/05/29