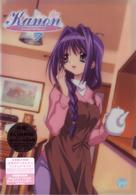- ホーム
- > 和書
- > 芸術
- > 絵画・作品集
- > 浮世絵・絵巻・日本画
出版社内容情報
広重の人生を辿りながら、広重作品の雪月花の余情を重んじた詩のような絵画世界の魅力や、近代を先取りしたともいえる新しい表現に迫る。改訂版では、広重の出世作「東海道五拾三次」(保永堂版)全五十五図を巻頭に新たに収録。
目次
序章 “出生”幕臣安藤家の嫡子として誕生(広重家系図;広重住居地図)
第1章 “揺籃期”広重デビュー、忍耐のとき(歌川派略系図;広重を育んだ師、歌川豊広の画風;猫背形美人画の第一人者、歌川国貞)
第2章 “躍進期”風景画で大輪を花を咲かせる(街道物ヒットの秘密;狩野派に触れる~広重を取り巻く環境 ほか)
第3章 “円熟期”旺盛な活動、人気絶頂のとき(名所絵師広重の往時の評判;見世物で消費された広重の絵「行燈絵」;広重はどこまで旅したのか;写生画法の吸収―円山四条派の学習)
第4章 “終焉”いまだ見ぬ景色をもとめて
著者等紹介
内藤正人[ナイトウマサト]
昭和38年、愛知県名古屋市生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科修了。博士(美学)。出光美術館主任学芸員を経て、慶應義塾大学教授、国際浮世絵学会常任理事。江戸時代の絵画史、とくに浮世絵・琳派などを研究テーマとする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
269
広重が火消同心の家に生まれ、自らも火消を務めていたのは知らなかった。絵は当初は副業だったとは。歌川豊広門下でデビューした頃は、やはり美人画から。画力の達者さは既に明らか。やがて、師の没後に風景画に主軸を移してゆくのだが、やはり広重の本領が発揮されるのはこちらだろう。見開きで紹介される「箱根」の偉容や「蒲原」の雪景色の情緒。そして、いずれの絵にも典型として人物がいる。広重の風景画はそれで初めて完結するのである。後、特筆すべきは広重ブルーか。後年のものはさらに構図に磨きがかかる。『名所江戸百景』などは⇒2025/01/19
mike
76
先日「動き出す浮世絵展」を見たが、そこで取り上げられていた広重。この人の風景画は好きだな。降りしきる雨、深々と降り積もった雪。いっぱいに広がる日本の風景とちょこんと描かれた民は何とも愛嬌がある。当時今で言うガイドブックの様な役割をして人々を楽しませたという。あのゴッホが心酔し広重作品をそっくりに模写していたとは全く知らなかった。2025/07/28
さばずし2487398
41
西洋画と違い、日本画は蒔絵のように空から全体を俯瞰して描かれているものが多いと聞いた事があるが広重や北斎も正に高い所から自然や町を描いているというのが人気の一つで貴重な歴史的資料でもあると思う。名所絵に確固たる芸術の粋を吹き込んだ広重作品。それでいて人物が一つ一つ細かい。ゴッホが参考にした技術など本当にどんな視覚をしていたか。江戸城詰めの武士の子で結構遅咲きの人物だったのも意外。掲載された「命」の絵が面白い。ベロ藍はもっと知りたくなった。後、確かに昔は歌川でなく安藤広重だったなあという事も思い出した。2024/08/15
びぃごろ
16
お茶漬けの付録で有名な『東海道五十三次』子どもの頃は古い絵の何が良いのか、さっぱりわからなかったよ。それでもあの時手にしていたから「あ、懐かしい」という郷愁を持て、詳細な解説を読めば「そういう背景なのか~」と絵に対する深みも増す。葛飾北斎・歌川国芳・歌川国貞らの作品に接した今では、違いも楽しめます。如何せんカードでは小さく豆粒みたいな人も拡大すると、その表情が様々で面白い。そして「東海道五十三次」は一つではなかった!行書、隷書、狂歌、人物、縦版、名物などなど。『木曽街道六十九次』『東都名所』の風景画もあり2025/08/16
takakomama
8
2007年刊を一部改変し、巻頭に16ページ「東海道 五拾三次之内 保永堂版」を増補した改訂版。「広重ぶるう」を読んだので、タイムリーでした。江戸時代、日本橋から京都まで歩いていくのは、遠い・・・2024/03/31