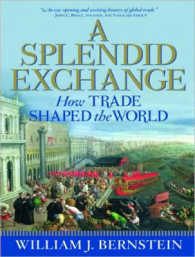内容説明
文明が衰退する原因は気候変動か、戦争か、疫病か?古代文明から20世紀のアメリカまで、土から歴史を見ることで社会に大変動を引き起こす土と人類の関係を解き明かす。
目次
第1章 泥に書かれた歴史
第2章 地球の皮膚
第3章 生命の川
第4章 帝国の墓場
第5章 食い物にされる植民地
第6章 西へ向かう鋤
第7章 砂塵の平原
第8章 ダーティ・ビジネス
第9章 成功した島、失敗した島
第10章 文明の寿命
著者等紹介
モントゴメリー,デイビッド[モントゴメリー,デイビッド][Montgomery,David R.]
ワシントン大学地球宇宙科学科・地形学研究グループ教授。地形の発達、および地形学的プロセスが生態系と人間社会に与える影響を主要な研究テーマとする。『土の文明史』で一般ノンフィクション部門2008年度ワシントン州図書賞を受賞
片岡夏実[カタオカナツミ]
1964年神奈川県生まれ。さまざまなジャンルの翻訳を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
76
人類が嘗て行った土への蛮行に嘆息する日々となった。嘗てではなく、今も…現在進行形の愚かさ。食べること、目先の食糧確保が喫緊とはいえ、国や支配者や経営者の愚昧さにうんざりする。(中略)本書について書きたいことはあまりに多い。付箋が何枚も。 愚かしさを強調し過ぎたようだが、マロリーが見た一九二〇年代のある中国は違った。2022/03/19
アナクマ
28
2章_ミミズと晩年のダーウィン「すべての腐葉土は何度もミミズの腸管を通ってきており、またこれからも何度も通るだろう」土壌生成速度。1mmできるのにイングランドでは4-8年。アイスランドは7年。アメリカは20年。10-100年で1ミリという研究も。◉「土壌生成と侵食のバランスのおかげで、生命は風化した岩石の薄い殻を頼りに生きてこられた」。土に感謝しよう。そして「資材ではなく、商品ではなく、価値ある相続財産として扱うこと」に文明の寿命がかかっている。服に土がついて〈汚れた〉なんて言ってる時代ではないと思うよ。2024/05/17
鯖
24
有史以来の、主として農業による土壌の浸食がもたらす文明の破壊を懇切丁寧に記していく本。でも農業がなければ文明自体がなかったんだよなあと思ってしまって、うなだれる。イースター島をはじめとしたポリネシアの島々に移り住んだポリネシア人による島の破壊の過程が切ない。それでも人は生きていかなきゃならなかったんだよなあとも思うし、これからどうするかでもあるよなあと。ミミズに感謝して生きようと思う。2020/01/19
六点
23
ぬこ田宅近所の山中にはとんでも無い所に結構離れた市町村の飛び地があったりする。理由はこの本で大きく取り上げられているが、田圃に鋤き込む植物を採取するための「山」であった。全地球的に見ると労働集約型の日本農業は例外であったのだなあと、しみじみ思う。江戸時代には近畿中央低地は土壌崩壊していたのだが。世界の文明や文化は、土壌の収奪を行い滅んでいったのである。現在でもサブサハラ世界でそれは起きつつある。有機農法というか、土壌を回復させる努力は細々としか行われない。歴史を学び未来を憂ゆるには良い本だ、2019/09/05
Francis
17
4年間積読。見過ごされがちな「土」。土は人間の命を支える農業にとっては最も重要なものであり、土をきちんと守らなければ人類文明も終わってしまう事が理解できた。土=土壌がミミズなどの自然の働きによりつくられるのには気の長い時間がかかるのに、土壌を保全することを考慮しない農法を選択するとあっという間に土壌は疲弊して最悪の場合砂漠化してしまう事、人類は「土」から搾り取る事で農作物を飛躍的に増加させ、人口増加を実現し、繁栄を築いたこと、しかし土壌の疲弊により文明が危機に陥りかねない事を著者はこの本で述べている。2024/09/19