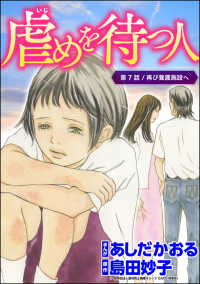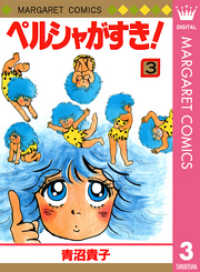感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
21
もう一つ面白かったのが、書院は日本人が経営する上海の大学だったわけですが、中華学生の学生寮が共産党細胞の活動拠点になったのは意外でした。中華学生部の梅電竜をリーダーに共産党細胞が生まれたが、中国官憲の手が届きにくい隠れみのになった。日本人も影響を受けて共産主義青年団組織ができて、30年には日本海軍陸戦隊、32年には日本軍人に反戦ビラをまいて逮捕。34年にはついに中華学生部を廃止。反戦活動家の日本人は戦後は共産党熊本県委員長に!へ~~~!初めて知った歴史です。31年まで院長は近衛文麿なんですよ!2021/05/19
小鈴
17
東亜同文書院って愛知大学の前進だったんだって!敗戦後、GHQからスパイ扱いされたためその名は名乗れず知を愛する大学ということで今の学名に。日清戦争後、日中貿易のビジネスマンを育てるため1901年に上海に誕生した学校で、その大きな特徴は清国、革命後は中華民国の全域の実態を把握するための徒歩の大旅行で、その記録を卒論としてまとめるもので、書院時代の50年間で700コース、都市部だけでなく中国全土、果ては東南アジアまで。すごい。20世紀前半の近世から近代化する姿を描いた記録は貴重だろう。→2021/05/19
kozawa
2
愛知大学のルーツとされる東亜同文書院/東亜同文書院大学(上海)について愛知大学名誉教授の著者が熱い物語として描こう、と。目的通りの本ではないでしょうか。面白く読ませて頂きました。2012/06/19
志村真幸
1
著者は愛知大学で学校史に携わり、東亜同文書院大学記念センター長を務めた人物。 本書は、東亜同文書院について、人物を中心にその歴史を回顧したもの。創立者や出資者たちの紹介、どのような教育が行われていたのか、卒業生へのインタビューなどから構成されている。 ただ、全体としては大学関係者/在校生向けの本であり、どこまで客観的な視点から描かれているか疑問が残る箇所も。 また、もともと『中日新聞』に連載されたものであり、エピソード中心なため、東亜同文書院についてきちんと知りたいひとは別の本を当たるべきだろう。2018/02/05