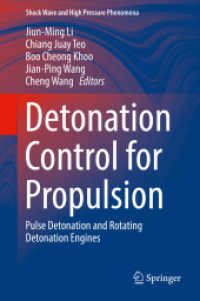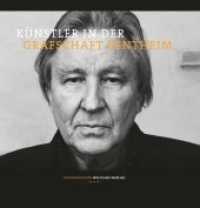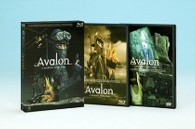内容説明
チェルノブイリ原発事故が近隣国ベラルーシの子どもたちにもたらした甲状腺ガンという大きな悲劇。菅谷昭医師は放射能に汚染された被災地で5年半にわたり医療支援をつづけた。高汚染地にある病院での手術。現地若手医師の育成。集団検診。家庭訪問。また、食料事情や治安問題。厳しい気候。楽しくもつらいロシア式宴会。さらには、子ども民族舞踊団との交流まで…。現地へ発つ日より帰国までの活動をつぶさに記録した「チェルノブイリの真実」。自分のため、社会のために考え、実践したひとりの日本人医師の「いのちの日記」。
著者等紹介
菅谷昭[スゲノヤアキラ]
1943年、長野県生まれ。信州大学医学部卒業。医学博士(甲状腺専門)。91年よりチェルノブイリ被災地の医療支援活動に参加する。95年末に信州大学医学部第二外科助教授を退官。翌年1月から2001年6月までベラルーシ共和国に単身滞在し、被爆者の治療にあたるなど、広く医療支援を行った。この活動によって、医療功労賞、吉川英治文化賞、フランシスコ・スカリナー勲章を受章
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆうゆう
3
ベラルーシで甲状腺がんの数々の執刀にあたり、原発事故の影響を見てきた筆者。大きな術創に後の心の影響を考える細やかさ、劣化した手術器具しかない、ケア用品も患者が準備する物資の少なさ、微妙なニュアンスを伝えきれない言葉の壁。帰国する頃には、悪性腫瘍がへってきたと希望を見てきた。大変な事も多かったでしょう。命を救うために奮闘された様子が淡々と綴られた行間からも伺える。いたずらに心配する訳でもないが、日本の、福島の子供たちの甲状腺が気になった。2013/11/16
hatagi59
2
医療再度から見たベラルーシの現状が分かったのが収穫。本書の内容に照らし合わせると、五年、十年後の福島、北関東、首都圏ホットスポットの子供達の甲状腺は大丈夫だろうか。。。 やはり忘れた頃に悲惨な結果が待ち構えている様な気がしてならない。 今回の原発事故を見て、現松本市長である菅谷さんはどんな気持ちでいるのだろうか? 本書の中でも度々『原発大国日本もチェルノブイリ事故は他人事ではない』と言及していた。 今後は菅谷さんの経験が非常に活きてくると思うので、医療面でのリーダーシップに期待したい。2011/08/19
更紗蝦
1
医療支援の記録だけでなく、ベラルーシの自然(特に、季節の移ろい)の描写がとても多いです。著者の菅谷氏が、いかにベラルーシという国を愛しているのかが伝わってきます。2012/09/24
-

- 和書
- ラーメンズつくるひとデコ