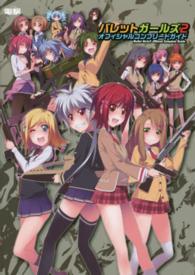内容説明
バルザック研究者のルースが、40歳になったいま、過去をふり返る。元女優の放恣な母、この母をいたわりながら愛人をもつ父。パリ留学時代の高名なフランス人教授との恋。成り行きまかせの結婚と夫の死。そして、ふたたび自分が人生の門出に立っていることを知る―。現実と文学が交錯する静かで繊細な心の風景、出会った人びとの織りなす人生のおかしみが、硬質な文章で浮かびあがる。戦後英国最高の女流作家と称されるブルックナーを世に知らしめたデビュー作。
著者等紹介
ブルックナー,アニータ[ブルックナー,アニータ][Brookner,Anita]
1928年、ロンドン生まれ。両親はポーランド系ユダヤ人。元コートールド美術研究所教授。18、9世紀フランスの美術史家。84年、『秋のホテル』でブッカー賞受賞。つづく『結婚式の写真』『英国の友人』で、現代イギリス最高の作家としての声価をゆるぎないものとする。『ある人生の門出』が81年刊行の処女作
小野寺健[オノデラタケシ]
1931年、横浜生まれ。東京大学大学院英文科修了。横浜市立大学名誉教授、日本大学・文化学院講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
NAO
62
自分たちのことしか考えない両親からほとんど構われることなく育った主人公がバルザックの研究者になり、40代になって自分の人生を回想する。今まで自分らしく生きていると思える時間などほとんどなかった主人公だが、それでも、父親の介護をしながらも少しずつ自分の時間を確保している今は、静かで平穏な心でいるようだ。その先には、穏やかで明るい日々が続いていくのだろう。2024/02/11
ののまる
10
これって今だったら子どもへの虐待じゃないの?と思うような両親のもとで青春を犠牲にし、最後も救いがない(たぶん)…ので、どうして「人生の門出」なのかわからない。ブルックナーのほぼ自伝、ということにも驚いた。ブルックナーはすでに研究者(教授職)にあったので、小説は神経症の治療のために書いた、というあとがきを読んで、ちょっと納得。でも、ところどころに、鋭い人間洞察があって何度もその行は読んでしまったり。2015/07/26
きりぱい
6
バルザックを研究するルースはあまりにもわびしい人生を送ってきたが、両親のせいで野暮ったく内気になってしまっても、自分の楽しみを諦めなくてはならなくなっても、心情に全く弱気でもない芯の部分を覗かせるのは救い。地味な性質をわきまえ過ぎて、ウジェニー・グランデ(恋を失いつつも超然としたバルザック作品のヒロイン)になりたいと願っていた頃からすると40歳にもなる今、残りの人生にも滅入るような、リセットを願いたいようなタイトルなのである。2010/08/23
Viola
4
ネグレクトの両親のもとで育ち、自立の機会を逸した女性研究者のルース。家は汚く両親の仲は冷え切っている。早く自立するよう友人に助言され、フランス行きのチャンスにやっと一人暮らしと小さなロマンスを手に入れるも、結局両親の元へ戻ってしまう。まるで、最近の日本でも問題になっている双依存の親子のようだが、ブルックナー自身の人生をなぞった小説で、心の整理のために書いたと知り愕然とする。内に向いた感受性と周囲の人間の執拗なほどの分析が、彼女の、悪意を感じるほど鋭い人物描写につながっている気がする。『門出』は意味深。2015/11/17
よし
3
何とも気分が滅入るような物語。主人公のルースにとって、「人生の門出」とは、子どもの時から続いていた父母の犠牲の繰り返しに過ぎないのかも。以前読むのを途中で投げ出した「谷間のゆり」の主人公とシンクロしていた。これはブルックナーの自伝的小説とあるのも、わかる気がしてきた。パリ時代の恋人との生活に、ルースの短い「青春」もあり、希望もあった。「男のことは、目の前にいられては考えられない。いなくてこそ、ロマンティックな愛はふくらむのだ。」寂しい人生を必死に立ち向かうルースの健気さに共感を覚えてしまう。2017/08/21