出版社内容情報
子ども・子育て支援制度の導入や教育要領や保育指針の改訂(定)など、現在、日本の保育現場には変化の波が押し寄せています。このような時期だからこそ、「子どものための保育を推進したい」という思いを込めて本書を著すことにしました。
福祉国家であり、子どもの権利の先進国でもあるスウェーデンでは、21世紀を迎える直前に待機児童問題を克服し、希望するすべての子どもに保育を受ける権利を保障する制度を確立しています。そして現在は、その質の向上に力を注いでいます。
本書では、質の向上をめざしてスウェーデンが導入した「教育的ドキュメンテーション」を取り上げました。これは、イタリアのレッジョ・エミリア市の協力を得て、スウェーデンが行った実践的研究に基づいて開発されたツールです。子どもの言葉、作品、写真、動画などを用いて、保育のプロセスを可視化した「ドキュメンテーション(記録文書)」を資料として、保育者同士、または保育者と子どもが一緒に活動を振り返り、省察して、次の展開を考えることを「教育的ドキュメンテーション」と言います。
第?部では、スウェーデンの保育者や研究者が、プロジェクト活動の実践例を紹介しながら「教育的ドキュメンテーション」について解説しています。続く第?部では、日本の三つの保育園で試験的にドキュメンテーションを活用した事例を紹介しています。最初、保育者たちは子どもの興味や関心を探り、それを「ドキュメンテーション」にするところからはじめました。すると、子どもたちの賢さ、感性の豊かさ、発想のユニークさ、友だちへの思いやりや連帯感など、「素敵なところ」がよく見えるようになったのです。「ドキュメンテーション」を活用することによって生まれる「子どもから出発する保育実践」の推進力、まずは本書で確認してください。(しらいし・よしえ)
白石淑江[シライシヨシエ]
著・文・その他
内容説明
子どもの思いや考えから出発する保育実践。見つけよう!子どもたちの素晴らしさ。「子どもの権利」の先進国発。
目次
スウェーデンの保育と教育的ドキュメンテーション
第1部 スウェーデンにおける教育的ドキュメンテーション(スウェーデンの就学前教育における子どもの参加;教育的ドキュメンテーションの実践;アトリエリスタの視点とプロジェクト活動;保育者にとっての教育的ドキュメンテーション;「森のムッレ教育」と教育的ドキュメンテーション)
第2部 日本の保育園での教育的ドキュメンテーションの試み(スウェーデン人から見た日本の保育;試行的実践から見えてきたこと―新しい目で子どもや保育を見るために;教育的ドキュメンテーションで保育が変わる;ドキュメンテーションを活かした創作劇の取り組み)
著者等紹介
白石淑江[シライシヨシエ]
愛知淑徳大学福祉貢献学部子ども福祉専攻教授。大学院修士課程修了後、短期大学保育科に勤務。その後、大学などの非常勤講師を経て、1991年から同朋大学社会福祉学部に勤め、2010年より現職。大学において保育士養成に携わるとともに、児童虐待の発生予防を視野に入れた地域の子育て支援活動にも関わっている。2000年にストックホルム教育大学(現・ストクホルム大学)に短期留学して以来、スウェーデンの研究者や保育者との交流を深めながら、この国の制度や保育実践について研究している。また、勤務校の学生のスウェーデン保育研修も行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
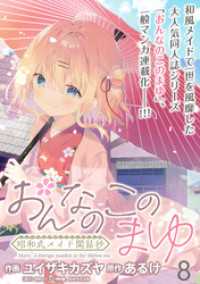
- 電子書籍
- おんなのこのまゆ 昭和式メイド閑話抄 …
-
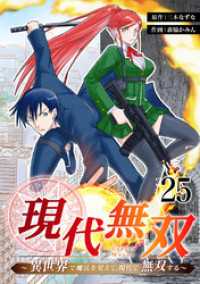
- 電子書籍
- 現代無双~異世界で魔法を覚えて、現代で…
-

- 電子書籍
- 優しい死神の飼い方 第05話【単話版】…
-
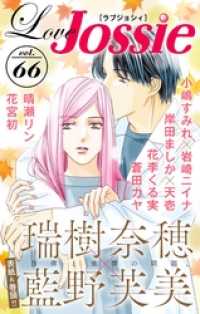
- 電子書籍
- Love Jossie Vol.66 …





