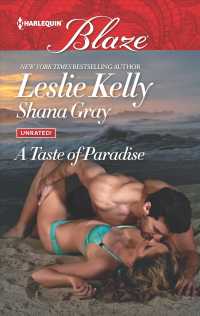出版社内容情報
綿毛で上空1000mを浮遊するタネ、時速200km超で実から噴射されるタネ…タネたちの生き残り戦略を美しい細密画と楽しむ。
内容説明
植物の生き残り戦略とは、つまるところ、「タネをいかに拡散するか」である。植物は移動できないが、タネは移動できる。綿毛で上空1000mを浮遊するタネ、時速200km超で実から噴射されるタネ、数千年後でも発芽可能なタネ…。台所で捨てられるスイカやリンゴのタネにも、子孫繁栄のための秘密がある。さあ、タネの不思議な世界をのぞいてみよう。美しい細密画、多数収載。
目次
風で旅するタネの話
動物に運ばれるタネの話
まかれるタネの話
まかれないタネの話
時を超えるタネの話
食べられるタネの話
豆と呼ばれるタネの話
芽生えで食べられるタネの話
油を取るタネの話
果物のタネの話
野菜のタネの話
植物にとって種子とは何か?
すごい種子
著者等紹介
稲垣栄洋[イナガキヒデヒロ]
1968年静岡県生まれ。静岡大学大学院農学研究科教授。農学博士。専門は雑草生態学。岡山大学大学院農学研究科修了後、農林水産省に入省、静岡県農林技術研究所上席研究員などを経て、現職
西本眞理子[ニシモトマリコ]
1955年兵庫県生まれ。日本植物画倶楽部会員。神戸大学教育学研究科修士課程修了(美術科教育)。兵庫県内の小中学校教諭を経て、現在は公民館、植物園等で植物画を教える。植物画入門書、塗り絵、スクラッチアートなど、著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
Aya Murakami
へくとぱすかる
saga
ホークス
-
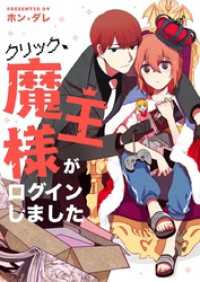
- 電子書籍
- クリック、魔王様がログインしました【タ…