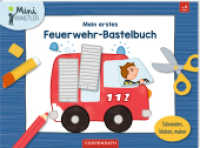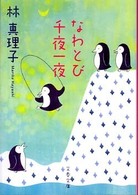出版社内容情報
実は格差がひどいドイツ。もはや崩壊寸前の日本。
ドイツ在住35年超の著者が綴る、介護・医療制度の国際比較ルポ。
世界一の高齢国ニッポンの老後は、介護も医療も、実はあまりに恵まれていた!
将来の世代が心配になるほどに――。
欧州の高齢国ドイツが苦しむ介護と医療の問題を紹介し、日本と徹底比較。
在独35年超の著者が日本での両親の入居施設探しに奔走した経験などを交えつつ綴る、介護・医療の国際比較ルポ。
【内容より】
◎ドイツの老人ホームは高額で庶民は入れない
◎「福祉国家ドイツ」の驚くべき医療格差
◎人口あたりの医師数、日本はドイツの6割以下
◎ドイツの介護職は外国人の出稼ぎ仕事と化した
◎延命治療をしないほうが、苦しまずに死ねる。
まえがき――快適な老後を求めると若者が苦しむ
序 父と母と老人ホームと私
・ある日突然、父はまったく立てなくなった
・職員の態度が気に入らず、父はハンストに突入
・母による老老介護の破綻もまた、突然訪れた
・「親の面倒は誰が見るのか?」娘として考えること
第1章 人はいかにして介護士になり、介護士を続けるか
・特養と有料老人ホームの違い
・両親とも施設に入って、初めて見た介護の世界
・介護の世界を見て、私の死への感覚は変わった
・老人ホームを見てわかった人手不足解消策の空理空論
・ドイツで「介護」と「看護」の資格が統合された理由
第2章 介護の費用の日独比較
・ドイツも介護をめぐる家族の事情は日本と同じ
・ドイツも日本も介護保険料は値上がりしている
・介護保険料の値上げが政治課題となったドイツ
・日本の介護保険の仕組みはどうなっているか
・ドイツでは要介護になったらいくら支払われるか
・要介護認定に若い「ケアマネ」が厳格な理由
・ドイツでは老人ホームに入るといくらかかるか
第3章 ドイツでは庶民は老人ホームに入れない
・驚くほど贅沢なドイツの非営利老人ホーム
・高級ホテルの一室のように清掃が行き届いていた
・ドイツでは非営利老人ホームでも料金は高額
・ドイツでは老人ホームは個室しか認められなくなる
・ドイツでは介護費用を最後は子供に負担させる
第4章 医療格差社会ドイツと患者天国の日本
・プライベート保険と法的強制保険というドイツの医療格差
・日本の医療保険に似ているドイツの法的強制医療保険制度
・若いうちは割安なドイツのプライベート医療保険制度
・医師への金払いがよくない法的強制保険制度
・プライベート保険は高齢になると保険料が上がる
・医療保険制度が2つあることの弊害は大きい
・子供と若者に手厚いドイツの医療保険制度
・日本の医療保険制度はどうなっているのか
・日本の患者は恵まれすぎ。医療従事者へしわ寄せが…
第5章 北欧の福祉は本当に理想的か?
・非民営路線の北欧モデルの医療費収支
・デンマークの在宅高スペック介護政策
・ドイツも日本もデンマークの真似はできない
・北欧も高福祉の維持は困難。日本は学びつつ別の道を
第6章 医療・介護に市場原理を持ち込んだドイツ
・ドイツでは90年代に病院も老人ホームも市場原理に
・病院の利益向上のため必要ない手術が行われている
・外国の格安老人ホーム、優良投資先としての老人ホーム
・ドイツならではの選択肢「在宅介護+私設ヘルパー雇用」
・「24時間自宅介護」の勤務形態はどうなっているか
・重労働で孤独。出稼ぎ介護士の立場は弱い
・自宅介護を推進したいドイツ政府の錬金術的解決策
・自宅介護を機能させる夢のような方法はない
・日本は介護制度で離職を防ごうとしているが…
第7章 認知症を受け入れつつあきらめない
・「もう○○できない人」がどんどん増えていく日本
・呆けてしまった父とも話すのは楽しかった
・父は私のことだけを忘れてしまっていた
・年齢と生年月日が思い出せず、不動産取引が中止に
・医師の認知症テストで張り切った父
・日本の「認知症グループホーム」とはどういうものか
・認知症高齢者と地域との交流「認知症カフェ」
・手に負えなかった認知症患者への対応も進歩している
第8章 日独の介護士不足はどれほど深刻か
・老人虐待の証拠ビデオには映らない「真実」がある
・性善説か性悪説か? 日独の違い
・老人ホームでの虐待や殺人の背景となる労働環境
・介護の人員は一体、何人足りないのか?
・ドイツの老人ホームの劣悪な労働環境
・ドイツじゅうを揺るがした介護学生のひとこと
・外国人介護士の流入で賃金の上がらないドイツ
・外国人介護士の受け入れをはばむ日本の資格制度
・介護ロボットによる劇的改善はしばらく無理?
第9章 介護と医療の待遇・職場環境改善闘争
・東欧の労働者をドイツはどのように受け入れてきたか
・低賃金の仕事を外国人にさせてきたドイツ
・日本の介護士の給与は改善されつつある
・ついに起きたドイツの病院でのストライキ
・これまで看護師・介護士はストを避けてきた
・老人ホームの介護士にはストによる闘争が不可能
・日本の介護は「若者の善意」に甘えている?
・人手不足の末にある医療崩壊・介護崩壊
第10章 延命治療をするか、否か?
・麻生大臣発言の報道に見る終末医療議論のすれ違い
・なかば強制的に延命治療が行われてきた日本
・延命治療が患者を苦しめることがあるのはなぜか
・延命治療せずに在宅で迎える「平穏死」の実際
・財政破綻の影響で「平穏死」が実現した夕張市
・私の父が最後に固形物を食べた瞬間
・父の延命治療を望む私に、弟が返した言葉
・延命治療を受けなかった父の平穏な死
・延命治療をすべきだったか? 遺された者の迷い
・「北欧には寝たきり老人がいない」の本当の意味
第11章 社会保障制度に負担かけず長生きしよう
・「介護されたくない!」と思う人、思わない人
・介護される自分を許容する人は介護しやすい
・理想の死に方「ピンピンコロリ」のいろいろ
・「寿命マイナス健康寿命=ゼロ」なら介護もゼロ
・要介護度を下げるのが難しい理由
・元気な高齢者を増やし活用するプロジェクト
・増加する活動的高齢者をよりよく導く施策とは
・平均寿命と健康寿命の差は10年弱
・やるべき社会保障改革を妨害する人たち
・「保険」から「福祉」への転換で若者の負担減を
・健康保険組合は高齢者医療で赤字続き
・年をとっても若者を優先する気持ちを持ちたい
あとがき――皆保険を実現した知恵と実行力を再び!
川口 マーン 惠美[カワグチ マーン エミ]
著・文・その他
内容説明
世界一の高齢国ニッポンの老後は、介護も医療も、実はあまりに恵まれていた!将来の世代が心配になるほどに―。欧州の高齢国ドイツが苦しむ介護と医療の問題を紹介し、日本と徹底比較。在独35年超の著者が、日本で両親の入居施設探しに奔走した体験などを交えつつ綴る、介護・医療制度の国際比較ルポ。
目次
序 父と母と老人ホームと私
第1章 人はいかにして介護士になり、介護士を続けるか
第2章 介護の費用の日独比較
第3章 ドイツでは庶民は老人ホームに入れない
第4章 医療格差社会ドイツと患者天国の日本
第5章 北欧の福祉は本当に理想的か?
第6章 医療・介護に市場原理を持ち込んだドイツ
第7章 認知症を受け入れつつあきらめない
第8章 日独の介護士不足はどれほど深刻か
第9章 介護と医療の待遇・職場環境改善闘争
第10章 延命治療をするか、否か?
第11章 社会保障制度に負担をかけず長生きしよう
著者等紹介
川口マーン惠美[カワグチマーンエミ]
作家。ドイツ在住。日本大学芸術学部音楽学科ピアノ科卒業。シュトゥットガルト国立音楽大学院ピアノ科修了。『ドイツの脱原発がよくわかる本 日本が見習ってはいけない理由』(草思社)が第36回エネルギーフォーラム賞の普及啓発賞、『復興の日本人論 誰も書かなかった福島』(グッドブックス)が第38回同賞の特別賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
ごへいもち
hk
mazda
のるくん
-
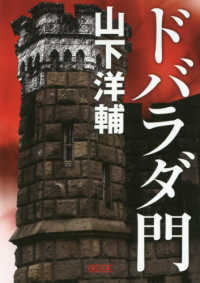
- 和書
- ドバラダ門 朝日文庫