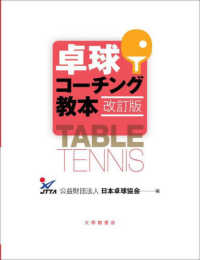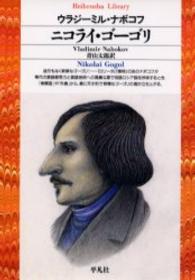内容説明
前作『徳川慶喜家の子ども部屋』で幼時の思い出と戦前の華族の生活を活き活きと描き、好評を博した著者の後半生を回想した続編。昭和15年、越後高田藩の元譜代大名、榊原家の第16代当主、榊原政春氏に嫁した著者は戦後の華族制度の崩壊と厳しい現実のなかでも誇りを失わずたくましく生きていく。現代において、古い家を守って生きること、伝統を生きるということの難しさと喜びを率直につづる。
目次
第1章 戦中戦後のころ
第2章 榊原家
第3章 家族の肖像
第4章 昭和某日
第5章 暮らし歳時記
第6章 行く日来る日
著者等紹介
榊原喜佐子[サカキバラキサコ]
大正10年(1921)、東京小石川第六天町の徳川慶喜家に一男四女の三女として生まれる。父は慶久、母は有栖川宮家から嫁した実枝子、姉は現高松宮妃殿下、喜久子様である。女子学習院を経て、昭和15年、越後高田の元譜代大名榊原家当主、榊原政春氏と結婚。現在、東京都杉並区在住
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜の女王
19
徳川公爵家から榊原子爵家へ嫁ぎ、さらに戦後の華族制度廃止の時代へと、波乱の後半生の話。榊原家の話や戦中戦後の苦労話は興味深かった。太宰治の『斜陽族』をバカバカしい!とバッサリ切る気概は小気味いい。確かに、その教養と人脈があれば普通の庶民より有利に生き残れるはず。全体を通して家への誇りと矜持が感じられた。昭和2年に家督を継いだご主人が旧領の新潟高田にお国入りしたとき、後見人の荒井賢太郎氏(枢密院顧問)に向かって、「殿様の隣に座ってるのは足軽だ!」と言った人が居たとか。お江戸がまだ残ってたんだね(笑)2018/09/29
mawaji
4
「徳川慶喜家の子ども部屋」でのお姫さまの暮らしから一転して本書は元譜代大名当主に嫁した後、戦後の華族制度崩壊の中を逞しく生きる著者の回顧録でした。「ほんとうの華族はどういうものか、まったくご存じない」と太宰治の「斜陽」に物申すくだりや、敬語や礼儀ある言葉に対する思い入れと若い人たちに対する辛口の物言いは皇室の藩屏たりうる華族としての矜持を貫いて生きてきたからこその言葉なのでしょう。「おふろ召す?」「すぐ召しあがる?』などという言葉づかいが日常的に交わされる暮らしはとても穏やかな日々のように感じられました。2022/11/12
たく
1
前作ほど面白くはない。2015/04/28
けいちか
1
『徳川慶喜家の子ども部屋』の続編。「徳川慶喜家の子ども部屋」の作者による、結婚後の生活に関しての話。本人が書き溜めた短歌が披露されているが、私は短歌が苦手で飛ばし読みしました。すいません。作者は世が世なら徳川のお姫様であったはずの女性で、明治になってから越後高田藩の榊原家の当主と結婚し、3人の子どもを生み、育てた。普通の生活がこちらから見ると違う世界で、こんな世界もあるのだなと興味深かった。2007/02/09
のんき
1
『徳川慶喜家の子ども部屋』の続編。素直というか天然というか野生児というか、そんな形容はお姫様にふさわしくないけど、でもそういう人柄の方なんだと思った。飾らないしなやかさが心地よく、読むのが楽しかった。2009/06/12