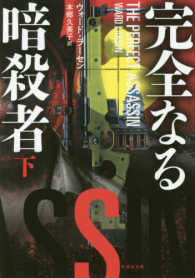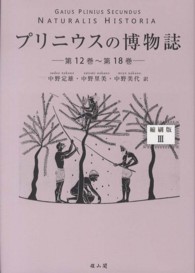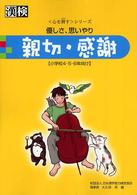内容説明
世界最先鋭のクリエイティブ集団・Googleは、夢のように充実した職場環境をそなえ、その恩恵に授かる社員の採用試験では、自由回答の難問で知的能力を試す。ありきたりでない質問をしてこそ、どの企業も求めていながら、測り方を知らない資質=「革新を生む能力」をはかれるのだ。Google元面接官は言う―「面接の目的は、どこでアイデアがつきるかを見ることだ」。
目次
1 グーグルプレックスは激戦の場―超人気企業に採用されるには
2 創造力というカルト―人事の歴史、あるいはなぜ面接官は悪乗りするのか
3 ひっかかった、面食らった!―大不況はいかにして奇問珍問を流行らせたか
4 グーグルの採用システム―一三〇人の応募者からどうやって一人を選ぶのか
5 エンジニアという人種 彼らのように考えないためには―単純に考えることの大切さ
6 クセもの問題対策の手引き―面接官の隠された意図を見抜く
7 ホワイトボード利用術―図を用いて解答するコツ
8 フェルミ博士と地球外生物―一六秒以下で答えを出すには
9 割れない卵―「どのようにして」を問う問題
10 自分の頭の重さを測る―絶体絶命のときはどうするか
解答編
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヨクト
14
著者は「ビル・ゲイツの面接試験」という本を書いており、形式的にはほとんど同じで、問題編と解答編で構成。違う点は、マイクロソフトとグーグルが求める解答の比較が載せてある点。グーグルの方がトリッキーというか柔軟性を備え解答を求める傾向かな。偉そうに言っておりますが、ぼくは解答までほとんどたどりつけなかったんですけどね。ミキサー問題、砂時計問題、娘の年齢問題、割れない卵問題、末尾の0問題あたりが面白かった。そして「最も美しい方程式」についても興味が湧いた。2014/12/21
kubottar
8
コンピュータサイエンスの博士号持ちの人よりも知識のない人の方が優れたやり方を見つける場合もある。なぜなら、数学を極めた人は数学教の信者と化すからだ。とはいえ、たまたまいいやり方を思いついた全く知識のない人が会社に入ってコンスタントにいい仕事ができるかといわれたら、それは無理だろう。グーグル入社試験を見ながら思ったが、どうやって論理的思考能力を深めていくか、そのやり方は人によって違うだろう。少なくとも自分にとってはフェルミ推定みたいな問題はやりたくないと感じた。そのひっくり返し方ばかり考える。2012/09/03
ぱぱちん
1
本当にGoogleがこのような問題を面接で出しているかは不明だが、いきなり何の準備もなくてこの手の質問を受けたら面食らうだろう。まぁ面接する前に書類審査である程度の学力と職歴はわかるから、今後どの程度実際に会社の力になれるかを測る意味では有効かもしれない。頭の体操的な問題から、フェルミ思考、数学の教養がないと解けないものなど、かなりの分量が紹介されていた。Microsoftの社風との違いがくすっと笑えたが確かにそんな気もする。答えよりも解き方を見ることもあるので面接では最後まであきらめないことが大事。2021/09/10
Takayuki Higashi
1
こういうパズル・クイズだけで優秀な人材を採用できるかどうかは意見が分かれるが、仕事には、捉えどころのない問題を具体的な物事に落とし込む作業があるのは事実で個人的には面白く読めました。(ただ、問題と解答が別構成で読みにくい)2015/04/13
egu
1
実際問題これを即座に解説出来るだけあって世界のgoogleの博学さや論理的思考力更にユーモアの高さに只々驚かされるばかりだ。こんなにも手の込んだ面接や問題を潜り抜けても採用の確率は高くないということはまだまだ採用面接の改善点は沢山あるんだと感じる。 日本の企業がベンチャー界で後塵を拝する理由がなんとなく分かった気がする。2014/02/05