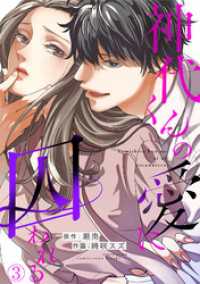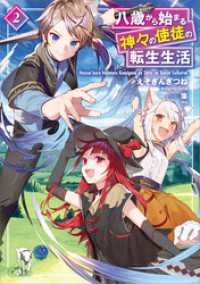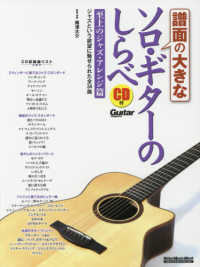出版社内容情報
南仏洞窟での演奏体験から、四国のサヌカイトまで、最新の音響考古学や認知考古学の成果を踏まえ、古代音楽の豊穣さを甦らせる。
内容説明
先史時代の壁画洞窟、それは絵画芸術の揺籃にとどまらず、人類のイマジネーションをよびさます音響装置だった―。南仏洞窟での貴重な演奏体験から、著者の故郷・四国のサヌカイトの謎解きまで。最新の音響考古学や認知考古学の知見を踏まえ、古代音楽の豊饒な世界を甦らせる探究の成果。
目次
第1章 レ・トロア・フレール洞窟探訪―小さな魔法使いの謎
第2章 壁画と洞窟の音―音響考古学者ミシェル・ドーヴォワの挑戦
第3章 楽器の起源―骨の楽器をめぐって
第4章 壁画洞窟での演奏
第5章 ブッシュマンの岩絵とシャーマニズム
第6章 芸術のビッグバン―認知考古学者スティーヴン・ミズンの音楽起源説
第7章 サヌカイト―石を巡る不思議の旅
著者等紹介
土取利行[ツチトリトシユキ]
1950年香川県生まれ。音楽家、パーカッショニスト。70年代前衛ジャズの天才ドラマーとして頭角を現し、近藤等則、坂本龍一、阿部薫、ジャズ評論家の間章らと音楽活動を展開する。渡米して伝説のドラマー、ミルフォード・グレイヴスと出会い、音楽の根源的な探求に導かれる。スティーヴ・レイシー、デレク・ベイリーら海外の多くの即興演奏家と共演。70年代よりピーター・ブルック国際劇団で演奏家、音楽監督として「ユビュ王」「鳥のことば」「マハーバーラタ」「テンペスト」「ハムレット」最新作「ティエルノ・ボカール」などを手掛け世界の注目を集めている。一方、音楽の根源を求めてアフリカ、アジアなどをはじめ、世界各地で民族音楽の調査研究を続ける。87年より桃山晴衣とともに岐阜県郡上八幡に活動の拠点「立光学舎」を設立、地元の人たちとの文化活動にも力を注ぐ。また日本では大野一雄・慶人、田中泯、山田せつ子など舞踏家とのコラボレーションをはじめ、五木寛之戯曲「蓮如」の音楽制作、呉鼓の打楽器集団で演奏を繰り広げるなど多岐にわたる活動を展開する。縄文鼓はソロコンサートのほか、メキシコの古代楽器集団トリブやアイヌの歌手安東ウメ子とのジョイントを行ない、パリのシャトレ劇場でも初の海外コンサートを行った。近年は旧石器時代の音楽研究に向かい、フランスの壁画洞窟での演奏がNHK番組「人類最古・洞窟壁画の謎」で放映された(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。