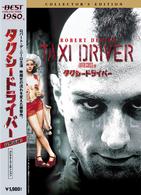内容説明
東インドネシアに住むエンデ人の世界―誰と結婚し、何を交換し、どんな集団を作るか―を、理論人類学の光の下に生き生きと照らし出す。犬(事実)好きのための民族誌構築事始め。
目次
はじめに 犬好き派の人類学と猫好き派の人類学
1 交換の人類学―交換、関係、集団(けちの経済学から気前のよさの経済学へ;クラと大地と祖先の墓と;市場と墓;王様の倫理;人はなぜ贈りものをするのか;敵の敵が味方であるわけ;結婚相手の選び方)
2 エンデの民族誌―集団、関係、交換(ズパドリ村で;キョウダイとシンセキ;いろいろなキョウダイ;いろいろなシンセキ;婚資の与え方ともらい方)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
★★★★★
9
犬好きは民族誌好きで、猫好きは理論好きだとE=Pが言ったらしい。私は猫派だけど民族誌好きなのよね。それはさておき。本書は交換をめぐる民族誌的事実を通じて、関係と属性の弁証法を解説する本です。入門と銘打ってあるだけあって確かに読みやすいんだけど、中身は緻密に計算された幾何学的構造を取っていて、非常に奥深いです。2010/10/16
なつきネコ@着物ネコ
6
大学のテキストの一つ。まずは文化人類学からはじめてみた。今までならこんな世界があるのかと関心して終わりだが理解しないといけない。交換は取引交換、もう一つの交換、貢賜交換に分類される。ここで取引交換は経済活動で、もう一つの交換は人間関係構築する事。上下関係に対しての貢賜交換。この関係で思うのは平成に入り日本で減ったのほ経済活動以外の交換。お歳暮や、奢りなども、もう一つの交換と貢賜交換だな。自分が人間関係が苦手な理由が理解できた。政治家の汚職が蔓延るのも貢賜交換のような上下関係の威厳の消滅にもあるのかも。2020/05/09
AKO
4
交換の起源は古く、石器時代から石や貝などを交換していたという。人類の歴史とは交換の歴史なのだ。近代経済学の父アダム・スミスが言っているように人間とは取引をする唯一の動物。著者がいうに、交換は三種類に分類できるらしい。親しい者同士で行われる『贈り物交換』経済の基礎『取引交換』献上の『貢賜交換』の三種類。昔は贈り物交換で小規模な村は回っていたが、現代社会は人々が疎遠になり、取引交換がほとんどだ。お金さえあれば生きていけるようになったが、心は荒む一方。思い出したときに、お世話になった人、親しい人に贈り物を――。2021/07/19
クロスリバーゴリラ
0
ひたすら交換と関係に絞って話を進めていき、なるほどぉという場面も多かった。後半部のエンデでのフィールドワークに関してはカッエウンブやウェタアネなど現地の語彙がたくさんでてくるので読み進めるのに多少難儀した。 第三講義の内容が個人的には新鮮だった。2025/03/29