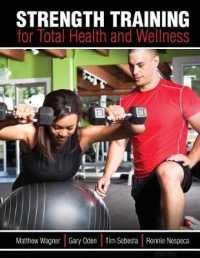内容説明
「和食」は本当に健康食か?ダイエットは糖質か脂質か?栄養健康情報はどこでゆがむか?「根拠に基づく栄養学」がその問いに答えます。
目次
第1章 こんなにややこしい?!あぶらと脂質異常症の関係
第2章 こんなに大問題?!食塩と高血圧
第3章 不思議がいっぱい!肥満問題
第4章 呑んべえ必読!お酒、なにをどれくらい、どのように飲むか
第5章 究極の健康食?地中海食から糖尿病管理まで
第6章 あなた自身が試される!「栄養健康リテラシー」の時代
著者等紹介
佐々木敏[ササキサトシ]
東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野教授。女子栄養大学客員教授。京都大学工学部、大阪大学医学部卒業後、大阪大学大学院・ルーベン大学大学院博士課程修了。医師、医学博士。国立がんセンター研究所支所、国立健康・栄養研究所などを経て現職。いち早く「EBN」を提唱し、日本人が健康を維持するために摂取すべき栄養素とその量を示したガイドライン「食事摂取基準」(厚生労働省)策定に貢献。日本の栄養疫学研究において、中心的役割を担い続ける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-
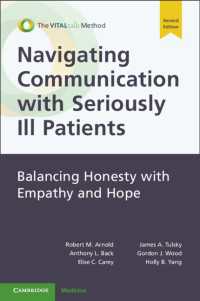
- 洋書電子書籍
- Navigating Communic…
-
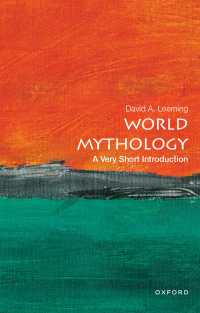
- 洋書電子書籍
-
VSI世界神話
World My…
-
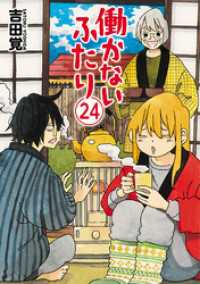
- 電子書籍
- 働かないふたり 24巻 バンチコミックス
-
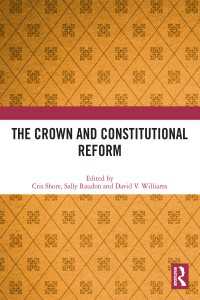
- 洋書電子書籍
- The Crown and Const…