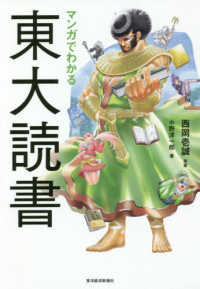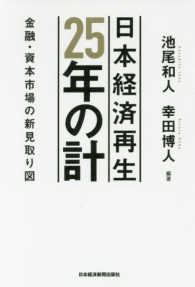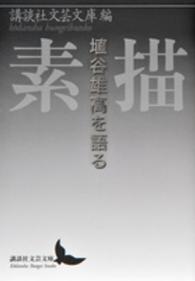出版社内容情報
国民の外交的センスが求められている!本書は、現役外交官でありながら東北大学に出向して教鞭をとる著者が、実践から導かれた理論的枠組みを提供し、外交という営みの全体像と本質をわかりやすく説き起こす。
内容説明
国民の外交センスが求められている!「外交の理論と実践」を、知識としてではなく「ものの見方、考え方」として、わかりやすく解く。
目次
序章 外交という営み―目的と座標軸を持つ
第1章 インテリジェンス―判断と行動に役立てる
第2章 政策のデザイン―理想に形を与える
第3章 交渉のアート―相手と自国を説得する
第4章 バイとマルチ―効果的に組み合わせる
第5章 繁栄―安心して働ける環境を創る
第6章 安全保障―リスクを回避し、平和を創る
第7章 外交と世論―信頼関係を築く
終章 限界と可能性―新古典外交をデザインする
著者等紹介
柳淳[ヤナギジュン]
1988年、東京大学法学部を3年で中退し外務省入省。オックスフォード大学から学士号・修士号(哲学・政治・経済)取得。本省では北東アジア、南東アジア、APEC、インテリジェンス、パブリックディプロマシー等を担当。海外では、在ナイジェリア、在オーストラリア、在ロシア、在カナダの日本大使館に勤務。国際科学協力室長、西欧課長を経て2012年9月より東北大学教授に退職出向中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ceskepivo
7
外交実務家の著者がこれまでの経験を踏まえ、外交実務家の政策立案・実施の際の物事の考え方を丁寧に説明している。「常に、種を蒔き、水をやり、収穫を刈り続ける。外交はその繰り返しである」。外交は国益実現の手段であるが、究極には人の営みであるので、この指摘は理解できる。他方、「日本の繁栄と安全保障にとって、外交よりも教育の方が大事」と言い切るのは、いかがなものか。外交も教育も大事であり、外交が人の営みである以上、教育は外交を支える重要な要素というのが正しい。2015/08/22
省事
2
実務家教員を経験した外務省員による外交論。定評ある外交論に、著者が外交の現場で経験的に得た「ものの見方、考え方」をブレンドする形で作られている。理論的にどうあるべきか、一方で現実にどういうことが起こりがちだったか、といった塩梅で記述のバランスがよいのが特色。章構成も情報収集と情勢判断、政策の立案、交渉、各政策分野の論点などよく練られている。現在の国際報道や過去の歴史を見る時にも「こういうことがあるんだろうな」という補助線を引くのに役立つ本である。またプロとしての「職業外交官」の意義の強調が印象に残る。2018/09/09
Sho
1
言われてみれば当然のように聞こえるが、いざ説明せよといってもできない外交の基本が体系的に説明されている。あくまで外交は国益の為であり、小学校の道徳のような綺麗事の世界ではない。それでも時として意思決定者の道義・信条に国家の判断が影響を受けるというのも面白いところ。またメディアに振り回されず冷静に日本の外交環境を理解できているか大いに反省。2020/09/01
わび
1
著者が外務省から出向した東北大学での講義を基にした外交論。と言っても特定の地域や案件について述べたものや単なる体験談ではなく、あくまで著者が身につけた外交官の考え方、外交の作法を紹介するものとなっている。しかしこれがかなり面白い。理論や歴史といった堅い話と実際の業務のプロセス、個人の経験談が適度に混ぜ合わされ、著者が設定した目的にはかなり高い水準で応えている。インテリジェンスや交渉のアートの章は交渉事全般に応用できるし、外交交渉のニュースの分析や歴史研究の補助線ともなる、色々と使い道のある一冊。2019/09/13
ヤマーナ
1
★★★★☆ 民主主義である以上我々一般国民にも外交的センスが求められているよなー。そして、より多くの国民に外交的資質が備われば、世界における日本の存在感は増すことでしょう。そんな一歩を踏み出すのに最適な本。2018/02/17