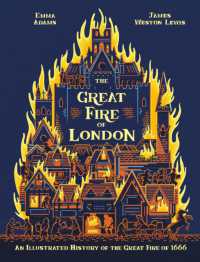内容説明
愛媛県松山市の郊外、道後平野をみわたす丘陵上で未盗掘の古墳がみつかった。一四〇〇年あまりの時をへて慎重に開けられた石室内には「記紀」が記す神代の説話、イザナキの黄泉の国訪問譚を彷彿とさせる光景がひろがっていたのである。
目次
第1章 黄泉の国との遭遇(葉佐池古墳の発見;未盗掘の石室)
第2章 黄泉の国の光景(一号石室の調査;墳丘の調査;二号石室の調査)
第3章 葬送儀礼をさぐる(「殯」とハエ;「ヨモツヘグイ」と「コトドワタシ」;玄室内の謎の儀礼;墳丘での祭祀)
第4章 被葬者像をさぐる(葬られたのは首長?;考古学からみた道後平野;窯業生産地のリーダー)
第5章 地域の中の葉佐池古墳(史跡指定;葉佐池古墳のこれから)
著者等紹介
栗田茂敏[クリタシゲトシ]
1953年愛媛県生まれ。1978年京都大学文学部中退後、松山市教育委員会、財団法人松山市生涯学習振興財団を経て、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団埋蔵文化財センターに発掘調査担当として勤務。2015年現在、同センター専門嘱託員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
月をみるもの
13
この「遺跡を学ぶ」シリーズは、文章は言うに及ばず、写真や図表の豊富さと美しさが素晴らしい。表紙になってる図16を見たら、腐乱しつつあるイザナミの姿を見てしまったイザナギの気持ちになれること請け合い。追葬の時に、前の遺体をはじっこに移動させてるんだけど、その時はまだ組織がある程度残ってたというのが、骨の残り具合からわかるらしい。「最古でも最大でも絢爛でもない」が、この古墳から学べること+この古墳が提起した謎の価値は圧倒的に高い。2019/01/14
サンチェス
2
昔の墓からわかることは、当時墓を作り埋葬した人たちが「死」に対して抱いていた思いである。葉佐池古墳から出土した木の棺は砕けていて、また副葬品も破壊されていた。このことから、死者に対して「蘇って欲しい」という感情はなく「もう蘇らないで欲しい」と思っていたことが想像できるだろう。世界の宗教を見れば、魂が帰ってくると考えた古代の国は魂の器であるミイラを作り、終末に審判が下されると考える世界的な宗教は現在でも土葬である。このような宗教感とは異なっていることに興味を抱くきっかけとなる本となるはずだ。2016/12/21