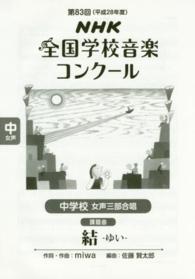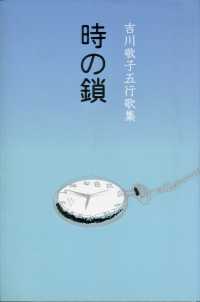- ホーム
- > 和書
- > 児童
- > 学習
- > 文明・文化・歴史・宗教
目次
1 イスラームのひろがり(世界のなかのイスラーム;イスラームのひろがり方;聖者信仰ってなに?;枝分かれするイスラーム;イスラーム法のなりたち;さまざまな巡礼のかたちとその役割)
2 イスラームと他者(ワクフ:イスラーム社会を支えたしくみ;ムスリムとそれ以外の人びととの関係;アラビア語:イスラーム社会の共通語)
3 イスラームと世界(イスラーム社会と科学の発展;イスラーム社会とヨーロッパ;イスラーム社会と日本)
著者等紹介
長沢栄治[ナガサワエイジ]
東京大学東洋文化研究所教授。東京大学経済学部卒業、アジア経済研究所を経て現職。専門は、中東地域研究・近代エジプト社会経済史
勝沼聡[カツヌマサトシ]
東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程単位取得退学。博士(学術)。東京大学大学院人文社会系研究科特任研究員、早稲田大学イスラーム地域研究機構研究助手などを経て、慶應義塾大学文学部准教授。専門はエジプトを中心とした近現代中東社会史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chiaki
40
他人の利益のために(アッラーに捧げるために)寄付をする喜捨という行いが、社会全体を支えて来たしくみであることを初めて知りました。また、イスラーム社会においては、ムスリムが多数派になるに従い、ムスリム以外の人々(ユダヤ教徒やキリスト教徒など)と、ある程度の決まりを設けて共存するしくみがかつてはあり、互いの信仰や文化を共有していたのだとか。一方で宗教間の争いの歴史の根深さも痛感。和歌山県沖の「エルトゥールル号遭難事件」は、トルコとの友好のしるし。私もトルコ記念館を訪れたことがあり、イスラームを身近に感じる。2021/05/25
遠い日
9
「イスラームってなに?」シリーズ3。昨今のイスラームの世界の印象は、なにやら過激で高圧的なものに感じられるが、本来、これまでのイスラームの広がり方を読むと、穏やかで強制的に布教したのではなくて、その土地土地の人々に自然と受け入れられるようになるまで時間に任せたような感じだ。知らないことは怖い。信仰とその考え方は、反駁しあうものではなく、お互いに認め合うためのもの。2018/03/11
のん@絵本童話専門
3
chiakiちゃんにオススメしてもらった一冊!イスラム教が世界に広まっていく過程の話。その中で特に印象に残ったのは、イスラム教はとても他宗教や異文化、弱者に対して寛容であるということでした。女性の社会的立場の低さや昨今のテロ行為で、真逆のイメージが強い。色んな側面があるのが当たり前だと思いますが、本来はそうだったのかと。こちらのシリーズ内では欧米のキリスト教社会への批判を躊躇なくしていて、イスラーム側の立場に立って物事を考えられている感じがします。こちらはシリーズ4巻と併せて読んだ方がいい!2021/06/17
Go Extreme
1
ムスリムと本当の友に コーランか剣か は誤解 聖者信仰 バラカ ズィヤーラ スンナ派 多数派 主流 シーア派 アリー 子孫 イスラーム法 シャリーア コーラン スンナ 法基本 ウラマー イスラム法学者 メッカ巡礼 ハッジ ウムラ 巡礼 社会発展 交流促進 ワクフ 社会支える寄付 ムスリム 他宗教徒 関係 庇護民 ズィンミー 信仰自由 日常交流 文化尊重 アラビア語 共通語 啓典言語 科学継承 アラビア科学 ギリシア継承発展 バイト・アル=ヒクマ 智恵の館 欧州支配 対立助長 エルトゥールル号 日土友好2025/04/24
あさつゆ
1
ムスリムとそれ以外の人たちが共存してきた歴史が書かれていた。「チェスを楽しむユダヤ人とムスリム」の絵が印象に残った。2024/05/05
-

- 電子書籍
- 帝都妖怪新聞 角川ソフィア文庫
-

- 電子書籍
- 11号 〈3〉 - 世界一のピュア・ラ…