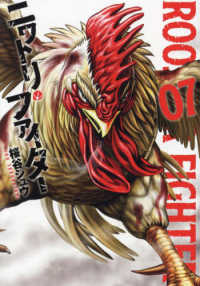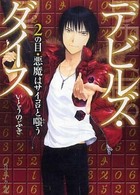出版社内容情報
ニューギニア高地、始源の文明史! 文明との接触から30年、ニューギニア高地民族の石器時代に生まれ、成人した語り部たちと暮らした2年間の記録と聞き書き。
この年代記は二十世紀の世界の辺境で起こった歴史を記したものである。世界の辺境。二十世紀の中葉に初めて世界文明史のなかに呑みこまれたニューギニア高地の一民族を呼ぶには、その言葉がふさわしい。
だが、イエスが彼の終末運動を始めた時、彼の活動していたガリラヤ地域はローマ帝国世界の辺境だったのではあるまいか。少なくとも彼が活動していた時、ローマ帝国の文明の中心においては、その運動が知られることはなかったのである。イエスの終末運動がキリスト教となって世界文明史を転回させることになろうとは同時代の文明の中心にいた者達には夢想だにできなかったであろう。
来るべき文明の芽がどこに潜んでいるか、同時代の人間には窺いしることはできない。
本書は、しかし、その可能性に賭けているのである。
始まったばかりのこの千年紀に世界が進んでゆく萌芽はひょっとしたら、世界の辺境、ニューギニア高地に芽生えたのではないか?
このいささか誇大妄想的な問いかけをもって、本書は書き綴られた。
本書の執筆のきっかけは当時、S社の編集者をされていたOさんのニューギニア高地に関するエッセイ集を出さないかというお申し出に誘発されたものである。当時、私は、フイールドワークを行ったニューギニア高地のインボング族の民族誌を書こうとして壁にぶつかっていた。民族誌というエクリチュールの制度を通しては私が交わっていたインボング族の人々の生命が消し去られてしまうのだ。私は新たな文体を求めていたのだった。Oさんの申し出は私にとって渡りに船とでも言うべきものだった。
書き始めてみると、私のインボングの地での体験、そしてインボングの人達の語りが、それ自体の生命を帯びて、私はその自動書記を行っているようにペンが進んでいくのだった。私は文章が形をとってゆくのに身を任せるしかなかった。騎虎の勢いというのはこうしたことを指すのであろうか。
やがてそれはニューギニア高地のエッセイ集という当初の約束をどんどん逸脱し始めていった。しかし私は筆の勢いに身を任せる以外にはなかった。そして書き終えてみると、それは四百字詰め原稿用紙千五百枚にもなんなんとしていた。Oさんの努力にかかわらず、本書の草稿は商業ベースに乗らないとして、出版を拒否された。
それから本書の草稿は筐底に秘められたまま十年近い歳月が経った。アジア経済研究所の移転に伴う引越し、二年間のオーストラリア派遣などで多くの資料が散逸する中、本書の草稿だけは奇跡的に手元に残った。そして縁あって、彩流社の竹内淳夫社長の知遇を得て、本書は陽の目を見ることになった。
民族誌という制度をはるかに逸脱し、逸脱に逸脱を重ねたこの年代記を書いておいてよかったと私は今、心の底からそう感じている。『平均律クラヴィア曲集』を繰り返し、繰り返し回しながら憑かれたように筆を進めていったあの夜の数々は、今となっては二度と戻ってこない。
石器時代に生きる人々の行動と心性、そして文明と遭遇し、文明に呑みこまれることによって彼らの精神にいかなる変容が生じたのか、そこからいかなる新たな精神のドラマが展開してくるのかが本書の主題である。
そしてそのためには、私は絶妙のタイミングで最高のフィールドに入っていったのだった。今から二十年前、文明接触から三十年、石器時代に生を享け、その中で成人となり、石器時代の生を鮮明に記憶している老人達が未だ多数生存していた。今やインボング族に残る語り部は、私のニューギニアにおける父ウィンディ老人や我が人生の師モゴイ・オガイエ老人など十指に満たない。
そして一九八六年に突如生起した終末運動の嵐。私はその渦の中に巻き込まれ、今日に至るまで続けてきた、そしてこれからも続けていくであろう精神の遍歴の出発点となる強烈な衝撃を受けることになった。それは、インボング族が単なる文明の受容者ではなく、近代西洋文明を突き抜ける主体であることを示す証しであった。あの疾風怒涛を体験することがなければ、この年代記は全く異なったものとなっていただろう。
本書の物語る私のニューギニア滞在は一九八五年一月から一九八七年四月まで、アジア経済研究所の海外派遣員として行われた。アジア経済研究所と私の自由奔放なフィールドワークを裁可して下さった当時の海外業務室長平島成望氏には感謝の意を申し述べたい。また本書の草稿をタイプしてくれた東京都立大学大学院博士課程の馬場淳君の存在がなければ本書の刊行は大きく遅れていたであろう。馬場君の助力にも感謝の意を申し述べたい。だが何よりも彩流社の竹内淳夫社長の出版快諾と情熱がなければ、本書がこの世に現れることはなかったであろう。私は飯田橋の彩流社の編集室で竹内社長と交わした会話を忘れることができない。社長の確かな読みと的確な指示によって本書は刊行にこぎつけたのである。竹内社長の御厚情には心からの感謝の念を捧げたい。
そして私を迎え入れてくれ、私を人間存在に対する永遠の探求者へと導いてくれた驚嘆すべき民、インボング族の人々、とりわけ本書の登場人物のすべてには、その恩義に対する正当な感謝の言葉を見出すことも難しい。この書の出版がその恩義にいささかなりとも報いることになれば幸いである。そして『遠野物語』の筆法を借りれば、願わくばこの書をして全ての文明人を戦慄せしめんことを。私の魂を震憾させた如く。
(「はじめに」より)
日本図書館協会選定図書に決定
内容説明
今、壮大な共同幻想がニューギニア高地から立ち上がる!文明との接触から30年、その前の石器時代に生まれ、成人した語り部たちと暮らした2年間の記録と聞き書き。
目次
第1部 石斧(サイモン・アペの章;オガネの章;モゴイ・オガイエの章;白人到来の章;インボング族の変化;戦争と平和)
第2部 十字架(リバイバルの勃発;アンボ・ルートの告白;ククの章;さらば、パプアニューギニア)
著者等紹介
塩田光喜[シオタミツキ]
1979年3月東京大学教養学科文化人類学課程卒。アジア経済研究所調査研究部入所。1985年1月海外派遣員としてパプアニューギニアへ。1987年4月帰国。2003年3月海外調査員としてオーストラリアへ。2005年3月帰国(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
カネコ
メルセ・ひすい
Arte
-
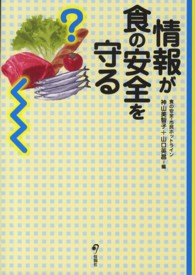
- 和書
- 情報が食の安全を守る