出版社内容情報
非認知能力とは、成績やIQのように数値で図れる力とは異なり、<物事にやる気を出して集中する力、粘り強く取り組む力、自分のことを理解する力、自己主張や他者と協力する力>など、よりよく生きるための力のことです。
この本では10代の子どもたちが直面する 家族・友人との関係性、考え方のくせ、自尊感情、心と体の変化の悩みの場面をとりあげました。
それぞれのワークを通して、他者との意見や考え方の違いに触れることで視野を広げ、つながりを感じることで孤立の解消や自己理解の深まりなどを感じるきっかけになることを目指しています。
内容説明
非認知能力とは、成績やIQのように数値で測れる力とは異なり、“物事にやる気を出して集中する力、粘り強く取り組む力、自分のことを理解する力、自己主張や他者と協力する力”など、よりよく生きるための力のことです。この本では10代の子どもたちが直面する家族・友人との関係性、考え方のくせ、自尊感情、心と体の変化の悩みの場面をとりあげました。それぞれのワークを通して、他者との意見や考え方の違いに触れることで視野を広げ、つながりを感じることで孤立の解消や自己理解の深まりなどを感じるきっかけになることを目指しています。
目次
1章 日常生活のストレス・自己管理(朝の準備に時間がかかって毎日ギリギリ!;授業がわからない、集中できない ほか)
2章 もっと上手な人との付き合い方(アサーションで自分の想いを上手に伝える;クラスメイトからどう思われているか気になる ほか)
3章 好きな人、性のこと、コンプレックス(ずっと彼氏(彼女)や親友とつながっていないと不安
中学生のスキンシップはどこまでしていいの? ほか)
4章 家族関係の悩み(両親のケンカを見るのがつらい;ストレスを自分で和らげる方法;イライラして家族に暴力的になってしまう;友達には言えない家庭の悩みがある;親や兄弟に嫌なことを言われても嫌だと言えない)
著者等紹介
高口恵美[コウグチメグミ]
精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師。2011年福岡県立大学大学院人間社会学研究科修了。精神科ソーシャルワーカーとしての勤務を経て、現在は、福岡県教育委員会などにおけるスクールソーシャルワーカースーパーバイザーや西南女学院大学保健福祉学部福祉学科の非常勤講師に従事する
大黒剛[オオグロツヨシ]
臨床発達心理士。九州大学大学院人間環境学府行動システム心理コース修士課程修了。人間環境学修士号取得。児童相談所、スクールカウンセラーを経て、現在は児童養護施設、刑務所、保護観察所にてカウンセラー業務に従事する
田島千穂[タシマチホ]
公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士。松山東雲女子大学人文学部人間心理学科より長崎国際大学人間社会学部社会福祉学科へ編入学し2007年卒業。松浦市教育委員会学校適応指導教室指導員を経て、現在、長崎県教育委員会スクールカウンセラー、長崎県立佐世保高等技術専門校PSWとして従事する
松本智子[マツモトトモコ]
臨床心理士、公認心理師。2005年横浜国立大学大学院教育学研究科修了。佐世保市子育て家庭課(現・子ども未来部)心理相談員を経て、2007年から佐世保市子ども発達センターにて幼児期~学童期の子どもおよび保護者への心理支援に従事する(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
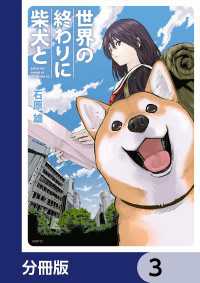
- 電子書籍
- 世界の終わりに柴犬と【分冊版】 3 M…
-

- 電子書籍
- 大富豪と遅すぎた奇跡【分冊】 12巻 …
-
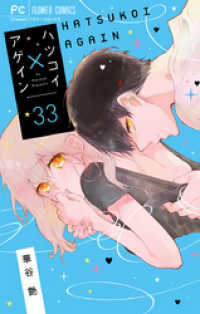
- 電子書籍
- ハツコイ×アゲイン【マイクロ】(33)…
-

- 電子書籍
- ガンダムフォワードVol.1 ホビージ…
-
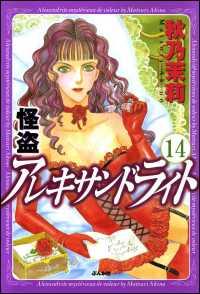
- 電子書籍
- 怪盗 アレキサンドライト(分冊版) 【…



