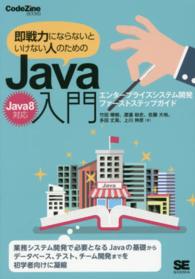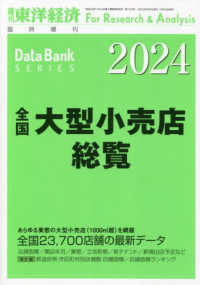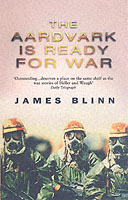内容説明
セラピストにとって心理療法とはいかなる行為なのか、心理療法におけるクライエントとセラピストの関係性(心理療法的関係性)はどうあるべきなのか。本書で述べられる「心理療法的関係性」をクライエントに提供することで、セラピストは「他者」として自身の存在を差し出し、その存在と関係によってクライエントはこれまでにない新しい他者体験をする。そうした体験と作業を通して、人々が背負うさまざまな「こころ・からだ」の問題は回復・修復されていく。これこそが(セラピストの存在とその関係による)「心理療法」であると著者は説く。話題となった「最終講義」の内容を中心に、平井正三氏との対話と討論、「オープンダイアローグアプローチ」の臨床理念やユングとコフートにおける「self」についての考察、さらに荘子の思想の心理療法的理解を通して、心理療法の本質といえる他者との深い「関係性」や「対話」の重要性に迫る、自らの個人史にも触れた著者渾身の臨床と思索の集大成。
目次
第1部 最終講義―「現代的不幸」の時代における人と人との小さな対話、そして心理療法(「現代的不幸」の時代;「現代的不幸」の時代とポストモダン問題;「“私”時代」と「デモクラシー」そして「セラピー(心理療法)」 ほか)
第2部 クライエントとセラピストの心理療法的関係性―セラピストとは何者なのか、心理臨床学的対話を通して考える(セラピストがクライエントに提供する「心理療法的関係性」―セラピストの存在とその関係による心理療法;心理療法における治療機序・治療作用の問題―平井正三著『意識性の臨床科学としての精神分析』を巡っての内的な対話と討論;「象」の巨大さに圧倒されながら群盲仲間と「象」について語り合う愉快―平井論文への応答と対話 ほか)
第3部 人生の不思議な「謎」から臨床心理学徒へと導かれて―「内なるクライエント」と対話し続ける(患者から学ぶ;河合隼雄先生に受けた教育分析の日々;「私の中の/私を超える/私ならざるもの」の働き ほか)
著者等紹介
渡辺雄三[ワタナベユウゾウ]
1941年生まれ。臨床心理士・社会学博士(関西大学)名古屋大学中退。佐藤神経科病院、医療法人生々会松蔭病院、渡辺雄三分析心理室、人間環境大学教授・大学院特任教授を経て、人間環境大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
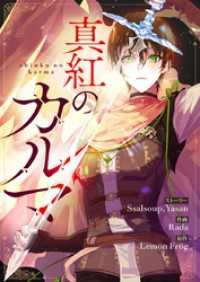
- 電子書籍
- 真紅のカルマ【タテヨミ】第117話 p…