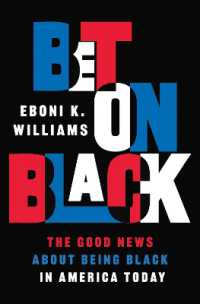内容説明
高次脳機能障害の当事者と臨床心理士による対談を、日本臨床心理士会の協力を得て書籍化。中途で障害を負うということについて語り、支援の在り方を問う。日々の生活において症状がどのような現れ方をするのかが当事者感覚をもって具体的に語られ、さまざまなエピソードには、神経心理学の視点からの解説も加えられる。目に見えない障害とも言われる高次脳機能障害の症状と、そこから生じる日々の生活上の困り感や心理的反応について、周囲の人が理解する手助けとなるよう構成されている。
目次
1 発病前の生活の様子
2 発病
3 入院中の様子
4 退院後に気付いたこと
5 対応にたどり着く
6 環境調整
7 中途で障害を負うとは
8 臨床心理士に望むこと
著者等紹介
鈴木大介[スズキダイスケ]
文筆業。1973年千葉県生まれ。子供や女性、若者の貧困問題をテーマにした取材活動をするルポライターだったが、2015年(41歳)で脳梗塞を発症して高次脳機能障害当事者に。その後は高次脳機能障害者としての自身を取材した闘病記を出版
山口加代子[ヤマグチカヨコ]
大学卒業後、横浜市中央児童相談所に心理判定員として入職。横浜市衛生局心理相談員を経て、平成3年横浜市総合リハビリテーションセンターに臨床心理士として入職。平成31年同退職。現在、中央大学大学院講師。リハビリテーション心理職会顧問。日本高次脳機能障害友の会顧問(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。