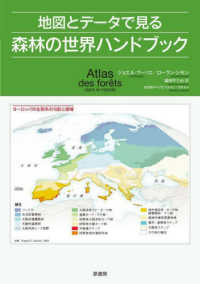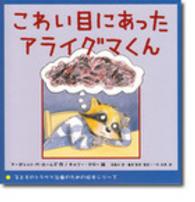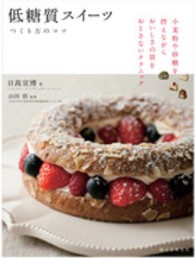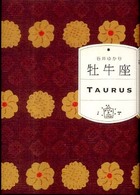出版社内容情報
本書で詳述する“CASEアプローチ”は患者の自殺念慮を導きだすための画期的な面接戦略である。米国の自殺学・死生学講座で必読教科書として採用されている名著。
本書で解説する“CASEアプローチ”は,クライエントの自殺念慮を導きだすための画期的な面接戦略である。臨床上の叡智,示唆に富む事例,自殺企図患者への面接技術を解説した本でこの本に勝るものはない。著者は自殺思考,自殺行動のニュアンスと本質を体系的にアセスメントするための実践的,常識的,実施可能な技術を多くの詳細なケーススタディをもとに紹介している。
全米各地で自殺学の専門書として,また臨床家の実践的教本として高い評価を受け,自殺学・死生学講座の必読教科書として採用されている名著待望の邦訳。
第?T部 自殺経験:自殺の病因論,現象学,リスク要因
第1章 自殺:究極のパラドックス
第2章 メールストロームへの転落:自殺の病因学と現象学
第3章 リスク要因:死の前兆
第?U部 自殺念慮を引き出すために――その原則、ならびにテクニックと戦略
第4章 面接にのぞむ心構え「自殺をタブー視していないだろうか?」
第5章 有効な情報を得る技法:話しにくい秘密を明かしてもらう簡便な方法
第6章 自殺念慮を引き出すには:実践的技法と効果的戦略
第?V部 実践的リスクアセスメント――柔軟な戦略と確かな記述
第7章 総括:安全で効果的な意思決定
内容説明
自殺に関する悪意ある神話を解き明かす。クライエントの自殺念慮を導きだすための画期的な面接テクニック。
目次
第1部 自殺経験:自殺の病因論、現象学、リスク要因(自殺:究極のパラドックス:メールストロームへの転落:自殺の病因学と現象学;リスク要因:死の前兆)
第2部 自殺念慮を引き出すために―その原則、ならびにテクニックと戦略(面接にのぞむ心構え「自殺をタブー視していないだろうか?」;有効な情報を得る技法:話しにくい秘密を明かしてもらう簡便な方法;自殺念慮を引き出すには:実践的技法と効果的戦略)
第3部 実践的リスクアセスメント―柔軟な戦略と確かな記述(総括:安全で効果的な意思決定)
著者等紹介
松本俊彦[マツモトトシヒコ]
佐賀大学医学部卒業。神奈川県立精神医療センター、横浜市立大学医学部附属病院精神科、国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部室長などを経て、現在、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター副センター長/薬物依存研究部診断治療開発研究室長
鈴木剛子[スズキヨシコ]
グリーフ・カウンセリング・センター(GCC)代表、グリーフ・カウンセラー、GCCグリーフ・カウンセラー養成講座主催及び講師。麗沢大学コミュニティ・カレッジ、桜美林大学アカデミー講師、International Work Group on Death,Dying&Bereavement、日本死の臨床死生学会、日本自殺予防学会会員。国際基督教大学教養学部言語学科卒。ボッテガ・ヴェネタ・ジャパン、モスキーノ・ジャパン代表取締役を歴任
近藤正臣[コンドウマサオミ]
1965‐1968国際基督教大学教養学部社会科学科卒業(学士号取得)。1968‐1972中央公論社書籍編集部勤務。1972‐74サイマル・インターナショナル、日本コンベンションサービスなどで通訳。1974‐76国際基督教大学行政大学院(修士号取得)。1976‐2011大東文化大学勤務。早稲田大学・立教大学・国立リハビリテーションセンター学院・都留文科大学で非常勤講師、AIIC(国際会議通訳者協会)メンバー、通訳理論研究会発起人、日本通訳翻訳学会初代会長、文部省教科書審査委員(英語)、ILO総会・PTTI会長専属通訳者などの通訳活動。2011大東文科大学退職、名誉教授
富田拓郎[トミタタクロウ]
1997年早稲田大学大学院人間科学研究科健康科学専攻博士後期課程満期退学。博士(人間科学)。臨床心理士。マルチシステミック・セラピー(MST)認定スーパーバイザー。国立精神・神経センター精神保健研究所流動研究員、科学技術振興事業団科学技術特別研究員、東洋英和女学院大学非常勤講師、東京都スクールカウンセラー、国立精神・神経センター精神保健研究所司法精神医学研究部研究員、首都大学東京非常勤講師、を経て、関西大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きくりん
ひろか
hsg